海沢大滝から大岳山・鍋割山(奥多摩)
![]()
![]()
| date | 2014/6/15 晴 |
| コース | 海沢園地〜海沢大滝〜大岳山〜鍋割山〜大楢峠〜海沢園地 |
| 実働 | 登り:2h20m、下り:1h55m、計:4h15m。 |
| 概要 | 海沢大滝見物と大岳山・大楢峠周回。 |
| メンバー | すうじい(単独) |
| 行程 | →:山道・踏跡、→:溯行、→:藪漕ぎ・不明瞭な踏跡、=:車 【6月15日】 晴 自宅5:45=7:45海沢園地8:10→8:50海沢大滝9:10→10:25 1075Mコル10:35→11:00大岳山11:05→11:55鍋割山12:05→→大楢峠12:45→13:10海沢園地13:30=15:40自宅 |
| 使用装備 | 軽登山靴、GPS、コンデジTG620、ストック、三脚、E-P2 |
| 不用装備 | |
| 記録 |
脚のトレーニングのため、短時間登頂と滝見に出掛けた。今回は、海沢園地のヘアピンに車を停め、三ツ釜滝・ネジレ滝・大滝を見物し、海沢遊歩道経由で大岳山に登り、鍋割山から大楢峠へ下るコースを辿ってみた。
【6月15日】 晴 先客のいない海沢園地のヘアピン付近に車を停め、ストックを持って、歩き始める。三ツ滝も結構な水量で、接近するとドボンしそうだ。コンデジでお茶を濁す。三ツ釜滝中段も、なかなかの水量だ。連瀑帯を見やりながら、左岸の巻道を登って行く。 折角だから、ネジレ滝も見物して行こう。この水量なら、大滝も期待出来そうだ。大滝下降点の小尾根肩状に出て、滝壺へと下降する。期待通りの水量で、飛沫が冷たい。三脚を立てて撮影するが、寒くて堪らない。寒さに負けて、滝を見ながらの休憩は断念する。下降点の小尾根肩状まで登り返してから、行動食を摂る。 肩状から、小尾根を登る。かなり高度を上げ、左岸トラバースに入る。やがて再び沢に近付くようになると、右岸へと渡らねばならない。3月に来た時は、スノーブリッジを利用したが、今回も橋らしいモノは見当たらない。適当な所で、濡れることなく渡渉する。 右岸に渡れば踏跡が復活し、しばらくワサビ田のモノレール沿いに、黙々と登る。前回の引返し点である、845M右岸枝沢出合から、この枝沢沿いの道となる。今年の大雪と大雨のせいか、道は荒れ気味だ。急登に大汗をかいて、1075Mコルに至る。海沢枠木沢右俣'11-11のツメ地点である。 ザックを下して、暫し休憩しよう。枠木沢右俣源流からは、沢の音が近い。コルからは、尾根道を登って行く。しばらくは、笹の林床となる。やがて傾斜が緩み、左へトラバースすると、鋸山からの縦走路に出る。 縦走路を左へ辿ると、最後の急登を経て、2週間ぶりの大岳山頂だ。今回は、晴れてはいるものの富士山の姿が見えない。小休止の後、山頂の賑わいを後にして、北へ急降下する。 大岳神社の可愛い狛犬を見て、縦走路を北へ向かう。鍋割山への尾根道分岐で、今回は尾根道に入る。人通りが少なくなって、気持ちの良い尾根道が続く。誰もいない鍋割山頂で、最後の休憩をする。W杯コートジボワール戦敗北のメールが入る。 鍋割山北尾根の、割と明瞭な踏跡を下って行く。途中、コアジサイの群落などもあり、概ね快適だ。林道に近付く辺りの斜面で、踏跡が不明瞭になるが、尾根に忠実に下れば、林道終点・大楢峠に降り立つ。どのコースを歩いたのか、家族連れが寛いでいた。 大楢峠からは、林道を歩いて海沢園地のヘアピンへと下る。愛車の周りには、ラフティング集団の車が停まっていた。この日も、大した渋滞に妨げられることもなく、帰宅する。 |
![]()
GPS軌跡
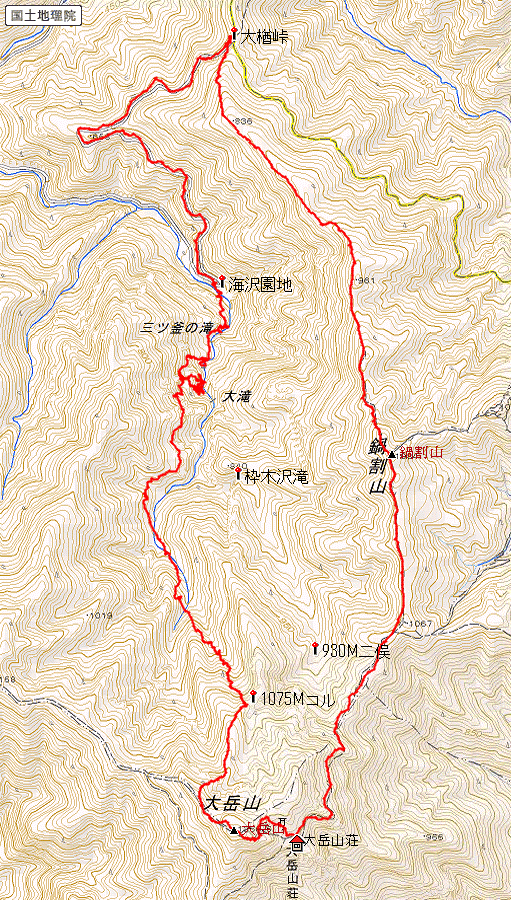
アルバム
 |
三ツ釜滝 |
| 三ツ釜滝 |  |
 |
三ツ釜滝 |
| ネジレ滝 |  |
 |
海沢大滝 |
| 海沢大滝 |  |
 |
海沢大滝 |
| 海沢大滝 |  |
 |
1075Mコルから枠木沢源流俯瞰 |
| 1075Mコル |  |
 |
1075Mコル |
| 縦走路に合流 |  |
 |
大岳山頂 |
| 鍋割山への分岐 |  |
 |
鍋割山への尾根道を行く |
| 鍋割山頂 |  |
 |
大楢峠への山道で咲くコアジサイ |
| 大楢峠 |  |
MR712_ 七代滝・綾広滝から大岳山・上高岩山'14-06
![]()
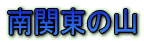 |