金山岳西尾根・剣ヶ峰・八丁尾根(両神)
![]()
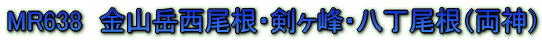
| date | 2010/1/10 晴 |
| コース | 落合橋〜1389P〜金山岳〜剣ヶ峰〜金山岳〜八丁峠〜上落合橋 |
| 実働 | 剣ヶ峰までの登り:2h25m、剣ヶ峰からの下り:2h55m、計:5h20m。 |
| 概要 | 金山岳西尾根から八丁尾根縦走。 |
| メンバー | すうじい(単独) |
| 使用装備 | 登山靴、アイゼン、ヘルメット、ストック、μ725SW |
| 不用装備 | 8mmx30mザイル、ハーネス、8環、細引、ピッケル、オーバーミトン、E-1、ED12-60mmF2.8-4SWD |
| 行程 | →:山道・踏跡、→:藪漕ぎ・踏跡無し、**:アイゼン、*→*:藪アイゼン、車:=。 【1月10日】 晴 自宅3:10=花園IC 4:10=4:50影森コンビニ5:10=5:30道の駅大滝温泉5:50=6:50落合橋7:30**1389P 8:00**藪取付8:10*→*1460M岩場下8:20*→*1570M枝尾根ノ頭9:00*→*9:30金山岳9:40**10:05剣ヶ峰10:30**金山岳10:55**東岳11:10**竜頭山11:35**12:00西岳12:15**13:00索道跡13:25→八丁峠13:30→14:05上落合橋14:30=15:25道の駅大滝温泉15:35=16:00影森コンビニ16:15=花園IC 17:00=18:30自宅 |
| 記録 | '07年12月の金山沢中間尾根(金山岳西尾根)・剣ヶ峰・大キギ・八丁尾根、'08年12月の八丁尾根・大キギ・剣ヶ峰・金山岳西尾根下降に続き、またまた金山岳西尾根と八丁尾根縦走に出掛けた。 【1月10日】 晴 前々日に、中津川側から県道210号線と林道金山志賀坂線の偵察をしておいたので、小倉沢のニッチツ社宅先の日陰に残る雪の手前でタイヤチェーンを装着する。5cmほど積雪のある落合橋・上落合橋間の駐車スペースには、先客の車が一台。八丁尾根縦走であろうか。 準備して、始めからアイゼンを装着して出発。落合橋袂の登山口には、立入禁止のロープが張ってある。痩せ尾根取付は、いつもながら慎重に登ろう。30分ほど登ると、1389Pに至る。ヒノキ林に覆われたピークである。1389Pから、一旦コル状へと下る。 コル状から緩やかに少し登ると、1400M付近で金山沢右俣左沢右岸杣道がトラバースを始め、西尾根から離れて行く。適当な所から、藪尾根に取り付く。尾根筋に沿って、適当に登って行く。踏跡らしいものは無いが、樹林帯の下藪は薄い。 藪尾根に取り付いて、10分ほど登ると、西尾根唯一の登攀的要素のある場所、1470M岩場下に出る。正面やや左手から岩場に取り付いて登る。一段登った所から、左へと続くバンド状を辿る。特に困難さは無い。このバンド状を進むと、1480M乗越ギャップの下に至る。このギャップから、再び尾根上へとよじ登る。 岩場を越え、痩せ尾根を進むと、尾根が幅広になり、ややハッキリしなくなる。下りのことを考え、黄色のすずらんテープで、所々マーキングして行く。傾斜が急になり、肩状を経て、1570M枝尾根ノ頭に到達する。枝尾根ノ頭から、顕著な枝尾根が南西側に派生している。枝尾根ノ頭から痩せ尾根を少し進むと、尾根は再び広がってくる。 幅広尾根の傾斜が緩むと、見覚えのあるマーキングが並び、金山岳北コルへのトラバース開始地点である1640M付近となる。ここから、ほぼ水平に北側へとトラバースすれば、比較的容易に北コルの縦走路に出ることが出来る。今回は、再び傾斜が強くなり、やや密になった樹林帯の斜面を、金山岳山頂に向けひたすら登って行く。 1640Mの緩傾斜帯から、急傾斜の樹林帯を登って行くと、20分ほどで金山岳山頂に至る。小休の後、剣ヶ峰へ向かう。金山岳から前東岳を経て、25分で剣ヶ峰に着いても、誰もいなかった。また、西の方の山々は、雲に隠れがちであった。 剣ヶ峰を後にして、金山岳へと戻る。途中、八丁尾根を縦走してきたと思しき二人パーティと擦れ違う。彼らは、アイゼンを装着していなかった。駐車スペースの車の主だろうと推測する。剣ヶ峰から40分で、東岳山頂に至る。 写真を撮ってベンチから少し先へ進むと、大キギ北西壁の良く見える稜線となる。同じ場所から、御荷鉾山方面の眺めも良い。東岳北西面の急降下開始鎖場を下る。鎖が埋まっていたら、結構苦労しそうな場所である。東岳の下り途中から、竜頭山と西岳を望むと、急な登り返しがキツそうだ。 一旦キレット底まで下り、岩場を登り返し、一つ岩峰を左から巻いて、竜頭山の竜頭神社奥宮に至る。 奥宮から北東へ急降下する小尾根には、恐怖の連続鎖場のある尾ノ内沢道が付けられている。特に冬場は、下降したくないルートなのである。 竜頭山北西側の下り始めも、なかなか大変である。下りきった次のキレット底が、風穴と呼ばれる場所だ。右手の急峻なルンゼが、尾ノ内沢道の難所「金ササゲ」へと落ち込んでいる。再び登りに転じ、西岳へと向かう。 西岳山頂まで来れば、先ずは一安心。小休しよう。雲に隠れがちだった御座山も、その姿を見せている。この位置から見ると、大キギも東岳の一部と化している。西岳の北側の尾根には、西岳新道という名のルートがあるのだが、これもまた、下りにはちと困難が伴う。 西岳から少し下って、行蔵坊ノ頭へと登り返す。その先の肩状を縦走し、下って行くと、索道中継点跡に出る。眺めが良いので、小休する。ここででアイゼンを外し、数分で八丁峠に至る。峠からは、落葉樹林の枯葉の積もった登山道を、大きくジグザグを切って下る。 やがて針葉樹の植林帯に入り、1180M右岸枝沢を右岸に渡って、八丁沢右岸沿いに出る。2万5千図の登山道破線は、実際とは異なる。この1180M右岸枝沢出合には、15m階段状スダレ滝が懸かるのだが、これが凍結していた。枝沢出合上流の八丁沢には、10m滝が氷瀑化していた。上落合橋近くの八丁沢も、かなり凍結していた。 駐車スペースの車の主は、まだ戻っていなかった。往きのチェーン装着地点でチェーンを外し、帰りの県道210号線で、前々日の偵察時に撮り損なった中津川右岸の氷柱を撮影する。帰りの関越道で、30分ほど事故渋滞につかまった。 |
![]()
GPS軌跡

アルバム
 |
上落合橋登山口(1月8日偵察時) |
| 上落合橋から上落合橋登山口(1月8日偵察時) |  |
 |
上落合橋から八丁沢(1月8日偵察時) |
| 路肩スペースから落合橋登山口(1月8日偵察時) |  |
 |
落合橋登山口から少し登った尾根取付付近 |
| 1389Pへの登り |  |
 |
1389P先の下り |
| 杣道がトラバースを始める1400M藪尾根取付 |  |
 |
1440M付近 |
| 1470M岩場 |  |
 |
1470M岩場 |
| 1480M下バンド状 |  |
 |
1480M乗越 |
| 1570M枝尾根ノ頭より正解尾根肩状 |  |
 |
1570M枝尾根ノ頭から枝尾根 |
| 以前、金山岳北コルへトラバースした1640M付近から尾根を俯瞰 |  |
 |
1640M付近から北側 |
| 1640M付近から尾根を見上げる |  |
 |
金山岳を振り返る |
| 前東岳から剣ヶ峰北峰 |  |
 |
剣ヶ峰から金山沢右俣ノ頭 |
| 剣ヶ峰から金山岳(右) |  |
 |
東岳から小倉沢 |
| 東岳から金山岳西尾根(左手前)と狩倉尾根 |  |
 |
東岳から金山岳(右)と前東岳(中央奥) |
| 東岳から大キギ |  |
 |
東岳から御荷鉾山方面 |
| 東岳北面の鎖場 |  |
 |
東岳北面から竜頭山と西岳 |
| 東岳北面から赤岩尾根 |  |
 |
東岳北面から狩倉岳 |
| 竜頭山の竜頭神社奥宮 |  |
 |
竜頭山北西側の鎖場を振り返る |
| 風穴キレットルンゼ |  |
 |
西岳から御座山 |
| 西岳から東岳(左)と金山岳(中央) |  |
 |
西岳山頂 |
| 西岳から行蔵坊 |  |
 |
行蔵坊ノ頭の北西稜線から二子山越しの御荷鉾山 |
| 行蔵坊ノ頭の北西稜線から赤久縄山 |  |
 |
行蔵坊ノ頭の北西稜線から西上州の山々 |
| 1570M肩付近から東岳・金山岳 |  |
 |
八丁峠 |
| 八丁峠からの下り |  |
 |
八丁沢(金山沢左俣)10m滝氷瀑 |
| 八丁沢下流部 |  |
 |
中津川左岸氷柱 |
MR597_ 金山沢中間尾根・剣ヶ峰・大キギ・八丁尾根'07-12
MR615_ 八丁尾根・大キギ・剣ヶ峰・金山岳西尾根下降(両神)'08-12
![]()
| 両神山の山行記録へ |
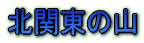 へ へ |
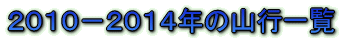 |