滝川右岸道偵察(奥秩父)
![]()

【注意!】滝川右岸道は、迷い易い箇所・危険箇所が多く、曲沢より上流側は、あまり踏まれていません
| date | 2009/9/16 曇のち晴 |
| コース | 山薊橋先下降点〜高滝下流吊橋〜滝川右岸道〜曲沢横断点〜金山沢横断点〜1290M肩先崩壊ザレルンゼ引返点(往復) |
| 実働 | 往き:4h37m、帰り:3h08m、計:7h45m。 |
| 概要 | 滝川右岸道を、槇ノ沢手前の1290M肩先崩壊ザレルンゼまで偵察。 |
| メンバー | すうじい(単独) |
| 行程 | →:山道・踏跡、→:溯行、→:藪漕ぎ・不明瞭な踏跡、=:車 【9月16日】 曇のち晴 自宅4:05=7:10山薊橋先下降点7:30→右岸道合流点8:10→9:00曲沢9:13→曲沢枝沢9:30→→10:30金山沢10:55→→12:15 1290M肩小屋跡12:25→→12:55崩壊ザレルンゼ引返点13:27→→1290M肩小屋跡13:55→→14:20金山沢14:30→→15:17曲沢枝沢15:27→曲沢15:43→16:05沢小屋沢16:15→高滝下吊橋分岐(右岸道合流点)16:30→高滝下吊橋1647→17:05山薊橋先下降点17:25=17:40道の駅みとみ18:05=19:55自宅 |
| 使用装備 | 軽登山靴、ヘルメット、μ-725SW、杖(拾った棒) |
| 不用装備 | アイスハンマー、渓流靴、E-1、ED9-18mmF4-5.6、三脚 |
| 記録 | '82年10月の二つの山行(滝川水晶谷・雁坂峠'82-10、滝川槇ノ沢・唐松尾山・古礼山'82-10)で、その利用価値が高かった滝川右岸道であるが、滝川金山沢・曲沢下降'04-06、滝川右岸道・金山沢・曲沢下降'08-06の山行では、荒れ方が酷く、二度とも道を外してしまうほどであった。今回、槇ノ沢八百谷溯行の偵察も兼ねて、滝川右岸道を槇ノ沢まで辿る計画を立てた。 【9月16日】 曇のち晴 R140の山薊橋先で、路肩の駐車スペースに車を停め、7:30出発。かなり遅くなってしまった。下り始めた所に、杖用の棒切れが、沢山立て掛けてあったので、有り難く一つ拝借する。小尾根状を絡み、右手のカレ沢状沿いに下ると、トロッコ軌道跡に降り立つ。右手上流側へと少し行くと、もう一つの小尾根を回り込んで、再び下降の踏跡を辿る。小沢の左岸を下り、最後にこれを渡って、吊橋へと向かう。 下降点から吊橋まで、15分ほどの下りである。この吊橋、高滝下流に架かっている。5年前には、床板が腐りかけていて、ちと怖かったが、昨年には、床板が金属製に整備されている。 高滝下流の吊橋を渡り、滝川右岸の小尾根を登る。やがて、尾根の幅が広がり傾斜が緩むと、右上方へとトラバース気味に登るようになる。吊橋から25分ほどで、右岸道に合流する。この吊橋への下降点は、帰りに暗いと、うっかり見落として直進してしまいがちだ。 右岸道に合流してしばらく進むと、最初の崩壊地点に差し掛かる。ここは、小さく高巻く。右岸道に合流して15分ほどで、道が分岐する。右手の藪っぽい踏跡は、沢小屋沢出合と曲沢出合との間で滝川本流に架かる、古い吊橋へと続くらしい。 右岸道に合流して20分、沢小屋沢を横断する。さらに30分歩くと、曲沢を横断する。曲沢横断点の立て札は、健在だ。右岸道も、ここまでは、昼間なら迷うことは無かろう。曲沢から先の踏跡は、少し薄くなる。曲沢から20分弱で、曲沢970M左岸枝沢を横断する。この左岸枝沢手前が、以前来たときには、藪っぽいやや不安定なガレ斜面だったのだが、今回は少しスッキリしていた。 曲沢枝沢から数分で、ロープの張られた崩壊ザレ斜面を横断する。枝沢から15分弱で、・1204尾根と思しき、幅広の緩い尾根を回り込む。曲沢970M左岸枝沢から30分強で、過去2回ミスルートしている問題の岩稜帯に差し掛かる。 踏まれている所を忠実に辿り、斜上するバンドに取り付くことにしよう。前回は、取付下のガレ沢左岸沿いに下巻いたため、急峻なルンゼに突き当たり、トラバース出来ずに下ることになり、随分と下流側に出てしまったのであった。 斜上バンド核心部の岩場トラバースには、残置ロープが懸かる。斜上バンドトラバースを終えると、顕著な岩尾根を回り込む。その先で、崩れ易いガレ土斜面に出る。眼下に金山沢が見下ろせる。踏跡は不明瞭になるが、ここをジグザグに下降して行くと、やがて左手の上流側へと踏跡が現れて、横断点の看板へと至る。 左岸側の小屋跡らしき平坦地で休憩する。この平坦地裏手から、踏跡があるが、最初は不明瞭で崩れ易い。やがて右上へと斜上し、小尾根を越える。すると、次第に踏跡は薄くなる。二番目の小尾根で、踏跡は極端に薄くなるので、この二番目の小尾根沿いに登るのかもしれない。取り敢えず、さらにトラバース気味に、薄い踏跡を辿って登る。やがて左へ折り返して登って行く。 岩根の所で、左手から来る踏跡と合流するようにも見える。ここから右上へと登る。小尾根状を登り、やがて左手の浅い窪状を登ると、古いケーブルが現れる。ケーブル沿いに右上し、適当に登ると、1290M肩と思しき地形に出る。金山沢横断点から、迷いながら1時間20分ほどだった。左手に歩くと、小屋の残骸が残っていた。 少しウロウロして、藪っぽい平坦地の南側へ回り込むことにする。平坦地の南側には、林道跡のような道形が続いていた。これを少し進むと、左手の林の中に、明瞭な踏跡が続くので、これを辿ってみる。すると、東西方向の小尾根上の踏跡と合流する。 この小尾根上の踏跡は、やがて笹藪に邪魔される。北側には、船窪地形が見られる。2万5千図のどこに相当するのか、首を傾げる。こちら側には、明瞭な踏跡はないようだ。林道跡のような道形に戻り、南東面のザレ斜面を少し下ると、傾斜のある樹林帯に入る。ジグザグに下るような踏跡らしきものもある。他方、そのままトラバースを続ける、極めて薄い踏跡もあるようだ。これを強引に辿ってみよう。 半ば強引にトラバースを続けると、急峻な崩壊ザレルンゼに出くわす。こいつの横断は、ザイル確保無しには、ちと無理っぽい。少し上方の林の中を進み、偵察してみたが、この辺りの横断は危険なようだった。崩壊自体を大高巻きするか、或いは、かなり戻ったところから下っていた踏跡らしきものを辿ってみるか、しかなさそうだ。今回は、時間と熱意が不足しているので、ここで引き返しとする。 1290M肩小屋跡から金山沢側への下り始めも、方向が難しい。それでも、帰りは25分で、金山沢横断点に下り着く。右岸側の斜上する踏跡を辿り、土砂斜面の登りに取り付く。土砂斜面に入ると、踏跡は不鮮明になるので、不安定な所を、強引に登る。かなり登ったところで、トラバースの踏跡が現れる。 このトラバース踏跡は、左手の顕著な岩尾根へと続く。顕著な岩尾根を越え、トラバースしてゆくと、岩稜帯核心部の斜上バンドを下ることになる。ロープが下がっている岩場を横切り、斜上バンドを無事下れば、あとはさほど難所は無い。・1204尾根と思しき、幅広の緩い尾根を回り込んで、曲沢枝沢へと向かう。 曲沢枝沢が近付くと、崩壊ザレ斜面を横断するが、さほど傾斜も無いし、よく踏まれているので、不安は無い。曲沢枝沢を横断し、さらに曲沢を横断する。上流側右岸に倒壊した小屋跡がある。右岸側の踏跡も、良く踏まれているので、迷うことは無いだろう。 沢小屋沢横断点付近は、都合3本の沢を横断する形になっているので、踏跡を見失わぬよう注意が必要だ。トラバース道から高滝下吊橋への分岐を、見落とさずに下って行くと、やがて高滝右岸側小尾根を下るようになる。やっと吊橋が見えて来た。 16:47吊橋到着。この分だと、17時過ぎには、車に戻れそうだ。釣り橋を渡り、最後の登りに取り掛かろう。山薊橋先下降点に出て、路肩の車に戻る。帰りは、雁坂トンネルを抜けて、中央道経由で帰宅する。 |
![]()
アルバム
 |
高平(山薊橋先下降点) |
| 軌道跡水平道 |  |
 |
軌道跡水平道、高滝下吊橋下降点 |
| 高滝下吊橋 |  |
 |
滝川右岸道に合流 |
| 滝川右岸道、小崩壊地を振り返る |  |
 |
滝川右岸道 |
| 曲沢横断点 |  |
 |
曲沢左岸枝沢先の崩壊ザレトラバース |
| ・1204尾根1120M付近 |  |
 |
金山沢手前岩稜帯の斜上バンド |
| 斜上バンドを登る |  |
 |
斜上バンドを登り、尾根を乗り越す |
| 金山沢横断点 |  |
 |
金山沢横断点右岸側 |
| 金山沢横断点左岸側 |  |
 |
1290M肩小屋跡 |
| 1290M肩小屋跡 |  |
 |
1290M肩先林道跡 |
| 1290M肩先小尾根 |  |
 |
1290M肩先小尾根横窪地 |
| 1290M肩先林道下斜面 |  |
 |
1290M肩先林道下下降路 |
| 林道末端から、引き返し崩壊ザレルンゼ |  |
 |
1290M肩先林道末端 |
| 金山沢横断点 |  |
 |
金山沢横断点右岸側ザレ斜面の踏跡 |
| 金山沢横断点右岸側ザレ斜面を俯瞰 |  |
 |
金山沢右岸岩稜乗越への踏跡 |
| 岩稜乗越斜上バンドを振り返る |  |
 |
斜上バンドを下る |
| 斜上バンドを振り返る |  |
 |
曲沢枝沢先崩壊ザレ斜面 |
| 曲沢横断点右岸上流側の、崩壊した小屋跡 |  |
 |
高滝下吊橋が見えてきた |
| 高滝下吊橋を渡る |  |
![]()
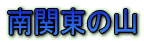 |