仙波尾根から和名倉山・ナシ尾根周回(奥秩父)
![]()

【注意!】ナシ尾根・仙波尾根は、迷い易い箇所・藪が多く、川又道・仁田小屋道ほど踏まれていません。
ごく一部の踏跡を除けば、鹿道拾いと藪漕ぎに終始します。
| date | 2012/4/28-29 快晴のち晴、快晴のち曇 |
| コース | 鮫沢橋ゲート〜松葉沢下降点〜仙波尾根取付〜東仙波〜和名倉山〜市ノ沢ノ頭〜尻無ノ頭〜大洞ダム〜鮫沢橋ゲート |
| 実働 | 第一日:10h10m、第二日:6h35m、計:16h45m。 |
| 概要 | 鮫沢橋基点、1975M平坦地で幕営、藪尾根周回。 |
| メンバー | すうじい(単独) |
| 行程 | →:山道・踏跡、→:徒渉・溯行、##:笹藪帯、→:藪漕ぎ・不明瞭な踏跡、=:車 【4月28日】 快晴のち晴 自宅3:10=6:10鮫沢橋7:10→大洞橋8:10→仁田小屋沢8:35→松葉沢下降点8:50→9:10堰堤下徒渉点9:20→9:30惣小屋谷出合仙波尾根取付10:00→→→1100M岩峰11:20→11:40鹿の楽園12:00→12:15 1219西コル12:20→13:05出逢いの広場13:15→##14:15白樺広場14:25##14:45鹿の十字路14:50##→15:35桜岩15:55→→17:30東仙波17:35→18:20 ・1965 18:30→1930M平坦地(八百平)18:50→→19:30 1975M平坦地(幕営) 【4月29日】 快晴のち曇 1975M平坦地5:20→5:45 1905M千代蔵沢出合(水場)5:55→6:18 1975M平坦地(撤収・朝食)7:40→8:10和名倉山8:20→8:50市ノ沢ノ頭8:55→1810M索道中継点跡9:20→9:35 ・1758 9:55→1750M笹藪上10:00##10:55 ・1550二重山稜11:05##11:45尻無ノ頭12:00##12:45 1350M笹藪下13:00→13:38 1070M炭焼窯跡13:53→→15:15大洞ダム15:25→15:55鮫沢橋16:40=17:35小鹿野18:15=20:50自宅 |
| 使用装備 | 登山靴、ヘルメット、ゴアライト、ガスコンロ、コッヘル、シュラフ、シュラフカバー、GPS、μ-725SW、水2L、飲料1L、ヘッドライト |
| 不用装備 | |
| 記録 | 和名倉山の主要な尾根のうち、未踏であった仙波尾根とナシ尾根(尻無尾根)を周回してみた。全般的には、ほぼ予想した通りの状態であった。しかし、大洞井戸沢偵察'03-06で通行した仙波尾根・1124岩峰北面トラバースは、桟道が落ち廃道化しているようであり、今回は安全を期して稜線を忠実に辿った。 【4月28日】 快晴のち晴 関越道を花園ICで降り、二瀬ダムから大洞林道を進むと、鮫沢橋でゲートが閉鎖されていた。数台の車が停めてある。この林道、鮫沢橋から先が荒れがちなので、ここでの閉鎖は良くあることである。準備をして歩き出す。 落石や土砂の間をすり抜けると、やがて大洞ダム下降点のモノレールが現れる。帰りは、この場所に出る予定なのだ。さらに大洞林道を歩いていると、ヘルメットを下げた単独男性に追い付く。聞けば、荒沢谷を溯行するそうだ。荒沢橋まで、同行する(この男性とは翌日鮫沢橋で再会した)。この間、林道は意外に荒れておらず、この分では、今シーズンの荒沢橋までの開通は早そうだ。 男性と別れると、すぐに大洞橋手前ゲートとなる。鮫沢橋から、丁度1時間であった。大洞橋を渡ると林道は荒れまくりとなり、四駆でも通行困難であろう。日向の道は陽射しが暑く、重荷と相俟って、大汗をかかされる。見晴らしの良い場所からは、仙波尾根とカバヤノ頭らしきピークが望まれる。 右手の斜面に、見覚えのある「ふれあいの森林」という看板が現れると、仁田小屋道取付が近いことを知る。仁田小屋沢左岸斜面に、戻るように取り付く踏跡が、仁田小屋道取付だ。さらに15分の林道歩きで、松葉沢への道形が左へ分岐する。 この道形を辿ると、すぐに細い踏跡となるが、やがて小尾根沿いに下り、堰堤下で松葉沢右岸へと渡る。そのまま踏跡を下降すると、大洞の堰堤下に出る。早速登山靴を脱いで、徒渉用の運動靴に履き替える。大洞の水量はやや多目で、林道歩きで拾った杖が、大いに役立つ。右岸に渡り、堰堤を左から越える。 すぐに惣小屋谷出合であり、今度は井戸沢を徒渉する。水は冷たく、足が冷え切る。濡れた運動靴を脱ぎ、登山靴に履き替えよう。休憩の後、仙波尾根取付を偵察する。この辺り、大洞井戸沢偵察'03-06時とは、様子がすっかり変わっており、少々困惑する。 出合から惣小屋谷右岸沿いに、ゴーロを数十メートル進むと、斜上する踏跡がある。その先も続いているようなので、荷物を取りに戻る。ここが、仙波尾根道取付である。薄い踏跡を辿り、落葉樹林帯・針葉樹林帯を登って行く。 傾斜が急になり、岩壁が近付くと、右手へトラバース気味に踏跡が付けられているのだが、道形や桟道が崩落しているらしく、「通行危険」を報せるテープが現れる。やむなく、一段登って・1124北壁と思しき岩根に接近する。ルートは、岩根沿いを右手へ倒木と土砂を踏み越えて斜上するか、岩根沿いに左上方の尾根を目指すか、の二者択一となる。 稜線に忠実の方が安全性が高いと考え、左上方の尾根を目指し、左手の岩根沿いの斜面を登る。こちらは、特に危険は無い。尾根に乗ると、少々藪っぽい岩稜となるが、慎重に進めば問題は無い。・1124と思しき岩峰を過ぎ、慎重に1095Mコルへと下降する。 ここへ、トラバースしてきた踏跡が合流する。踏跡の桟道は、朽ちているようだ。1100M岩峰への登りには、ロープが付いている。1100M岩峰から、右手へと斜めに下降すると、幅広の窪状へと入って行く。見覚えのある地形は、「鹿の楽園」だ。時刻は既に正午近く、気温は予報通り上昇し、芽吹いていない落葉樹林帯は、陽射しが暑くて堪らない。太い幹の木陰で、荷を下ろす。兎に角、水分補給だ。 休憩後、浅い窪状に沿って、1219西コルを目指す。コルからは、やや不安定な幅広尾根斜面を登る。傾斜の緩んだ肩状が、1360M「出逢いの広場」である。小休後、再び尾根状に取り付き、次第に右手の浅窪状へと入って登って行くと、横に広い1520M笹藪下平坦地形となる。 この先は、尾根がハッキリせず、笹藪の斜面となっている。ここで、完全に踏跡を見失ってしまい、中央の薄い鹿道を頼りに登り始めるが、すぐに笹藪バリケードに阻まれる。やむなく、適当に方向を定めて、藪の薄い箇所を強行突破して行く。 次第に左手へと向きを変え、それらしき鹿道を辿ると、地面の出た広場に至る。南側は禿げた斜面となり、展望も良い。どうやら、ここが1580M白樺広場のようだ。この先は、本格的な笹藪トンネルとなるので、しっかりと休憩しておこう。 さて、覚悟を決め、笹藪トンネルへと突入する。少し身を屈めて、ザックに引っ掛かる笹を少しずつ避けながら、前進する。この作業は、大いに疲れる。ひたすら我慢の連続だ。途中、何箇所か鹿道の交叉点がある。まさしく、迷路である。なるべく踏まれた道を、方向と傾斜とを頭に入れつつ、進んで行く。笹藪トンネルの鹿道なりに、進む以外にない。白樺広場から20分ほどで、「鹿の十字路」の看板のある交叉点に出る。どうやら、正解ルートにいるようだ。取り敢えず、ザックを下ろしてへたり込む。 「鹿の十字路」から少し進むと、顕著な1680M切り開きに出る。ここで左手へ直角に折れて、笹藪トンネルは続く。やがて尾根が次第にハッキリしてきて、笹藪の丈も低くなって来る。「鹿の十字路」から45分で、展望の良い岩に至る。「桜岩」という看板がある。水分と食べ物を補給しよう。 桜岩からは、藪は大したことはないが、笹藪漕ぎで消耗した身体には、辛い登りが続く。幾筋もの鹿道が、判断を迷わせる。どれが正解と言う訳でもなく、少しでも楽そうな所を進む。黒木の繁るカバヤノ頭の最後の登りは避け、左手に見えた岩壁の下をトラバースする。 そのまま水平にトラバースして、西側の肩に乗る。東仙波は、目前である。休むことなくのろのろと進み、東仙波への最後の登りにかかる。午後5時半、東仙波の縦走路に出る。最後の展望を楽しみ、水分を補給する。日没まで、さほど余裕は無い。本日の幕営予定は、二瀬分岐直下の1975M平坦地である。 踏まれて凍結した残雪を避けながら、北へと縦走を開始する。気持ちは逸るが、脚は捗らない。午後6時半、・1965西で小休し、ヘッドライトを装着する。目を皿にして、踏まれた所を探し、踏跡を辿る。1930M平坦地(八百平)まで来ると、幕営している二人を見付ける。二瀬道を登って来たらしい。サイトとしては、魅力的だったが、水場のことを考えて、先へ進む。 やがて、いつの間にか川又分岐を過ぎ、暗闇の中、踏跡を外しながらも、1975M平坦地へと至る。すぐに設営する。水はまだ1L以上あったので、水汲みは翌朝とした。カップ麺とパンの夕食を摂り、お茶を飲む。どうやら、鹿のヌタ場横だったようで、夜通し訪問者が絶えず、度々起こされた。 【4月29日】 快晴のち曇 朝、明るくなってから、水汲みに出掛ける。惣小屋谷の1850M右岸枝沢源頭を下降するが、おそらく本流近くまで降りないと、水が出ないようだった。途中で方針を変え、左手へとトラバースし、1905M千代蔵沢出合を目指す。千代蔵沢出合で水を汲み、ほぼ水平に戻る。平坦地付近まで登り返すと、水平方向にマーキングがあり、たぶん東へ水平に千代蔵沢を目指すのが、正解水汲みルートのようだ。 テントを撤収してから、カップ麺の朝食を食べ、たっぷりお茶を飲む。食事中も鹿ちゃんたちが、見物に来る。さて、今日も行程は長いぞ。二瀬分岐を過ぎ、千代蔵ノ休場で富士山を遠望する。今日も良く晴れている。和名倉山山頂には、仁田小屋道を示す道標まである。 さて、ここから再び藪漕ぎだ。尤も、倒木に踏まれた跡が付いており、あまり迷う要素は無い。9年前に仁田小屋道を往復した際の記憶を辿りながら、黒木の密林帯を抜け、明るい疎林の尾根沿いを市ノ沢ノ頭へと向かう。 ナシ尾根分岐となっている市ノ沢ノ頭で小休止し、少しだけ気合いを入れる。ここからのナシ尾根は、左手が黒木の林、右手が落葉樹の疎林となっている。歩き易い所を、適当に下る。1810M付近まで下ると、索道中継点であろうか、ケーブルや滑車が残る広場に出る。 更に下って行くと、次第に籔っぽくなってきて、・1758北面を巻く踏跡の広場状で小休止する。陽射しが強く、既に結構暑くなっている。再び踏跡を歩き出すと、1750Mの開けた鞍部状になり、周囲に笹籔が目立つようになる。ここから本格的な笹籔廊下が始まる。 なるべく尾根に忠実な、良く踏まれた踏跡を選んで進む。次第に丈が高くなる笹籔の廊下は、時折馬酔木を交え、結構手こずる。尾根左手は傾斜が急ではあるが、樹林帯で笹は薄いので、状況に応じ適宜利用する。1720-1700M付近の緩傾斜地形は、鹿道が錯綜するので、方向感覚が重要だ。 次第に尾根がハッキリすると、やがて顕著な二重山稜地形となって、・1550の木陰で休憩する。この先、尾根上の笹籔にめげて、北斜面の鹿道を辿ると、尾根北側に疎林平坦地形が現れ、しばらく北斜面を辿る。適当な場所で尾根に復帰するが、籔の急斜面登り返しがキツイ。 籔の中の踏跡を辿り、あまり展望の得られない、尻無ノ頭三角点に至る。休憩の後、再び笹籔トンネルを下る。一旦開けた斜面に出るが、その後は幾通りもの笹籔トンネルが、合流分散を繰り返しながら尾根を下っている。正解トンネルを選択するのは難しく、ついつい尾根の左側に寄り過ぎて、尾根に復帰するのに激藪漕ぎで苦労したりする。 1330M付近で開けた荒地に出て、笹籔漕ぎは終了だ。直下の杉林の中で、休憩する。傾斜が緩み、尾根が明瞭になると、馬酔木と落葉樹の疎林となり、歩き易い。1200M付近から尾根が不明瞭となり、傾斜も急になる。GPSで現在位置を確認し、微妙に方向を修正しながら、下って行く。 1070M付近で、炭焼釜跡に出くわす。この辺り、尾根がハッキリせず、踏跡も不明瞭だ。900M付近からは、次第に南へと方向を変え、正解尾根を外さぬよう慎重に下降する。810M付近で、不安定な急傾斜の杉林に入ってしまい、眼下に市ノ沢の流れを見る。 ちと下り過ぎたとは思ったが、急斜面の下をトラバースする薄い踏跡を辿ることにする。何箇所かの急なザレルンゼを慎重に横断し、トラバースを続けて、小尾根の仕事道に合流する。あとは、ジグザグに急降下すれば、大洞ダム湖畔に出る。 ダムの上で、ザックを下ろして休憩だ。もう危険箇所は無い。ぬるくなった水を飲み、最後の登り返しに備える。ゆっくりとした歩みで、大洞林道の高みを目指し、登り始める。やがて昨朝歩いた林道に出て、鮫沢橋まで最後の頑張りだ。 車に着いて、荷物整理をしていたら、昨日の単独男性が戻って来た。聞けば、荒沢谷から雲取山まで登って来たそうだ。帰り道は、秩父の芝桜渋滞を避け、両神・吉田経由でR254に入り、鶴ヶ島ICで関越道に乗った。 |
![]()
GPS軌跡

アルバム
 |
大洞ダム下降点 |
| 大洞橋ゲート |  |
 |
仙波尾根・カバヤノ頭 |
| ふれあいの森林 |  |
 |
松葉沢下降点 |
| 松葉沢徒渉 |  |
 |
大洞本流堰堤下 |
| 大洞本流徒渉点 |  |
 |
大洞井戸沢・惣小屋谷出合 |
| 仙波尾根取付 |  |
 |
斜面を斜上する |
| ・1124岩峰北壁下右 |  |
 |
・1124岩峰北壁下左 |
| ・1124岩峰付近 |  |
 |
・1124岩峰付近 |
| ・1124岩峰付近北側 |  |
 |
1095Mコル |
| 1095Mコル |  |
 |
1100M岩峰付近 |
| 鹿の楽園 |  |
 |
1580M白樺広場 |
| 1580M白樺広場 |  |
 |
南東側平坦地 |
| 再び笹藪へ |  |
 |
1665M鹿の十字路 |
| 1680M切り開き |  |
 |
1740Mからカバヤノ頭 |
| 桜岩からカバヤノ頭 |  |
 |
桜岩から雲取山 |
| 1820M付近から雲取山・三ツ山 |  |
 |
1830M付近の登りにて |
| 1840M付近から芋ノ木ドッケ・雲取山 |  |
 |
カバヤノ頭193M0西肩より東仙波 |
| 西肩よりカバヤノ頭 |  |
 |
鞍部より東仙波 |
| 鞍部よりカバヤノ頭 |  |
 |
東仙波よりリンノ峰 |
| 東仙波より将監峠 |  |
 |
東仙波よりカバヤノ頭 |
| 【4月29日】 朝の訪問者 |
 |
 |
朝の訪問者 |
| 二瀬分岐 |  |
 |
千代蔵ノ休場 |
| 千代蔵ノ休場から富士遠望 |  |
 |
和名倉山頂入口 |
| 和名倉山頂 |  |
 |
市ノ沢ノ頭のナシ尾根分岐 |
| ナシ尾根1870M付近 |  |
 |
1860M付近 |
| 1810M索道中継点跡 |  |
 |
1810M索道中継点跡 |
| 1750M笹藪上から市ノ沢ノ頭 |  |
 |
1750M笹藪上 |
| 1550二重山稜 |  |
 |
尻無ノ頭北西平坦地 |
| 尻無ノ頭三角点 |  |
 |
尻無ノ頭 |
| 尻無ノ頭南面 |  |
 |
1350M笹藪下 |
| 1320M付近 |  |
 |
1320M付近 |
| 1070M炭焼窯跡 |  |
 |
横断したザレルンゼ |
| 大洞ダム湖 |  |
 |
大洞ダム下流 |
| 大洞ダム |  |
MR474_ 大洞惣小屋沢焼小屋沢・和名倉山・惣小屋沢下降'03-06
![]()
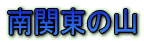 |