梓川二ノ俣谷〜中山コル〜一ノ俣谷滝見(北ア)
![]()

| date | 2008/7/18〜20、23 雨のち曇、晴、晴時々曇、快晴、晴のち曇、晴 |
| コース | 上高地〜二ノ俣橋〜二ノ俣谷峠沢溯行〜中山コル〜一ノ俣谷山田滝〜一ノ俣谷溯行〜常念乗越〜常念岳〜蝶ヶ岳〜横尾〜涸沢カール(定着)〜横尾〜上高地 |
| 実働 | 第一日:8h35m、第二日:9h15m、第三日:9h05m、下山日:4h、計:30h55m。 |
| 概要 | 二ノ俣谷から中山コル越えで一ノ俣谷、滝見後常念小屋へ。 |
| メンバー | すうじい(単独) |
| 行程 | →:山道、→:溯行、→:藪漕ぎ・踏跡不明瞭、=:交通機関。 【7月17日】 新宿23:00=(さわやか信州号)= 【7月18日】 雨のち曇 =5:30上高地6:15→7:00明神館7:20→8:05徳沢8:15→9:10横尾9:35→10:30一ノ俣橋10:35→10:45二ノ俣橋11:00→11:20渓流足袋11:30→12:33 1800M右岸枝沢12:43→1830M右岸枝沢12:54→13:20小休13:30→1860M右岸枝沢13:35→13:45峠沢出合下広河原14:10→14:45 1970M左岸枝沢14:50→15:05 2000M広河原15:20→→17:20中山コル(幕営) 【7月19日】 晴 中山コル6:25→6:55一ノ俣谷7:00→7:20転倒デポ地点7:45→9:03常念滝9:48→10:35山田滝11:10→常念滝12:20→13:25ザックデポ14:10→15:30 2190M二俣15:40→→16:00右岸崩壊地16:15→→常念小屋水源ドラム缶16:55→→17:25旧水源小屋17:30→→18:30常念小屋(泊) 【7月20日】 晴時々曇 常念小屋4:55→5:55休6:05→6:35常念岳6:55→7:42休7:57→8:14 2512P 8:19→9:00 2592P 9:40→10:00休10:05→10:35休10:55→11:10蝶槍11:35→11:45 2625分岐11:50→12:20休12:30→12:50休13:00→13.:25槍見台13:40→14:00横尾14:20→14:50休14:55→15:25休15:30→本谷橋15:36→16:00休16:10→16:40休16:45→17:20雪渓上17:25→17:50涸沢ヒュッテ(定着) 【7月21日】 快晴 (涸沢定着) 【7月22日】 晴のち曇 (涸沢定着) 【7月23日】 晴 涸沢ヒュッテ9:20→10:10本谷橋10:15→11:00横尾11:05→11:45新村橋11:50→12:45明神館12:50→13:40上高地14:00=18:15新宿 |
| 使用装備 | 革登山靴、渓流足袋、ヘルメット、ピッケル、幕営用具、ガスコンロ、コッヘル、防虫ネット、携帯虫避け、E-1、ED12-60mmF2.8-4.0、三脚、μ-725SW |
| 不用装備 | 細引 |
| 記録 | 数年に一度程度、北アルプス穂高岳の涸沢カールに定着して、ボランティア的なことをやっている。その入山時に、寄り道をするのが楽しみだ。今回は、かねてより気になっていた、梓川一ノ俣谷左岸に懸かる常念滝・山田滝を見物しようと企てた。 【7月18日】 雨のち曇 新宿から夜行バス「さわやか信州号」に乗り、殆ど眠れぬまま、5時半に上高地へ到着した。予想していたとは言え、ハナからの雨である。重荷を担いで、黙々と二ノ俣谷出合を目指す。明神、徳沢、横尾と、45分、45分、55分と順調なペースで歩く。 横尾近くまで来ると、すぐ近くに猿が現れ、カメラを向けるとこちらを威嚇する。知らんぷりをしていると、笹の新芽を食べているようだった。増築工事中の横尾山荘でウドンでも食べようかと思ったが、食事はラーメンのみで、10時からだと言う。待てないので、イオン飲料のみ購入し、先へ進む。 横尾から1時間強で、二ノ俣谷出合にある二ノ俣橋を渡る。二ノ俣橋を渡った所から、二ノ俣谷右岸の藪を漕ぐ。いきなり倒木に邪魔される。20分ほど右岸沿いに進み、徒渉のためにフェルト足袋に履き替える。 結構な水量があるので、慎重に徒渉する。革登山靴を首から下げ、ゴーロ歩きを続け、時折、徒渉やヘツりを強いられる。途中、雨が降ったり、日が射したりして、2時間ほどで、大量のガレゴーロの押し出す、1830Mの顕著な右岸枝沢出合となる。更に30分ほどで、1860Mの顕著な右岸枝沢出合だ。 1860m右岸枝沢出合から、10分ほどで、峠沢出合下の広河原に至る。この地形は特徴的なので、峠沢を見落とすことはないだろう。この辺り、幕営適地となっている。実際の峠沢出合は、もう少し上流である。 左岸広河原で休憩後、フェルト足袋から登山靴に履き替えて、少し進むと、1885M左岸峠沢出合となる。このゴーロ沢を詰めれば、2269中山コルに出るはずだ。次第に傾斜が出てくるが、やや濡れたゴーロ沢という印象だ。革靴だと滑り易いので、慎重に登る。 30分強登ると、1970M左岸枝沢が、顕著なガレゴーロ沢として出合う。さらに15分ほど登ると、2000M付近の傾斜のある広河原状となり、本流はゴーロ状のまま、ゆっくりと左へ曲がる。右手の林の中に、中山コルへ突き上げる沢を見出す。 中山コルへ向かう沢沿いに、獣道を拾って登る。やがて水は涸れるが、明確な踏跡は見られず、幾筋かの獣道状が続く。次第に傾斜が増し、藪っぽくなってくる。時折、色褪せた目印布が付けられているが、あまりあてには出来ない。樹林帯のズルズル急斜面となり、寝不足と重荷に、なかなか高度が稼げない。 2000M広河原から苦闘2時間、やっとのことで、予想外に痩せた、2269中山コルに出た。午後5時を過ぎていることもあり、傾いたテント1張分のスペースで、ビバークを決定する。水は700mlほどしか担いでいなかったが、なんとか一晩凌ぐことが出来た。シュラフカバー2枚では、夜中にかなり寒かった。 【7月19日】 晴 テントを撤収して、コル付近の踏跡を調査するが、あまり明瞭なものは無かった。立木に巻かれた、色褪せたテープや布切れが多い場所が、どうやら皆さんの利用するルートのようであった。赤ビニテを追加し、一ノ俣谷へと下降開始する。なるべく踏まれた所を、窪状に沿って下って行くと、次第に濡れたカレ窪となってくる。特に問題なく、30分で一ノ俣谷へと降り立つことが出来た。 振り返れば、コル沢出合は極めて藪っぽく、ハッキリした目印になるものは、何も無さそうだ。真西に向かって、コル沢を登れば良いわけだが、地図読み能力が問われる所であろう。帰りのことを考えて、赤ビニテを付けておこう。 この辺りの一ノ俣谷は、全く平凡なゴーロ沢となっている。しばらく、登山靴のまま、右岸沿いに一ノ俣を下って行く。少し下ったところで、足が滑ってもつれ、顔から倒木に倒れた。見え方がピンボケになったので、メガネの外れたのが判ったが、どこにもメガネは落ちていない。フレームが、頬に刺さっていたのだ。引き抜いて、15分ほど圧迫止血する。 目印用の赤ビニテを利用して、フレームとレンズとレンズ固定テグス糸をガッチリ固定した。壊れかけのメガネでは、予定コースの中山コルの藪漕ぎと二ノ俣谷のヘツり下りには、耐えられそうもない。常念乗越へのエスケープは、遠回りではあるが、やむを得ないであろう。その場にザックをデポし、フェルト足袋に履き替えて、常念滝と山田滝を見物することにしよう。 ザックデポ地点から20分ほど下ると、2095M左岸枝沢出合となる。この辺りから、右岸には踏跡状を見るが、藪っぽいので、辿ってもさほどメリットは無い。なるべく沢沿いに進んだ方が、速い。2040M右岸枝沢出合付近で、スノーブリッジが出現する。右岸側を巻き気味に通過する。この辺り、沢沿いの通過が困難な場合は、右岸に旧登山道跡を辿ることが出来る。 やがて、左岸に懸かる常念滝が見えて来て、嬉しくなる。常念滝は、下段10mほどの美しい滝だ。右岸の大岩脇から巻道が始まる。大岩の上に三脚を立て、常念滝を撮影する。ここから見ると、下段10mの上に、上段4mが続いているのが判る。 さらに旧登山道跡の巻道を辿るが、途中、振り返ると、常念滝が望まれる。常念滝から45分ほどで、山田滝8mに至る。山田滝の下には、出合の前衛3m滝が懸かる。今回は、この下流にある一ノ俣ノ滝見物は断念して、ここで引き返すことにする。 山田滝から30分ほど溯行すると、4m2条トヨナメ滝となる。ここは、右岸側を小さく巻く。下降時は、右岸側の旧登山道を辿ることが多かったが、沢通しまたは小さく巻く方が速い。さらに30分ほど溯行すると、3m階段状滝の上流に常念滝が見えてくる。この階段状滝も、右岸側をヘツり気味に越える。 常念滝出合下流は、左岸がフェース状大岩壁となっている。一ノ俣谷本流は、トヨ状階段滝を懸ける。下降時は、右岸側の巻道を辿ったのだが、溯行では、左から越え、ガリー状を登って右岸大岩の下へと入り込む。右岸大岩の下から、常念滝の瀑風と飛沫を避けつつ、手持ちで撮影を試みる。その後、大岩沿いに常念滝の前を通過する。 常念滝を後にして、沢沿いに溯行する。2040M右岸枝沢出合付近のスノーブリッジは、右岸をトラバース気味に通過する。常念滝から1時間ほどで、ザックデポ地点に戻る。再び重荷を担ぎ、首から登山靴をぶら下げて、平凡な一ノ俣谷を、ヨタヨタ溯行を続けるが、なかなか捗らない。 ザックデポ地点から、1時間20分で、常念乗越沢分岐である2185M二俣に至る。乗越沢へ入ると、間もなく、右岸側に旧登山道跡が現れる。しばらくこれを辿る。2235M右岸大ガレで、旧登山道跡は、左岸に渡る。この踏跡に突入するが、とんでもない藪漕ぎを強いられ、途中で断念して沢に戻る。右岸大ガレから、2290M右岸水源の沢までは、旧登山道跡は利用不能と思った方が良い。 2290M右岸枝沢は、傾斜のあるゴーロ沢状で、常念小屋の水源となっている。青いドラム缶が目印だ。この辺りから、右岸側に踏跡が復活し、曲りなりにも利用出来るようになる。 この後は、旧登山道跡もしくは小屋の水源黒ホース沿いに登高してゆく。水源の沢から常念小屋まで、約150Mの高度差は、風も無く虫の多い樹林帯で、本当にシンドかった。休憩時は、防虫ネットが重宝する。旧登山道は、最後にハイマツ藪に突入するため、直前に常念小屋の信州大診療所裏へとエスケープした。 この日は、常念小屋へ泊まる。連休とあって、やや混雑していたが、布団一枚に一人寝ることが出来た。夕食後、頬の傷が化膿しないか心配だったので、診療所ドクターに相談し、念のため抗生剤を頂いた。感謝。 【7月20日】 晴時々曇 常念小屋でたっぷり睡眠を取り、5時少し前に歩き始める。荷の重さに負け、2750M肩状で小休を入れる。小屋から実働1時間半で、山頂の祠前に至る。山頂の南東側は、烏川本沢の常念沢源頭であり、急な谷に雪渓が残っている。 常念岳から、大下りが始まる。2620-30M付近で、西へ下るガレに誘われ、ミスコースしてしまうが、すぐに岩々帯をトラバースして、事無きを得る。2512P手前の2460Mコルに近い辺りで、ウラジロヨウラクの小群落を見る。 2460Mコルから登り返して、2512Pに至る。当然のように、小休を入れる。ザックが肩に食い込んで、痛い。西側には、虹が出ていた。ここからは、次のピークである2592Pとその奥の蝶ヶ岳〜大滝山の連なりが望まれる。まだまだ、先は長そうだ。 2512Pを過ぎると、2490MPの西側をトラバースして、2592Pへの登りにかかる。樹林帯の登りに汗をかき、2580M肩付近の風通しの良い場所で、休憩する。さて、再び歩き始めると、もうすぐ2592Pだとは思っていたが、一、二分でお花畑の山頂に出てしまった。 北東側のお花畑には、ハクサンチドリが多い。南斜面は、とにかく、ニッコウキスゲの多いお花畑である。ザックを下ろして、カメラを出そう。咲き始めのニッコウキスゲ群落の向こうに、蝶槍が見える。南斜面を下って行く途中には、ハクサンフウロが多かった。 2592P南面のお花畑を下って行くと、やがて蝶槍との間の平坦地形へと入る。右手に池を見て、最低鞍部である2462独標となる。再び登りとなり、樹林帯を抜けて、見晴らしが良くなる。2600M付近まで登ったところで、チシマギキョウの群落に出くわす。撮影の口実で、ザックを下ろす。 蝶槍は、なかなか展望の良い場所なのだが、この日は残念ながら、槍・穂高の稜線が雲に隠れていた。他の登山者達も、残念がっていた。蝶ヶ岳の三角点ピークから、小屋裏のピークまで、なだらかな尾根が続く。 蝶ヶ岳三角点を過ぎて、2625の分岐で小休。いよいよ、横尾への大下りである。このコースは、下り1回、登り2回の経験があるが、樹林帯の急勾配が延々続くので、登りも下りも辛いところである。途中、1回の小休を入れ、実働50分で、展望を得られる場所に出る。このコースで展望が得られるのは、この展望台と、槍見台ぐらいである。 さらに25分下って、槍見台に至るが、雲に隠れて、槍の姿は見ることが出来ない。さらに20分で、横尾に着いた。 横尾から実働1時間強で、本谷橋に至る。結構、水量は多いようだ。屏風の頭から続く尾根を回り込む辺りで、横尾右俣が目に入る。カール尻から下に、雪渓が多く残るのが判る。同じ場所から涸沢方面を見遣ると、まだまだ先は長い。 涸沢は、全く伏流しておらず、沢音がずっと聞こえていた。トラバースから、沢に近付けば、雪渓がベッタリ残っている。今年は、ヒュッテまで、二ヶ所の雪渓が続いていた。こうして、涸沢定着が、始まったのだった。 【7月21日】 快晴 (涸沢定着) 【7月22日】 晴のち曇 (涸沢定着) 【7月23日】 晴 早くも下山日となってしまった。下界は猛暑の日々という情報に、ちと憂鬱になってしまう。 バスの時間があるので、横尾経由のノーマルルートを辿る。新村橋から梓川右岸林道を歩き、明神で左岸へと戻る。明神から下は、観光客だらけだった。 結構荷物が重かったので、時間が掛かるかと思ったが、意外と早く下れて、実働4時間で上高地に着いた。16時のバスを、14時に変更して貰い、新宿に18:15には到着できたのだった。 |
![]()
遡行概念図
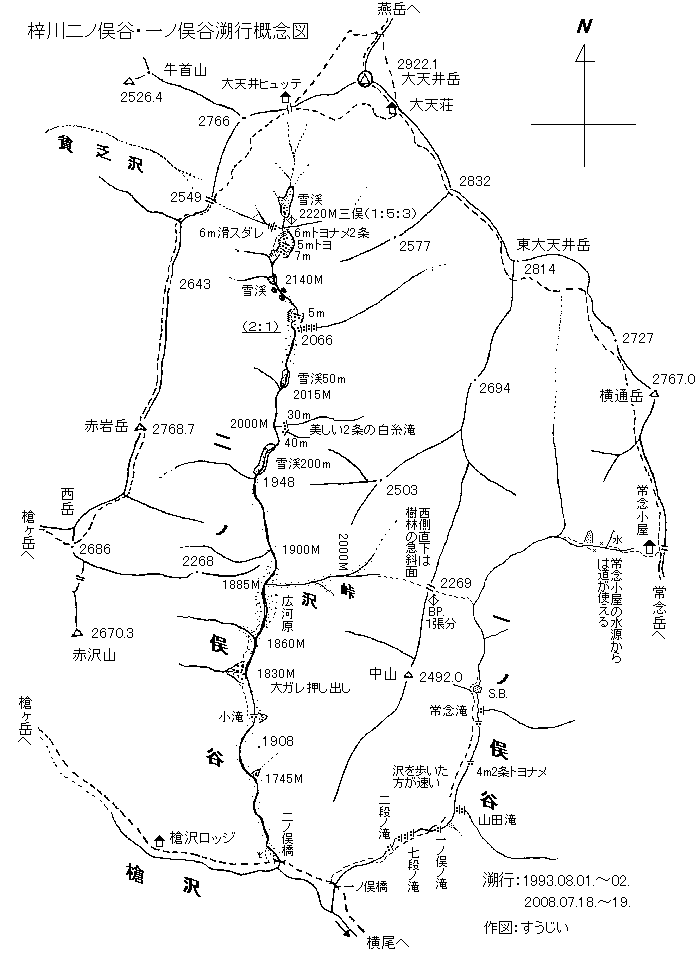
アルバム
 |
7月18日、横尾の猿 |
| 横尾の猿 |  |
 |
二ノ俣谷峠沢(中山乗越沢)出合下広河原 |
| 二ノ俣谷峠沢出合下広河原上流側 |  |
 |
二ノ俣谷峠沢出合下広河原下流側 |
| 二ノ俣谷峠沢出合のゴーロ |  |
 |
峠沢を登る |
| 峠沢1970M左岸枝沢 |  |
 |
峠沢2000M付近広河原 |
| 7月19日、・2269中山コル(乗越)幕営地の朝 |  |
 |
中山コル(乗越)付近樹林 |
| 藪っぽいコル沢(一ノ俣谷中山乗越沢) |  |
 |
一ノ俣谷コル沢(中山乗越沢)出合上流側 |
| 一ノ俣谷2095M左岸枝沢 |  |
 |
2040M右岸枝沢出合付近で、スノーブリッジ出現 |
| 常念滝が見えた |  |
 |
一ノ俣谷左岸常念滝下段10m |
| 一ノ俣谷左岸常念滝下段10m |  |
 |
一ノ俣谷左岸常念滝2段14m |
| 一ノ俣谷右岸巻道から常念滝 |  |
 |
一ノ俣谷左岸山田滝8m |
| 一ノ俣谷左岸前衛滝3mと山田滝8m 今回は、ここで引返そう |
 |
 |
一ノ俣谷4m2条トヨナメ |
| 一ノ俣谷3m階段滝と左岸常念滝 |  |
 |
常念滝出合下流から |
| 大岩下から常念滝 |  |
 |
再び2040M右岸枝沢出合付近のスノーブリッジ |
| 一ノ俣谷2185M二俣 右の常念乗越沢へ入る |
 |
 |
2290M右岸常念小屋水源の沢 |
| 7月20日、常念岳山頂の祠 |  |
 |
常念岳稜線より、常念沢源頭の雪渓 |
| 2460Mコル付近で、ウラジロヨウラク |  |
 |
ウラジロヨウラク |
| 2460Mコル付近から、2512Pを望む |  |
 |
2512Pから常念岳 |
| 2512Pから見た虹 |  |
 |
・2512Pから、・2592Pと蝶ヶ岳 |
| ・2592Pお花畑と蝶槍 |  |
 |
・2592Pお花畑のニッコウキスゲ |
| ・2592Pお花畑のニッコウキスゲ |  |
 |
・2592Pお花畑のハクサンチドリ |
| ・2592Pお花畑のハクサンフウロ |  |
 |
蝶槍北面2600M付近のチシマギキョウ |
| 蝶槍北面2600M付近のチシマギキョウ |  |
 |
蝶槍から中山コル・大天井岳 |
| 蝶槍から常念岳・大天井岳 |  |
 |
蝶槍から三角点ピーク・小屋裏ピーク |
| 下降尾根展望台付近の針葉樹林 |  |
 |
展望台から赤沢岳 |
| 本谷橋 |  |
 |
屏風北西尾根を回り込む辺りから、横尾谷右俣カール方面 |
| 屏風北西尾根を回り込む辺りから、涸沢カール方面 |  |
![]()
 へ へ |