中津川石舟沢右俣右沢・両神山(両神)
![]()
![]()
| date | 2002/5/12 晴 |
| コース | 長栄橋〜石舟沢右岸杣道〜石舟〜石舟沢右俣右沢〜ヒゴノタオ〜両神山(剣ヶ峰)〜ヒゴノタオ〜三芳岩〜大峠〜石舟下〜石舟沢右岸杣道〜長栄橋 |
| 実働 | 7h30m |
| 概要 | 長栄橋基点、石舟沢右岸杣道桟道朽ちる、奇観石舟、大峠から石舟への踏跡崩壊、上部危険。 |
| メンバー | すうじい(単独) |
| 行程 | →:山道、→:溯行、\\:藪漕ぎ 長栄橋7:50→トウタロウ沢出合8:10→8:35石舟下9:10→石舟上9:30→1010M二俣10:00 →10:50 1170M二俣11:15→11:55ヒゴノタオ12:15→12:55大笹13:00→13:20剣ヶ峰13:30 →ヒゴノタオ14:00→14:20三芳岩14:25→14:55大峠15:15\\16:10 1140M二俣16:20→ 16:55石舟下→トウタロウ沢出合17:15→17:30長栄橋 |
| 記録 | かねてより気になっていた石舟沢を、偵察を兼ねて訪れてみた。右俣右沢なら、危険無くヒゴノタオに突き上げるであろうとの予想は、ほぼ正解であった。大峠からの下降の踏跡が、まったく当てに出来ず、下り始めに緊張させられた。 長栄橋の位置が判らず、一つ手前のトンネルで旧道を走り、時間を食う。さらに次の旧道では、長栄橋直前で、崖崩れのため引き返す羽目に。グルッと迂回して、やっと長栄橋に辿り着く。ミニバンが一台停めてある。釣師であろうか。 念のため、9mmx40mザイル・シュリンゲ・ヘルメット・アイスハンマー・ツェルトを持って行く。一眼レフとデジカメも担ぐので、結構な重さである。石舟沢右岸杣道を辿るが、始めは小尾根を登り、鉄塔跡らしき場所からトラバースとなる。時折、桟道が朽ちかけていて、なるべく頼りにしないよう心掛ける。 20分ほどで、トウタロウ沢出合となり、少し行くと、杣道は沢に降りている。杣道は再び右岸に上がり、滝場の手前でジグザグを切って、高度を上げる。トラバースになると、朽ちかけた桟道がまた現れる。一つ一つ判断をせねばならない。再び沢に近付くと、石舟下に至る。長栄橋から45分である。 荷物を下ろして、先ずは偵察だ。左岸の大峠から下る「峠沢」出合の、15m空滝は、やはり石灰岩から成るようだ。中間尾根に、巻道が付いている。石舟を見に行けば、灰白色の曲線的な造形の器は、褐色の朽ち葉の水たまりを湛えている。ホールド・スタンスらしきものが、全く見られず、体験したことのない「登攀」になりそうだ。滑り台状のトヨナメには、水流は見られない。 釜は深いぞという情報から、防水パッキングを完璧にして、ステッキを手に石舟に入る。滑り台のような涸れトヨ状を登り、最初の深い釜を、ステッキで探る。手前は深いが、なるべく奥の方に立てば、太ももぐらいで済みそうだ。朽ち葉が沈殿した釜水には、ヤマネと思われる小動物の死骸が浮いている。かわいそうなヤマネちゃん、生きているうちに、逢いたかったよ。 首から下げたデジカメをレジ袋で包み、脚を伸ばして釜に入る。第二の滑り台に取り付こうとした途端、バランスを崩して前につんのめり、反動でお尻も濡らす。デジカメは、レジ袋のお陰で無事だった。気を取り直して、第二の滑り台にズリ上がる。荷が重いので、落口に相当する箇所の通過が大変だ。全身のフリクションを利用して、やっとこさ越える。水垢みたいな汚れが、服に付着する。 第二の釜を探ると、膝上くらいで済みそうだ。ボチャンをせぬよう、慎重に第三の滑り台を登る。S字状トヨを抜けて、出口の涸石滝を越える。上に立って振り返ると、S字状トヨ付近で、右岸からスラブの涸れ枝沢が出合っている。僅かな距離ではあるが、石舟は楽しめる。朽ち葉水と水垢の臭いが、服に染み付くのがイヤだけどね。 右岸にガレを見ると、そのすぐ上流に岩小舎がある。沢が左へ曲がる川原状に、焚火の跡がある。4月に石舟沢を溯行した、NCMの夜空さんたちのものであろうか。3x6mナメを越え、ゴーロを行くと、やがて左俣は巨岩ゴーロ、右俣は2段5m滝の、1010M二俣である。 2段5m滝は、下段のナメの上に立ち、シャワーを避けて、右壁に取り付く。荷が重いので、最初のワンステップがシンドイ。しばらくゴーロを進み、左岸から涸れ沢が出合うと、綺麗な小滝が連続する。3m滝の上で、右岸の立木に、東京営林局の境界見出標のプレートが打ってある。 左岸から涸れ沢が二本ほど出合うと、石滝を越え、ナメを見る。右岸から涸れ沢が出合い、完全に伏流となったゴーロを進むと、サワグルミの大木が、その根に大石を幾つか抱えて、沢の真ん中に立っている。あたりは、明るく開け、この上で二俣になっている。やっと1170M奥ノ二俣だ。 左沢は、しばらくゴーロが続くようだ。右沢は、やたら藪っぽい。今日は偵察だから、右沢からヒゴノタオへ抜ける予定なのだ。荷物を下ろし、大休止しよう。右沢入口付近の立木に、エスケープ目印の赤布を付けておく。 完全に水の涸れた右沢を登り始めると、巨岩の押し出しや倒木などで、やたら難儀する。これを過ぎれば難所もなく、東へ東へと進む。やがて右岸に、1683Pからの沢形を見送り、地形図を見ながら、ヒゴノタオを目指す。コルへの最後の登りは、ちょっと足場が不安定だが、特に問題なく、ヒゴノタオに出る。荷が重いせいか、かなり疲れた。 ヒゴノタオ付近は、好ましい広葉樹の疎林となっており、ピンク色のツツジが咲き誇っている。フェルト足袋を軽登山靴に履き替えて、剣ヶ峰を目指そう。大笹までの、標高差約280mの登りが辛い。剣ヶ峰まで行ってみると、人気の無い梵天尾根と違って、随分賑わっている。咲き残りのアカヤシオや、ムシカリの白い花も見られる。 早々に山頂を辞して、引き返す。さすがに、下りは速い。ヒゴノタオから三芳岩へ登る。三芳岩は、高度感があり、慎重に通過する。大峠までは、さらに30分程かかる。大峠に着いたのは、14:55であった。下りの難路に備え、ザイル・シュリンゲ・アイスハンマーを出しておく。デジカメも、しまっておこう。 mina○師匠の報告を参考にして、ベンチのある大峠から、右手へトラバースする踏跡を辿る。急な小尾根をトラバースするところが、踏跡が崩れかけており、悪い。アイスハンマーで騙して通過し、その先の踏跡が消えているので、次の沢状の手前で下降し始める。しかし、よく見ると、一旦消えたトラバースの踏跡は、その沢状をも横切って、さらに右手の小尾根へ渡っているようだ。強引に沢状を斜めに登って、踏跡に合流する。 踏跡は、この二つ目の小尾根を下っているようだ。薄いので見失いがちだが、しばらく辿ることができる。やがて、不明瞭になるので、末端が崖になっていないことを祈りつつ、この小尾根に沿って下って行く。苦労すること小一時間で、「峠沢」の沢床に降り立つ。1140Mの涸れ二俣地点と思われる。 さて、先を急ごう。少し下ると、僅かに水流が現れ、左岸から水流のある枝沢が出合う。さらに下ると、左岸に広いガレ斜面が現れる。やがて石灰岩の涸れ石滝3mを下ると、出合の空滝15mの上に出る。右岸の岩壁の下をトラバースして、中間尾根の踏跡を辿れば、石舟下に降り立つ。 あとは、石舟沢右岸杣道が明瞭なので、ガンガン飛ばす。怪しい桟道も騙し騙し通過し、一気に長栄橋まで下る。車に戻ったのは、17:30であった。 |
![]()
溯行概念図
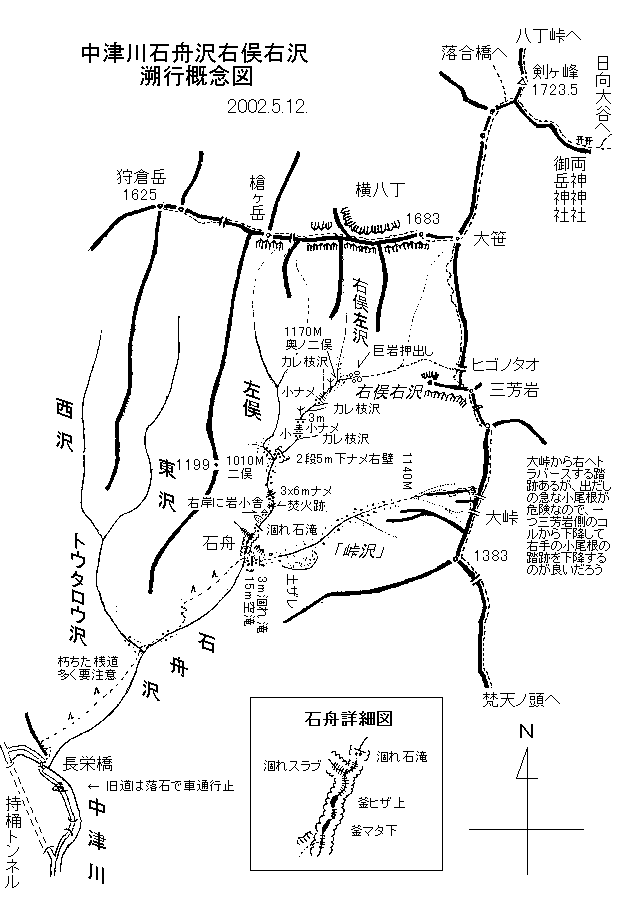
 |
石舟沢左岸峠沢空滝 |
| 峠沢空滝15m |  |
 |
石舟沢の石舟に入る |
| 石舟 |  |
 |
滑り台のような涸れトヨ状を登る |
| 深い釜を探る |  |
 |
石舟 |
| 1010M二俣 |  |
 |
右俣出合の2段5m下ナメは、ナメの上に立ち右壁を登る |
| 1170M奥ノ二俣、右沢はやたら藪っぽい |  |
 |
1170M奥二俣、涸れゴーロ続く左沢 |
| ヒゴノタオに出る |  |
 |
アカヤシオかな |
 |
|
 |
剣ヶ峰直下のアカヤシオ |
| 剣ヶ峰山頂 |  |
 |
剣ヶ峰から金山岳方面 |
| 剣ヶ峰から大笹方面 |  |
 |
白い花は何だろう |
 |
|
 |
三芳岩から、大笹(中央)と・1683P(左) |
| 三芳岩から辺見尾根かな |  |
 |
三芳岩 |
| 三芳岩から、狩倉槍(左)と・1683P(右) |  |
 |
三芳岩から、大笹(中央)と・1683P(左) |
| 三芳岩から、両社のピーク |  |
 |
大峠、下小屋沢側 |
| 大峠 |  |
![]()
| 両神山の山行記録へ | |
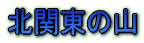 へ へ |
|