加賀禅定道から白山・別山(両白)
![]()
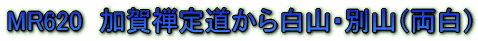
| date | 2009/5/3-5 曇、曇、快晴のち曇 |
| コース | 檜新宮参道〜加賀禅定道〜大汝峰〜御前峰〜室堂〜南竜山荘〜別山〜チブリ尾根〜市ノ瀬 |
| 実働 | 第一日:7h、第二日:9h35m、第三日9h11m、計:25h46m。 |
| 概要 | 百四丈滝を遠望し、残雪の白山別山縦走、チブリ尾根下降。 |
| メンバー | Tds君、すうじい |
| 行程 | →:ツボ足、**:アイゼン、$$:スノーシュー、=:車 【5月3日】 曇 自宅18:05=1:45市ノ瀬4:35=Taxi=5:15県道岩間一里野線入口ゲート5:40→6:05ハライ谷登山口6:25→7:20 1000M 7:45→8:45休9:10→9:55休10:10→10:45檜新宮11:05→11:30シカリ場分岐手前11:50$$→12:50 1630M肩13:25$$13:45→1595Mコル$$1620M→14:35 1653P 14:55→15:40奥長倉山避難小屋(泊) 【5月4日】 曇 奥長倉山避難小屋5:30**6:25休6:35**1968P 7:05**7:35滝展望台8:30$$2138P 9:00$$→9:20 2075Mコル9:30$$10:30 2150M肩10:50$$11:20 2220M 11:30$$2300M長坂取付11:55→13:00四塚山北肩2460M付近13:25$$2490M四塚山・七倉山コル13:47$$14:20七倉山南東面14:30→14:55 2530M付近15:05**15:55大汝峰16:30**17:20御前峰17:30**1745室堂18:15$$18:50南竜山荘(泊) 【5月5日】 快晴のち曇 南竜山荘6:05**6:55 2244.0P 7:10**7:35休7:40**2256P油坂ノ頭8:00**8:10油坂ノ頭南8:20$$8:35 2230M付近8:45**2190M最低コル9:04**9:35 2276P 9:50**10:40 2342P北コル10:45**11:20御舎利山11:37**11:50別山12:00**12:13御舎利山12:25**2160M小尾根乗越→13:10 2020M 13:15→13:30チブリ尾根避難小屋13:40→14:00(迷)14:50→14:55 1760M尾根復帰15:00→15:55 1380M 16:00→16:10最終水場16:15→17:10休17:15→18:00市ノ瀬18:35=18:55白峰温泉(入浴)19:50=Ts君宅3:50=4:45自宅 |
| 使用装備 | 登山靴、アイゼン、ピッケル、スノーシュー、ストック、μ-725SW、、E-1、ED12-60mmF2.8-4SWD、ED50-200mmF2.8-3.5、三脚、宿泊用具一式 |
| 不用装備 | 8mmx30mザイル、テント一式 |
| 記録 | 加賀禅定道の尾添尾根から、丸石谷に懸かる百四丈滝を遠望し、さらに白山へと登り、別山まで縦走する、という計画を立てた。同行者は、妙高〜雨飾縦走(頸城)'08-10・八丁尾根・大キギ・剣ヶ峰・金山岳西尾根下降(両神)'08-12の時のTds君である。 【5月3日】 曇 休日の高速道路1000円を利用し、関越道〜北陸道経由で、金沢西ICから降りる。市ノ瀬駐車場で仮眠し、予約しておいたタクシーで、一里野温泉スキー場へと向かう。県道53号線(岩間一里野線)入口ゲート前に降ろして貰う。 舗装された県道53号線を、歩いて行くと、ミソサザイ・ウグイス・オオルリ・キビタキなどが近くで囀ったり、オオタカが悠々と空を舞ったり、法面にヤマブキやキバナノイカリソウが咲いていたりする。時折、後ろから来る車や、自転車に追い越される。地元の林業者や、新岩間温泉に向かう人々であろうか。入口から25分ほど歩くと、ハライ谷を渡り、ハライ谷登山口に到着する。 ハライ谷登山口から檜新宮参道に取り付くと、いきなり急登が始まる。標高差にして、350Mほど続くことになる。辛い登りだが、道の真ん中にまで生えている、カタクリやスミレなどが、慰めてくれる。カタクリも多かったが、写真を撮り損ねた。1000M付近で傾斜が緩くなり、雪が出てくる。最初の休憩を入れよう。この辺り、カタクリの芽吹きだらけである。 夏は水場があるという、1115の先の小沢を右に見て、1120M付近で右へ少し回り込む。林道状の道形を辿ると、杉林となり、踏跡不明瞭となる。良く捜すと、道は杉林の中を登っていた。杉林を抜ければ、潜り易い雪の岳樺疎林の登りとなる。少し登ったところで、休憩していたら、ショートスキーを担いだ新潟の5人パーティに抜かれた。 ひたすらツボ足で、雪の上を歩く。緩やかな窪状を進み、雪の急斜面を登ると、ハッキリした尾根上に乗る。振り返れば、大笠山と笈ヶ岳が望まれる。尾根の東側の安定した雪庇状を、歩くようになる。登るにつれ、次第に、大笠山と笈ヶ岳が見やすくなってくる。 歩き始めて5時間、やっと檜新宮に到達する。大木に囲まれた、独特の雰囲気の場所である。 しかり場分岐からは、口長倉へ続く藪混じりの長い尾根を辿る。度々雪が切れ、スノーシューを装着したり外したり、なかなか行程が捗らない。遠方に、四塚山が望まれる。口長倉直前コル付近では、スノーシューが使える。Ts君のザックの肩紐が壊れかけているのが見付かり、応急処置をするものの、気分はかなり暗くなる。 口長倉先1610MP付近から、1653Pと奥長倉山越しに美女坂ノ頭が望まれるが、次第に雲が低くなってきて、気分は滅入ってしまう。この先でスノーシューを装着したが、1653Pへの急登で、またまた外す羽目になる。奥長倉山中腹に避難小屋が見えているものの、なかなか近付かない。 15:40、やっと避難小屋に到着する。先客は、途中追い越された、ショートスキーの新潟5人パーティー。避難小屋の周囲には、最近降った新雪があり、水用の雪に事欠かない。我々の後に、犬付き親子連れパーティーも到着して、この日の宿泊者は、3パーティ11人と1匹。 【5月4日】 曇 心配された天気も、曇り空だが、改善傾向にあるようだ。出発は、少し遅れて5時半だった。最初からアイゼンを装着して、奥長倉山へと登る。正面には、本日最初の難関、美女坂が待っている。美女坂ノ頭の台地の左手には、四塚山が見えている。四囲の山々も遠望出来るので、百四丈滝は十分展望可能だろう。少し安心する。それにしても、溶岩台地を浸食した、丸石谷右岸断崖の凄まじさ。 奥長倉山から少し下った1730Mコルから見上げると、美女坂の登りが、ますます大変そうに思われる。潜りやすい雪と、時折ある藪っぽい所と、安定した場所の少ない急斜面とに苦労しながら、美女坂を登って行く。途中、座り心地の良さそうな岳樺の所で、小休を入れる。ここで、ショートスキー5人パーティに追い越される。 急登をこなして、やっと美女坂を越えると、うって変わったなだらかな溶岩台地の尾根となる。スノーシュー装着は、滝展望台までお預けにして、休憩するショートスキー5人パーティを横目に、さらに進むことにする。滝見台への登りの途中で、再びショートスキーパーティに追い越される。 30分ほどのアルバイトで、滝見台に到着する。安全な所でザックをデポし、恐る恐る雪庇へと近付く。そして、やっと百四丈滝の実物を目にする。雪と氷で出来た桶筒の中に、落水が吸い込まれて行く。この時季ならではの光景に、違いない。この滝を見るために、ここまで登って来たのだ。しばし、撮影に没頭する。 滝見台では、ちと時間を使い過ぎた。ここからスノーシューを着け、30分の登りで、2138Pに至る。この先には、天池があるらしいのだが、完全に雪で埋まっている。展望は良好なのだが、それにしても、四塚山はまだまだ遠く高い。天池付近の稜線漫歩後、2120MPからツボ足で2075Mコルへと下り、小休する。 2075Mコルから、スノーシューで2158Pに取り付く。夏道は東面をトラバースしているようだが、雪の斜面を横切るのは危険なので、しばらくは忠実に尾根を登る。かなり登ってから、傾斜が緩んだのを見計らって、トラバースに入る。正面に、四塚山が大きくなる。 所々ブッシュが顔を出した油池を過ぎ、2150M肩付近で、越えて来た2158Pと2138Pを眺めながら休憩を入れる。丸石谷の百四丈滝上流が俯瞰出来る。清浄ヶ原越しに見る大笠山・笈ヶ岳は、大分遠くなった。四塚山へは、まだまだ登りが続く。 2230M肩へは、ちと傾斜がキツイ登りを頑張る。2290M付近は、風のイタズラか、新雪の雪稜が出来ている。慎重にこれを辿る。長坂と呼ばれる辺りであろうか、2300M付近から、ハイマツの間を夏道の階段が付いている。新雪に半分埋まって、少々歩きにくい。スノーシューを外して、夏道通しに登る。 長坂の雪混じりの階段道を登り、疲れ果てて、四塚山北肩2460M付近で大休止を入れる。水分と行動食を摂っておこう。四塚山上部の北東面は、緩やかな斜面で、その左手に七倉山が見える。大休止の後、四塚山上部まで登ると、北東側緩斜面をトラバース出来る。大量の雪が、まるでカール状に溜まっている。ここまで来ると、今まで七倉山に隠れていた大汝山が、その姿を見せる。 2490Mコルを経て、七倉山に取り付く。トラバースは危険なので、尾根沿いに登って行く。七倉山から振り返ると、四塚山の北東面は、真っ白だ。スキー向けの斜面である。あんな所を、トボトボ歩いたかと思うと、(元)山スキー屋としては、ちと悔しい。 七倉山を登り、稜線漫歩になると、大汝峰の中腹肩越しに、別山方面が姿を見せて来る。手前の白い斜面は、釈迦岳へ続く尾根の上部であろう。ブッシュの出た2557の西側に、荷物がデポしてあったが、後で聞いたところ、例のショートスキー5人パーティのものであった。 七倉山最高点の2557は踏まず、南側を巻き気味に南東面へ進む。ここで、やっと大汝峰へのルートが、確認できた。そこから、スノーシューを外し、御手水場の2455Mコルを目指して、急な雪斜面を下る。 2455Mコルから、大汝峰への登りが始まる。2530M付近で、氷化した急斜面にぶち当たり、ハイマツに身を寄せ、アイゼンを装着する。気持ちは少々焦るものの、重荷には勝てず、ゆっくりゆっくり登る。途中、例のショートスキー5人パーティと擦れ違う。彼らは、七倉山で幕営するらしい。アイゼンを装着してから、50分もかかって、やっと大汝峰山頂に至る。山頂付近は、地面が出ており、祠は、周囲を石垣で囲んである。 大汝峰山頂からは、剣ヶ峰と最高峰である御前峰が、やっとその姿を見せてくれた。御前峰の右手には、明日登る予定の、別山方面が見えている。御前峰を越せば、あとは南竜山荘まで下るだけだ。いざとなれば、テントがあるので、途中ビバークも可能だ。精神的に、ぐっと楽になる。既に午後4時だが、疲れ果てていたので、大休止する。ぐっと冷えて来たので、ゴア雨具など着込む。 大汝峰からは、南へ下るのだが、始めは少し夏道が出ており、あとは雪の詰まった窪状を、一気に駆け下る。今回も、剣ヶ峰には登る余裕が無かった。御前峰へのルートは、西側から登るしかないだろうと予想していたが、トレースに従い、2630MPの西側を巻き気味に進み、御宝庫直下の雪斜面に取り付く。 途中から、結構急な雪斜面を、右へとトラバース気味に登る。滑落するとヤバイので、バランスを崩さぬよう、集中する。やがて、御宝庫の岩場を南側から巻くように、雪のない斜面を登って行くと、御前峰の稜線に乗る。 午後5時20分、御前峰山頂着。いつの間にか、別山がシッカリとその姿を見せている。どうやら、明日はあのピークに立てそうだ。眼下に、室堂の建物が見えている。夏道を少し下り、腐った雪の上になると、アイゼンを外す。あとは雪斜面を、快適に駆け下りる。15分で、室堂へと至る。 室堂で、南竜山荘へのコースを確認する。一旦、東南東へと雪原を突っ切り、夏道の尾根に乗る。弥陀ヶ原越しに、日本海へと沈む夕日が望まれる。2370M付近で、尾根の東側へと乗越し、雪の詰まった幅広の谷を下る。重い雪だが、スキーなら、快適だろう。腐った雪なので、恐怖感は無いが、疲れのためか、何度も転ぶ。正面には、夕照の別山が望まれる。目指す南竜山荘が、次第に近付いてくる。 午後6時50分、やっと冬期開放の南竜休憩所に辿り着く。付近には、ヨーデルを歌うパーティもいた。小屋の中では、我々のために場所を空けてくれた。遅い夕食後、眠りに就く。 【5月5日】 快晴のち曇 早出をする予定だったが、6時を過ぎてしまった。空は、晴れ渡っている。2244.0Pへのルートは、南竜山荘から、ほぼ真南へと登り、西尾根に取り付くのだ。振り返れば、南竜山荘の後ろに、昨日下った谷が、白く光っている。昨日は、無事この小屋まで辿り着くことが出来て、本当に助かった。 2244.0P西尾根に乗ると、右手に2256P(油坂ノ頭)の白い峰が、大きく見える。左手には、御前峰と南竜ヶ馬場の地形が、ハッキリと見て取れる。西南西には、大長山・赤兎山などの峰々が望まれる。時折、周囲を眺めながら、2244.0Pへと登って行く。 2244.0Pまで登って、最初の休憩をする。2256P(油坂ノ頭)から御舎利山までの、ヤバそうな稜線が、イヤでも目に入る。広い稜線を2210M南肩まで下ると、これからの稜線が、雪の落ちた壁を見せ付ける。 2180Mコルから2256Pへは、腐りかけた雪斜面を登る。油坂と呼ばれる夏道は、2256P北尾根に付いている。雪のある季節には、油坂取付が雪崩の危険があるため、2244.0Pから尾根伝いに行くのが一般的である。苦しかった登りを終え、2244.0Pを振り返ると、南肩越しに、奥三方山が見えている。 これから先は、雪庇がかなり残っていそうだ。しばらくは、平坦な尾根が続きそうなので、2256Pから少し進んだ所で、スノーシューに履き替える。2230M付近まで進むと、急降下が待っているので、スノーシューからアイゼンに履き替える。 2210M付近から2190Mコル付近の稜線は、左側は、雪庇と断崖絶壁。右側は、針葉樹と底抜け腐れ雪の急斜面。ルート選定に、頭を悩ます。2190M最低コルは、かなり怖い所である。雪庇を警戒して、慎重に進む。安全を期し、最後は針葉樹の合間を縫って、腐れ雪と格闘しながら、2276Pへの斜面に取り付く。2276Pへの雪斜面は、結構な急傾斜で、苦しくてもコンスタントに登らねばならない。 苦しい雪斜面の登高をこなし、2276Pに辿り着くと、ぐっと展望が良くなる。小休を入れ、E-1を取り出す。2290MPへ続く、曲谷源頭の大雪庇が物々しい。2290MPから、大屏風の2342P付近も、油断出来ない稜線で、右手は岩肌の出た崖、左手は雪の急斜面である。重荷に耐え、バランスを崩さぬよう、ゆっくりと登る。 2342Pから少し下り、御舎利山への最後の登りをこなす。御舎利山でザックを下ろし、休憩しよう。ここから西へと、チブリ尾根が派生している。空身で、別山往復へと出掛ける。右手には、チブリ尾根が見下ろせる。鞍部から、別山へと登り返すと、単独男性に出会う。 最後のピークで、撮影タイム。南へ続く尾根、東へ続く尾根。縦走へと夢は膨らむ。時間もないので、そろそろ引き返そう。帰路、二人の登山者と擦れ違う。皆さん、チブリ尾根から登って来たようだ。 12時半前に、御舎利山を後にする。御舎利山から、チブリ尾根最上部の露出した夏道を、しばらく下る。アイゼンで浮き石を踏み、歩きにくい。やがて、雪の上を下るようになる。登って来る数人と擦れ違う。2250M付近では、右手に小尾根を見て、雪に埋まった、浅い沢状地形を急降下する。 2160M付近で、右手の小尾根を乗越す。この先、ツボ足の方が快適そうなので、ここで、アイゼンを外す。2100M平坦部からは、しばらく傾斜が緩そうだ。小さな谷状を右へと渡ると、1932Pの右手に、チブリ避難小屋が小さく見えて来る。 チブリ避難小屋は、しっかりした造りであった。小屋を堪能している単独男性がいて、話し込む。この先も、しばらくは雪の上を下る。快適な下りである。 トレースを辿って、安易に下って行くと、1760Mの夏道トラバースを見落としてしまった。雪渓を50Mほど下って、トレースが消え、間違いに気付く。強引に藪漕ぎをして尾根に戻ろうとするパーティもいたが、我々は登り返すことにした。その途中で、道を知る単独男性に出会い、正解ルートを教わる。危ない、危ない。ここで、50分ほどのタイムロス。 夏道を辿って、尾根に復帰し、雪の上と地面とを交互に踏んで下る。1500M付近からは、ブナの原生林の中を下るようになる。1380M付近で尾根を離れ、右手へトラバースするようになる。小さな水場があったので、小休を入れる。やがて沢沿いの道となり、ブナも芽吹き、コブシ・タムシバも咲く。 重荷で、肩が次第に苦しくなり、足の痛みも辛くなるが、様々な春植物の花が慰めてくれた。この後も、林道を横切ったり、林道を歩かされたりして、本当にイヤになる頃、やっとのことで、市ノ瀬のビジターセンターの駐車場に辿り着く。 しばらく放心状態であったが、何とか片付けをして、公衆電話で下山報告する。白峰温泉まで下り、日帰り入浴施設で、湯につかる。こうして、三日間の山旅は終わった。そして、徹夜で北陸道・関越道を運転し、帰京したのであった。 |
![]()
アルバム
 |
◆一日目◆ 下山予定の市ノ瀬駐車場からタクシーで登山口へ移動 県道53号:岩間一里野線入口ゲート |
| 県道脇のキバナノイカリソウ |  |
 |
県道歩き25分でハライ谷登山口に至る |
| 檜新宮参道、スミレ |  |
 |
檜新宮参道、1120M付近から道形は右手の杉林へと入って行く |
| 檜新宮参道、杉林の雪の上を進む |  |
 |
檜新宮参道、1280M付近緩やかな窪状を進む |
| 雪の急斜面を登ると、ハッキリした尾根上に乗る 登るにつれ、次第に、大笠山と笈ヶ岳が見やすくなってくる |
 |
 |
檜新宮参道、尾根の東側の安定した雪庇状を、歩くようになる。 |
| 檜新宮参道の登り |  |
 |
檜新宮参道、大笠山と笈ヶ岳 |
| 檜の新宮 |  |
 |
しかり場分岐先の、長倉山に続く痩せ尾根 |
| 1550M付近から振り返る |  |
 |
1640MP付近から1660.5P:口長倉 |
| 1610MP付近から、・1653P越しに奥長倉避難小屋が見えて来た |  |
 |
今宵の泊り場、奥長倉避難小屋に到着 |
| ◆二日目◆ 奥長倉山から・1968:美女坂ノ頭 |
 |
 |
奥長倉山から四塚山方面 |
| 奥長倉山から小桜平・薬師山方面 |  |
 |
奥長倉山先から・1968:美女坂ノ頭 |
| ・1968:美女坂ノ頭付近から、南方の眺め |  |
 |
百四丈滝展望台から丸石谷右俣百四丈滝 |
| 丸石谷右俣百四丈滝 |  |
 |
丸石谷右俣百四丈滝 |
| 丸石谷右俣百四丈滝 |  |
 |
百四丈滝展望台から百四丈滝 |
| 百四丈滝展望台から四塚山 |  |
 |
・2138Pから、・2158P(右)と四塚山(左) |
| ・2138Pから、四塚山と七倉山 |  |
 |
・2138Pから、大笠山・笈ヶ岳・仙人窟岳遠望 |
| ・2138Pから、左:大笠山、右:笈ヶ岳 |  |
 |
・2158Pの下りから四塚山 |
| 2150M肩付近から・2158Pと・2138P |  |
 |
2150M肩付近から百四丈滝上流の丸石谷右俣 |
| 2150M肩付近から大笠山・笈ヶ岳 |  |
 |
2150M肩付近から四塚山 |
| かめわり坂を登る |  |
 |
かめわり坂上部2290M付近の雪稜 |
| 2300M付近からの長坂はツボ足で夏道を登る |  |
 |
2300M付近から、・2158P、・2138P方面を振り返る |
| 四塚山北肩2460M付近から、・2158P、・2138P方面を振り返る |  |
 |
四塚山北肩2460M付近から七倉山 1313 |
| 四塚山北肩2460M付近から・2415P方面 |  |
 |
四塚山の・2530P横から七倉山と大汝峰 七倉山の夏道トラバースは危険なので、稜線通しで行く |
| 七倉山稜線から四塚山 |  |
 |
七倉山稜線から大汝峰中腹肩越しに別山 |
| 七倉山稜線から大汝峰中腹肩越しに別山 |  |
 |
七倉山稜線から大汝峰 |
| 七倉山・2557P南面を巻き気味に進み、南東面に至る ここでやっと大汝峰へのルートが確認できた |
 |
 |
大汝峰から剣ヶ峰と御前峰 |
| 大汝峰から別山 |  |
 |
大汝峰から別山 |
| 大汝峰山頂 |  |
 |
御宝庫の岩場を南側から巻くように、雪の無い斜面を登り、御前峰の稜線に乗る |
| 御前峰より別山 |  |
 |
御前峰山頂 |
| 御前峰より室堂を俯瞰 |  |
 |
室堂から御前峰を振り返る |
| 室堂より別山 |  |
 |
南竜山荘にて夕日が沈む |
| 南竜山荘より御前峰を振り返る |  |
 |
南竜山荘より別山 |
| ◆三日目◆ 南竜山荘からほぼ真南に進み、・2244.0P西尾根に取付く |
 |
 |
南竜山荘と昨日下降した斜面を振り返る |
| 昨夜の泊り、冬期開放の南竜休憩所 |  |
 |
2244.0P西尾根から・2256P油坂ノ頭 |
| 2244.0P西尾根から御前峰と南竜山荘 |  |
 |
2244.0P西尾根から御前峰と南竜山荘 |
| 2244.0P西尾根から御前峰、・2199P |  |
 |
2244.0P西尾根から西南西方向、赤兎山・大長山だろうか |
| 2244.0Pから・2256P油坂ノ頭と別山 |  |
 |
2244.0Pから御前峰 |
| 2244.0Pから・2256P油坂ノ頭と別山 |  |
 |
2244.0P南肩から・2256P油坂ノ頭と別山 |
| 南肩から2244.0Pと御前峰 |  |
 |
・2256P油坂ノ頭への登り |
| ・2256P油坂ノ頭から2244.0Pと三方崩山 |  |
 |
・2256P油坂ノ頭から御前峰 |
| ・2256P油坂ノ頭から白山釈迦岳、奥は・2158Pか |  |
 |
・2256P油坂ノ頭から赤兎山・大長山だろうか |
| ・2256P油坂ノ頭から大屏風・別山の稜線 |  |
 |
油坂ノ頭から続く穏やかな稜線は、スノーシューで行く |
| 油坂ノ頭と御前峰を振り返る |  |
 |
最低コルが近付くと稜線が痩せて来るので、2230M付近で再びアイゼンに履き替える |
| 最低コル付近から油坂ノ頭に続く肩状を振り返る |  |
 |
最低コル付近から・2276P |
| 最低コル付近の激ヤバ雪庇 |  |
 |
最低コル付近の通過 雪庇は先行者のトレースも当てにならない |
| ・2276Pから2290MP、・2342P、御舎利山 |  |
 |
・2276Pから三方崩山 |
| ・2276Pから雲に隠れた御前峰 |  |
 |
・2276Pから白山釈迦岳と・2158Pだろうか |
| ・2276Pから西方の山々 |  |
 |
2290MP付近から振り返る |
| 2290MP付近から御舎利山方面 |  |
 |
北コル付近から・2342P、右は御舎利山 |
| ・2342P北コル付近から振り返る |  |
 |
・2342P付近から御舎利山 |
| ・2342P付近から振り返る |  |
 |
・2342P付近から、御前峰方面を振り返る |
| 御舎利山にザックをデポし、別山へ向かう |  |
 |
別山へ向かう途中から、チブリ尾根・1932方面 |
| 別山から、御手洗池と三ノ峰、ニノ峰 |  |
 |
別山から、ニノ峰と一ノ峰 |
| 別山から東方、2168.6P方面 |  |
 |
別山から御舎利山、御前峰方面 |
| 御舎利山へ戻る途中で、別山を振り返る |  |
 |
チブリ尾根上部 |
| 2160M付近で、下って来た雪の浅窪状を振り返る |  |
 |
2160M付近の右手の小尾根を乗越す所で、アイゼンを外す |
| 2160M付近の小尾根乗越から、チブリ尾根下部 |  |
 |
2020M付近 |
| ・1932付近から、避難小屋 |  |
 |
チブリ尾根避難小屋 |
| 1760M尾根復帰付近 雪斜面から藪っぽい夏道に入る |
 |
 |
林道に降り立つ、駐車場までは更に30分ほど歩く |
![]()