妙高山・火打山・焼山・金山・雨飾山(頸城)
![]()
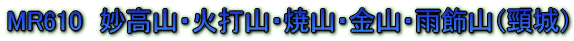
| date | 2008/10/10〜13 晴のち曇のちガス、雨、晴、晴のち曇 |
| コース | 燕温泉〜赤倉温泉源泉〜妙高山〜黒沢池〜高谷池〜火打山〜焼山〜富士見峠〜金山〜シゲクラ尾根〜雨飾山〜梶山新湯 |
| 実働 | 集合日:2h、第一日:7h、第二日:7h、第三日:8h25m、計:24h25m。 |
| 概要 | 燕温泉から梶山新湯へ、紅葉の頸城アルプス縦走。 |
| メンバー | Tds君、Sgs君(某山岳部)、すうじい |
| 行程 | →:山道、→:溯行、→:藪漕ぎ・踏跡不明瞭、=:交通機関。 【10月10日】 晴のち曇のちガス 燕温泉14:00→→→14:50惣滝下14:55→→→燕温泉15:20→15:30黄金湯・惣滝展望台15:40→16:15赤倉温泉源泉(ビバーク) 【10月11日】 雨 赤倉温泉源泉8:15→8:30称明滝8:40→9:30小休止9:40→10:25天狗堂10:55→11:45小休止11:55→12:55妙高山13:25→14:20長助池分岐14:35→15:20大倉乗越15:30→黒沢池15:50→17:10高谷池(幕営) 【10月12日】 晴 高谷池7:10→7:40天狗ノ庭7:50→8:30雷鳥平8:50→9:50火打山10:00→10:55 影火打西尾根2200M付近11:25→12:25胴抜キレット西2030MP 12:35→焼山直下2020Mコル12:40→13:20 2250M噴気口近く13:30→14:20焼山14:35→15:35泊岩15:40→16:00富士見峠(水:西へ下り10分)(幕営) 【10月13日】 晴のち曇 富士見峠4:45→5:35 2106P東5:45→6:35金山7:05→7:25 2050M付近7:35→8:15 1760M肩8:25→茂倉峰8:35→白倉峰9:00→9:10黒沢峰手前9:25→黒沢峰9:30→10:10大曲(水)10:35→小谷温泉分岐11:30→11:35梶山新湯分岐11:40→12:00雨飾山12:15→12:35梶山新湯分岐12:55→中ノ池13.:30→13:40休13:55→14:35 ・1309肩14:45→15:05山ブドウ15:15→15:55梶山新湯(入浴)17:45=Taxi=18:30糸魚川=越後湯沢=東京 |
| 使用装備 | 革登山靴、幕営用具、ガスコンロ、E-3、ED12-60mmF2.8-4.0、μ-725SW、ヘッドランプ、雨具 |
| 不用装備 | 細引 |
| 記録 | 某山岳部のTds君からのお誘いで、頸城の縦走をすることになった。思えば、24年前の秋に、真川裏金山谷・金山谷・鍋倉谷の溯下降をした際、同時期に仲間が妙高〜雨飾の縦走をしたのであった。それ以来、いつの日か頸城主脈の縦走をして、梶山新湯へと下りたいと思い続けていた。 【10月10日】 晴のち曇のちガス ヒコサノ滝、苗名滝、惣滝の見物を終え、燕温泉から舗装された道を、黄金湯へと登る。黄金湯の露天風呂前で、湯上がり客に湯加減を尋ねると、「もう最高!」の返事。黄金湯の前にザックをデポし、舗装された遊歩道をそのまま登って行くと、惣滝展望台へと至る。先客が一人。ガスが懸かって、今一つハッキリ展望出来ないのが、残念である。 黄金湯へ戻り、ザックを背負って、車道へと戻る。スキー場の中の道を登れば、やがて、細い赤倉温泉源泉管理道へと入る。この舗装された登山道は、北地獄谷右岸沿いに登って行く。黄金湯から35分で、赤倉温泉源泉に至る。ここには、この山域では貴重な、良い水場がある。 源泉管理小屋があって、良い目印になっている。但し、この小屋は、一般には使用出来ない。この辺り、辛うじてDocomoの電波が届くので、後発隊2名との合流場所としたのは、正解だった。夜になって、妙高高原駅からタクシーで燕温泉に着いた2名が、登って来て合流する。この夜は、ここでビバーク。 【10月11日】 雨 翌朝、予想通りの雨である。舗装された登山道から、光明滝が見下ろせる。光明滝を越えると、称明滝下に至る踏跡があるので、見物に行く。霧雨のため、滝の撮影は難しい。驚いたことに、滝の直下に、露天風呂までこさえてあった。 称明滝の高巻き道に入り、ジグザグに登って行くと、薄日が射してくる。蒸し暑い。辺りの紅葉に、陽が当たって綺麗だ。再び地獄谷に戻り、沢沿いを歩くようになると、麻平からの登山道と合流する。急に、登山者が多くなる。 合流地点からは、地獄谷の右岸沿いに登って行く。北地獄谷源頭の紅葉に、時折陽が当たって、見事である。やがて、北地獄谷から離れて、南側の斜面を登るようになる。前山から続く尾根に取り付くのだ。妙高山東面の紅葉が美しい。苦しい登高も、見事な紅葉が慰めてくれる。 前山からの尾根に乗れば、気持ちに余裕が出てくる。この辺りの紅葉も美しい。やがて天狗堂前で、大谷ヒュッテ側から登ってくる道と合流する。ここで、大休止しよう。 天狗堂から少し登ると、光善寺池の畔に出る。小さな池だが、心落ち着く雰囲気である。天狗堂から50分ほど登った所で、小休を入れる。休憩を終え、歩き出したところで、再び雨が降り出す。次第に傾斜が増し、鎖場も現れる。 やっと飛び出した所は、最高点の2454神社のピークである。2445.9三角点ピークは、少し下って登り返した所にあった。肌寒い山頂では、テルモスのお湯が有り難い。ガスで展望も全く無いのに、30分の大休止となってしまった。 さて、少し北へ進み、窪状を西から北西へと向かうだが、イヤになるほどの下りが続く。1時間弱で、長助池分岐に到達する。ここから、大倉乗越への長いトラバースが始まる。次第に、右手に長助池の草紅葉と周囲の紅葉が見えてきて、なかなかの眺めである。最後に、ズルズルの急登を強いられ、大倉乗越に至る。 大倉乗越からは、樹林帯の緩やかな下りで、やがて黒沢池・茶臼山方面の紅葉が見えてくる。黒沢池ヒュッテでは、かなりのテントが張られており、高谷池で張る余地があるか、ちと心配になったが、取り敢えず行ってみることにする。因みに、黒沢池ヒュッテの今夜の予約は、400名という話であった。 霧雨の中の行動が続き、疲れ果てた所で、ダメ押しの茶臼山越えをして、高谷池に出る。午後5時を過ぎ、既に受付テント数が定数をオーバーしているテント場は、文字通り満杯であったが、泥んこ気味の場所に無理矢理2張追加設営する。 夜中に寒冷前線が通過したらしく、フライは凍り付き、周りを歩く足音が、パリパリするようになった。 【10月12日】 晴 パリパリになったフライをたたみ、高谷池のテント場を撤収する。重荷と凍結した木道に、バランスを崩しがちだ。高谷池の草紅葉の上に、火打山が姿を見せている。木道沿いに高谷池を回り込んで振り返ると、高谷池ヒュッテの三角屋根が目に入る。 高谷池から天狗ノ庭へと向かう木道も、ツルンツルンに凍結しており、全くペースが上がらない。天狗ノ庭へ向けて、緩やかに下る木道は、まるでスケートリンクのようだ。天狗ノ庭の木道に入ると、見事な景色に、思わず撮影タイムとなってしまう。池塘の草紅葉と、周囲の紅葉とが、秋山の魅力を引き立てる。 天狗ノ庭から一段登った2150M付近から振り返ると、高妻乙妻、そして槍ヶ岳などの北ア南部の山々が、雲海上に姿を見せている。尾根の右手には、黒菱山・鬼ヶ城へと続く2124Pの紅葉が美しい。2124Pの上部に続く2276Pの岩壁もまた、青空に映えている。このような景色を愛でつつ、登高してゆくのも、また秋山の醍醐味かもしれない。 更に登って、2230M付近から天狗ノ庭と妙高を振り返る。あまりの眺めの良さに、小休を入れることにする。雲海の雲が薄くなり、高妻乙妻の麓の方まで見えて来ている。目を凝らせば、富士山も見えている。気が付けば、天狗原山の左手の雲海上に、北アルプス北部の山々も姿を見せている。 2310MPを越え、枯れ枝に着いた霧氷を楽しみながら、稜線漫歩となる。巻雲の青空を背景に、霧氷と山頂を仰ぐ。最後の斜面の階段状を登れば、やがて火打山山頂に至る。山頂は、かなりの人出であった。 我々には、当然の事ながら、これから縦走する山々のことが気になる。次のピークである影火打、そして胴抜けキレット越しに、噴煙蒸気を上げるドーム焼山、懐かしの金山。かって、秋の鍋倉谷から天狗ノ庭を経てこの山頂に立った時、一番印象に残った焼山北方溶岩台地。振り返れば、逆光ながら、ちと鈍臭い妙高の後ろ姿が、遠方の山々を従えて望まれる。 火打山から西へ、ハイマツの間の踏跡を辿る。穏やかな影火打北面に、霧氷が見える。影火打山頂付近は、二重山稜状になっていて、窪地はビバーク適地である。踏跡は窪地の北側を辿っており、南側の2384独標は通らない。2345Mコルで振り返ると、影火打北面の霧氷越しに、火打山が望まれる。足元を見下ろすと、僅かながら、雪田が残っている。 影火打の西面で、休憩中の単独登山者に出会う。火打からの往復で、ここから引き返すらしい。眺めが良い場所なので、我々も撮影タイムとする。キレットの紅葉も、なかなか美しい。尤も、痩せた稜線の急降下は、結構厳しそうだ。焼山北方には、昼闇(ひるくら)山・阿弥陀山など、独特の岩肌を持つ山々が、その魅力的な姿を見せている。あの稜線にも、足を伸ばして見たいものだ。 撮影タイムを終え、西尾根を下降する。急な下り道は、霜解けで滑り易く、要注意である。焼山手前の胴抜キレット目指して下るのだが、あんなに下って、登り返すのかと思うと、ちと溜息が出そうだ。どんどん下って行けば、次第に焼山が高くなる。焼山の登りが辛そうだ。 キレットへの痩せ尾根急降下に備え、2200M付近で休憩を入れる。ここからも、周囲の展望は素晴らしい。更に急な下りを続けると、いよいよ、胴抜キレットの痩せ尾根が迫る。この辺り、ザレた所もあるので、重荷では注意を要する。火打から焼山往復だという、男女ペアと擦れ違う。 胴抜キレットを越え、2030Mの丘陵状で小休する。目前に、焼山東面が立ち塞がる。上部の噴気口からは、噴煙蒸気が立ち上る。あんな所まで、登るのか。振り返れば、蜿蜒下って来た影火打西尾根が、これまた高い。少し行くと、焼山直下の2020Mコルだが、ここは長閑な草っ原である。2万5千図では、ここがキレットとの記載があるが、どう見ても、切戸とは言い難い。 焼山に取り付くと、しばらくは樹林帯の登りだが、やがて草付の登りとなる。迷うほどではないが、踏跡は、かなり薄めである。気が付けば、そこここに、シラタマノキが白い実を付けており、紅葉も見事だ。登るにつれ、火山特有のザレた斜面となり、噴煙を上げる噴気口と同じくらいの高さで、小休する。火打・影火打が正面に望まれ、如何に大下りをし、そして登り返したか、実感される。 噴気口近くの小休から、さらなるアルバイトで、ついに焼山の爆裂火口縁へと到達する。逆光の山頂が眩しい。足元には、爆裂火口のボロボロの急斜面と旧火口が目に入る。その向こうには、昼闇山やゴツゴツした特異な形状をした岩峰群が連なる。 山頂と思しき地点に移動すれば、風が冷たい。金山・天狗原山方面を望めば、その手前に裏金山、奥には後立の山々が連なる。さらに、金山の右手には雨飾山、奥には白馬三山も見える。山岳展望には飽きることは無いが、なにせ風が冷たい。早々に、山頂を辞することにしよう。 先ずは、ザレた稜線を西へ下り、岩峰を回り込む。岩峰から北へ岩稜を下る。鎖とロープが設置されているが、重荷では、慎重に下りたい。北側旧火口の西縁に降り立ってから、窪状を西へと下って行く。開けた草付斜面の小尾根状を下るようになるが、薄い踏跡や目印を見失わないようにしたい。やがて、左へとトラバース気味に下るようになり、次第に落葉疎林帯に入って行く。 焼山山頂から1時間の下りで、湿気た所をすり抜けて(残念ながら水は得られない)、泊岩に至る。戸は外れ、内部を覗くと、床も抜けている。雨の日は、有り難いかもしれないが、ちと使う気にはなれない。泊岩から少し下ると、カレ沢沿いのT字路に出る。右手に下れば、溶岩台地を経て、笹倉温泉に至る道だ。左へ登る道を辿る。 カレ沢沿いの道は、やがて刈り払われた笹斜面のトラバースとなり、右下に海谷源頭と思しき窪状草地を見て、富士見峠へと至る。泊岩から、20分ほどであった。驚いたことに、富士見峠の切り開きには、テントが2張設営されていた。 早速、峠の西側に見た窪状草地へ、水場を捜しに出掛ける。草地には水たまりもあり、有望と見て、沢状を下って行く。期待通り、峠から10分の下りで、冷たい流水を得る。これで、思いっ切り水が使えるぞ。登り返しも、10分強であった。 先客2張は、金山方面から縦走して来た単独男性と、真川沿いの道を登って来て金山を往復したという男女ペアであった。何れのコースも、刈払いしてあると言う。我々も、テント2張を設営し、富士見峠は、予想外の人口密度となった。 【10月13日】 晴のち曇 前日、予定の金山まで行けず、富士見峠に幕営したため、この日は暗いうちにヘッドランプを点けて出発した。裏金山への尾根は、いきなりの笹藪であるが、しっかり刈払いされているので、藪漕ぎは無い。それでも、暗いうちは、踏跡を外しそうになる。 裏金山は、踏跡が西面をトラバースしているので、素通りしてしまう。このトラバースは、根曲りの上を歩くため、極めて滑り易く、難色である。でも、背丈を超す笹藪漕ぎのことを思えば、随分と助かる。笹藪の刈払いは、切り株が尖っているので、転倒すれば刺さりかねない。慎重を要する。 裏金山西面トラバースを終え、再び稜線を歩くようになると、大分明るくなり、ヘッドランプを消す。踏跡は、尾根の南斜面を辿るようになり、富士見峠から50分ほどで、2106P手前まで進むことが出来た。金山までのロングピッチは無理と見て、ここで小休を入れる。 2106P先のコル、そして24年前の裏金山谷溯行でツメ上げた辺りを過ぎた稜線東面の草地で、無性に懐かしさがこみ上げる。振り返れば、昨日苦労して越えて来た焼山・火打のシルエットが浮かび上がる。草地の踏跡には、霜が降りている。尾根東面の草地に付けられた、薄い踏跡を辿って、金山山頂に至る。 刈払いのお陰で、富士見峠から、実働1時間40分であった。金山から南へ、神ノ田圃や天狗原山へと続く踏跡がある。24年前は、神ノ田圃でビバークし、金山谷へと下ったのであった。金山を後にして、西へシゲクラ尾根を下降する。金山東面の乾いた草付の薄い踏跡とは違い、ハッキリとはしているが、樹林帯の湿った道である。滑り易く、展望はあまり得られない。 20分ほど下ると、開けた尾根上の道となり、展望が得られるので、撮影タイムとなる。南方には、大倉沢を挟んで、金山南西へと派生する尾根の、2025Pが北壁を擁して顕著である。正面には、これから向かう雨飾山が存在感を示す。背後には、白馬北方稜線と水平線が続く。 少し下って、右手を振り返ると、2106Pから北西へ海谷へと続く尾根に、紅葉が美しい。その尾根越しに、焼山の頭が覗いている。さらに下り、展望のない所で小休後、急降下をして、痩せ尾根を渡ると、1650M茂倉峰である。何の道標も無いが、尾根道が左へと折れるので、判り易い。 茂倉峰から西へ下る尾根は、傾斜が緩くなり、ルンルン歩きとなる。どこが山頂だかハッキリしない白倉峰を過ぎ、展望の良い所で、小休する。雨飾山が、高い。これから登る黒沢峰がすぐそこに、そして大曲の1650MPから、北端の1652Pまで、四つの小ピークが並ぶ。 黒沢峰から1574Pを経て紅葉の中を登って行くと、1650MPの手前で、道は左へとトラバースする。鋸岳からの道は、1650MPから東南東へ下る尾根から少し南へ外れ、水場で合流している。大曲のT字路では、正面の小沢で、水が得られる。振り返れば、笹の上に、金山・天狗原山が望まれる。 大曲から、水場の沢を越えて登って行くと、次第に傾斜が増し、標高差200Mほどの急登が待ち構える。水場から1時間弱のアルバイトで、本日初めての他パーティの声を聞き、笹平の一角に飛び出す。予想はしていたが、人人人・・・。 笹平の梶山新湯分岐にザックを置いて、雨飾山を往復する。人通りが多いので、登山道の擦れ違いに、時間が掛かる。次第に雲が出てきて、ガスもかかりがちとなる。山頂は、まさに人だかりであったが、紅葉の連休ともなれば、この人出も当然だろう。2万5千図には、西尾根に破線が付いている。機会があれば、辿ってみたいものだ。 笹平の梶山新湯分岐から、北へ下って行く。このコースを登ってくる人も、意外と多い。1560M付近まで下ると、平坦な場所を通り、中の池がある。モリアオガエルが棲息するという。もう一つの池を覗くと、大きな黒っぽいオタマジャクシが、ウヨウヨ居た。これは、別の種類であろう。 ・1309肩付近から、下ってきた紅葉の尾根を振り返る。さらに下って行くと、登山道の脇で、藪の中で木々に取り付いている人々がいる。ヤマブドウの実を、集めているようだ。我々も、ザックを置いて、このイベントに参加する。 梶山新湯に到着し、タクシーを呼んで貰い、その間に入浴する。「都忘れの湯」と言われるそうだが、仕事を忘れて、しばらく滞在したくなった。糸魚川から、メチャ混みの特急はくたか・上越新幹線を乗り継ぎ、帰京する。 |
![]()
アルバム
 |
【10月10日】 展望台から大田切川大倉谷惣滝 |
| 赤倉温泉源泉水場 |  |
 |
赤倉温泉源泉管理小屋 |
| 【10月11日】 大田切川北地獄谷光明滝落口 |
 |
 |
大田切川北地獄谷称明滝 |
| 称明滝と露天風呂 |  |
 |
北地獄谷源頭の紅葉 |
| 妙高山東面の紅葉 |  |
 |
妙高山東面の紅葉 |
| 天狗堂付近の紅葉 |  |
 |
天狗堂 |
| 光善寺池 |  |
 |
妙高山三角点 |
| 長助池方面 |  |
 |
黒沢池・茶臼山 |
| 霧雨の高谷池 |  |
 |
【10月12日】 高谷池と火打山 |
| 高谷池とヒュッテを振り返る |  |
 |
天狗ノ庭と火打山 |
| 天狗ノ庭と・2276P |  |
 |
天狗ノ庭と火打山 |
| 2150M付近から天狗ノ庭と高妻乙妻 |  |
 |
2150M付近から・2124P |
| 2150M付近から・2276Pと・2124P |  |
 |
雷鳥平から天狗ノ庭と妙高山 |
| 雷鳥平より天狗ノ庭と高妻乙妻 |  |
 |
雷鳥平より北ア北部 |
| 雷鳥平より富士・八ヶ岳・南ア方面 |  |
 |
火打山の霧氷 |
| 霧氷と火打山 |  |
 |
火打山頂から、影火打・焼山・金山 |
| 火打山頂から、焼山北方溶岩台地 |  |
 |
火打山頂から、妙高山を振り返る |
| 火打山頂から、天狗ノ庭と高谷池、妙高山 |  |
 |
火打山頂から、雨飾山 |
| 火打山の下りから、影火打と焼山 |  |
 |
影火打北面の霧氷 |
| 影火打西面から、影火打北面雪田 |  |
 |
影火打西面から、胴抜キレット・焼山 |
| 影火打西面から、胴抜キレット付近の紅葉 |  |
 |
影火打西面から、昼闇山・阿弥陀山 |
| 影火打西尾根の下り |  |
 |
焼山を正面に下る |
| 焼山北方溶岩台地 |  |
 |
影火打西尾根を、さらに下る |
| 2200M付近から、金山と白馬三山 |  |
 |
2200M付近から、焼山 |
| 2200M付近から、金山〜高妻乙妻 |  |
 |
胴抜キレット直前 |
| 胴抜キレット西の2030MPから、焼山東面を仰ぎ見る |  |
 |
胴抜キレット西の2030MPから、影火打西尾根を振り返る |
| 穏やかな2020Mコル とてもキレットとは言い難い |
 |
 |
2020Mコルから、2030MPと影火打を振り返る |
| シラタマノキ |  |
 |
焼山東面2200M付近より、火打山と影火打 |
| 焼山東面2200M付近より、妙高山 |  |
 |
焼山東面2200M付近より、黒姫・飯縄・高妻乙妻 |
| 火口縁から焼山山頂 |  |
 |
北側旧火口と昼闇山 |
| 焼山から、金山・後立山 |  |
 |
焼山から、金山・雨飾・白馬 |
| 焼山から下降開始 |  |
 |
火口西側外縁より北側旧火口を俯瞰 |
| 泊岩外観 |  |
 |
泊岩内部、雨風は凌げそうだ |
| 富士見峠近くの海谷源頭窪状草地 |  |
 |
富士見峠から南西方向、海谷源頭下り10分の水場 |
| 【10月13日】 裏金山谷右俣源頭稜線より、 焼山・火打シルエット |
 |
 |
黒裏金山谷右俣源頭稜線より、 姫山方面 |
| 裏金山谷右俣源頭稜線の踏跡 |  |
 |
裏金山谷右俣源頭稜線より、 裏金山・焼山・火打山を振り返る |
| 金山山頂 |  |
 |
金山から南へ続く踏跡 |
| 茂倉尾根2050M付近から、・2025P |  |
 |
茂倉尾根2050M付近から、雨飾山と日本海の水平線 731 |
| 茂倉尾根2050M付近から、白馬三山方面 |  |
 |
茂倉尾根2050M付近から、高妻乙妻 |
| 茂倉尾根1900M付近から、・2106P北西尾根越しの焼山 |  |
 |
黒沢峰手前から、笹平1894Pと雨飾山 |
| 黒沢峰手前から、荒菅沢奥壁群・笹平 |  |
 |
黒沢峰手前から、黒沢峰・大曲方面 |
| 大曲から金山 |  |
 |
笹平から雨飾山 |
| 雨飾山から西尾根 |  |
 |
雨飾山頂 |
| 雨飾山頂から、笹平を俯瞰 |  |
 |
中の池 |
| ・1309肩付近から、紅葉の尾根 |  |
 |
ヤマブドウの葉 |
![]()
 へ へ |