不動道・二瀬道から和名倉山川又道下降(奥秩父)
![]()
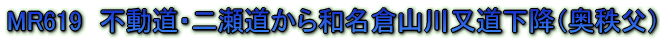
【注意!】不動道・川又道は、迷い易い箇所が多く、二瀬道ほど踏まれていません
| date | 2009/4/24 晴のち曇 |
| コース | 川又バス停〜不動滝〜不動道〜1369.4P西コル〜二瀬道〜和名倉山〜二瀬分岐〜金山沢中間尾根上部下降〜川又道〜川又バス停 |
| 実働 | 登り:6h07m、下り:3h04m、計:9h11m。 |
| 概要 | 川又基点、不動道から二瀬道に合流、川又道下降周回。 |
| メンバー | すうじい(単独) |
| 行程 | →:山道・踏跡、→:溯行、→:藪漕ぎ・不明瞭な踏跡、=:車 【4月24日】 晴のち曇 自宅3:10=4:50影森コンビニ5:10=5:47川又バス停6:20→不動滝入口6:44→6:57不動尊(不動滝見物)7:14→大除沢木橋7:29→8:05 870Mコル8:10→作業道引返点8:27→1000M付近不動尾根上復帰8:36→8:50 1070P 9:00→9:30 1180M付近トラバース開始点9:40→→→10:35 1369.4P西コル10:40→11:10水場11:25→→12:15 笹藪上1680Mコル12:25→12:43展望台12:49→13:13笹ッ場13:23→13:43二瀬分岐13:51→14:03和名倉山14:08→14:19二瀬分岐14:22→(金山沢中間尾根上部下降)→14:40川又道14:50→曲沢下降点15:00→1826肩15:20→15:27 曲沢左俣右沢源頭1830M作業場跡15:32→15:48 1762P北15:53→→(850M付近針葉樹植林帯)→→17:35川又バス停18:08=20:35自宅 |
| 使用装備 | 長靴、ヘルメット、μ-725SW、杖(拾った棒) |
| 不用装備 | 6mmx10m細引、運動靴、ピッケル |
| 記録 | 大除沢溯行時の下降に使った不動道を登りに使い、昨年雪で敗退したヒルメシ尾根の川又道を下降に使って、周回してみた。 【4月24日】 晴のち曇 例によって、影森のコンビニで食料を調達し、R140の川又バス停観光トイレ裏に駐車する。軽量化を図るために、今回の足周りは登山靴・アイゼンを省略し長靴、カメラはE-1・三脚を省略しコンデジμ-725SWのみである。 舗装された旧道を歩き、不動滝遊歩道入口へと向かう。25分の歩きで、遊歩道入口の東屋が見えてくる。ここから、ジグザグの遊歩道を吊橋(不動橋)まで下る。対岸に渡って、今度はジグザグに登りである。歩き始めて40分で、不動尊前のテーブル・ベンチへと到着する。 ザックを下ろして、お茶を飲もう。時間節約のため、滝写真は撮らないつもりであったが、ここまで来て、不動滝を見ないのは、やはり惜しい。空身で滝見物に向かう。今日の不動滝は、結構、水量がある。数枚のコンデジ写真を撮って、引き揚げる。暑くなりそうなので、上着を脱いでおこう。 不動尊の祠の横から、尾根沿いに登って行く。すぐに左へトラバースする薄い踏跡は、不動滝上へ向かうものだが、尾根沿いにしばらく登る方が、ハッキリした杣道となる。やがてトラバースとなり、数ヶ所のザレ沢を横切り、やがて大除沢を木橋で渡る。木橋の下流側は、綺麗なナメとなっている。 右岸に渡ると、ヒトリシズカの群生が、あちこちに見られる。少し沢沿いに登ると、大除沢右岸杣道から戻るように分岐する薄い踏跡があるが、これが不動道の入口だ。不動道の踏跡を辿り、戻るようにトラバース気味に登って行くと、やがてジグザグ登りとなる。 踏跡は、一旦小尾根に出て、不動尾根871Pの南面をトラバースするように登って行く、比較的明瞭な道形となる。道形を辿ると、871P南の平坦地形に出る。道形は、さらに続き、やがて871東コルへと至る。 871東コルから先も、尾根の南西面にトラバースの道形が続くが、どんどん尾根から離れるようなので、途中から尾根へとよじ登る。少し登った900-950M付近で、左へとトラバースする踏跡を見付け、これを辿ってみたが、植林帯の小尾根に出たところで、さらにやや下り気味にトラバースしていた。東大演習林の作業道のようだったが、上中尾向沢方面へ続いているのかもしれない。 戻るのも癪なので、植林帯の小尾根を直登する。1000M付近で、不動尾根上に復帰する。少し登ると、1060Mで傾斜が緩くなる。先程の植林帯直登で消耗したので、1070Pで小休しよう。垣間見えるのは、二瀬尾根1515P方面であろうか。1070Pの先はストンと下って、東コルに出る。 東コルから、再び尾根沿いを登って行く。1800M付近の尾根上の立木に、古い目印があったが、トラバース開始点付近は、枯葉が積もっており、道形が全く判然としない。目印(昨年巻いた黄ガムテープと今回のスズランテープ)を巻いた立木から、水平に行くと、踏跡を見失う。正解は、左上方へ登る、極めて薄い踏跡だ。この踏跡を見出すのに、10分ほど歩き回った。 トラバース開始点付近の不明瞭な踏跡も、少し辿ると、ややハッキリしてくる。これをひたすら辿って、どんどん進もう。小尾根を回り込むと、やがてガレ沢地帯に突入する。このガレ沢地帯は、踏跡が不明瞭なので、注意が必要だ。スズランテープで、目印を補強しておこう。 ここを過ぎると、再び踏跡が明瞭になり、トラバースを続ける、やがてザレルンゼの手前で、ジグザグ登りとなり、少し高度を稼ぐ。再びトラバースの踏跡がザレルンゼにぶつかると、踏跡は一段登る。その後、ルンゼに降りて、慎重に渡ることになる。急なザレの上に、枯葉が降り積もって、不安定だ。対岸の踏跡目指し、少し登り気味にルンゼを横切る。 最大の難所を過ぎて、再びトラバース気味に進んで行く。やがて1369.4P北西の平坦な尾根に乗り、向きを変えて、1369.4P西コルへと至る。小休後、南へ下り、二瀬道の1350Mトラバースに合流する。ここからは、水平軌道跡と思われる明瞭な道形が続く。 少し行くと、東大演習林のバス停型看板がある。左下へ、石津窪左岸道が分岐する。これを見送って、新反射板のある尾根を、大きく回り込むと、左前方に和名倉山頂が見えてくる。 トラバース道が、作業小屋跡に消え、残骸を通り抜けると、小沢状に突き当たる。さらにトラバースを続ける道形もあるが、水平道は次第に薄くなり、和名倉沢1380M右岸枝沢出合に至る。 二瀬道の方は、小沢状に沿って登って行く。小沢状を少し登った場所に、水場がある。水場から先は、苔生したゴーロ状の左側に沿って、登って行くことになるが、少々判り難いので、目印を見落とさぬようにしたい。次第に藪っぽくなり、ズルズルの泥斜面をよじ登る。やがて、和名倉山名物の笹藪となる。 以前の笹藪に比べ、近年かなり薄くなってきている。木々の成長に伴う陽当たり減少が一番の理由であろうが、二瀬道利用の登山者増も、かなり影響しているであろう。笹藪廊下に飽きる頃、1680Mコルに出て、笹藪廊下は終了する。'07-09の大除沢溯行時、このコルに突き上げたのだった。 1680Mコルからは、二瀬尾根をほぼ忠実に登る。針葉樹・常緑樹に覆われていて、展望は得られない。コルから20分ほど登ると、肩状の小ピークで展望を得る。二瀬尾根では、数少ない展望台である。展望台から少し進むと、尾根上のちょっとした広場に出る。索道施設の跡のようで、樹木に囲まれていて、展望は得られないが、休憩に適している。ここからは、二瀬尾根の南東面をトラバースするように、道が付けられている。 索道広場から、樹林帯のトラバースを20分ほど続けると、笹ッ場と呼ばれる、開けた草地斜面に出る。笹ッ場下の樹林の中には、僅かながら雪も残っていた。笹ッ場を抜けると、北ノタルの鬱蒼とした樹林帯に入る。薄暗くて、林床は、切り株・倒木も含め苔生している。苔の踏まれて薄くなっているところが、道である。 道は、しばらく南へ緩やかに登り、いつの間にか鬱そうとした針葉樹林を抜ける。混淆林となり、広い尾根の西側を巻くように進む。金山沢・曲沢の中間尾根上部は、針葉樹の藪が濃く、また尾根筋がハッキリしないため、下降には適さないと思われた。やがて、岳樺の疎林となった金山沢中間尾根上部を通過するが、ここは下降できそうだ。 間もなく、二瀬分岐に至る。ザックをデポし、和名倉山頂を往復してこよう。二瀬分岐からトラバース気味に進むと、すぐに千代蔵ノ休場と呼ばれる、広い荒れ地斜面に出る。道はその下端を通り抜けて、緩やかに登って行く。やがて、山頂手前の荒地に出る。ここから、密林に突入し、数分で、山頂の切り開きに出る。 相変わらず、展望のない山頂である。方向感覚が、麻痺しそうだ。すぐに引き返し、二瀬分岐へと戻ろう。千代蔵ノ休場を通過し、二瀬分岐にデポしたザックを回収する。二瀬分岐は、およそ2000M付近である。ここから、川又分岐まで回るのでは、ちと時間が掛かる。時間節約のため、金山沢中間尾根上部を直接下って、川又道に出ようと言う作戦なのだ。 適当に西へ向けて、藪を漕いで行くと、やがて、次第に尾根がハッキリして来る。この金山沢中間尾根上部を、標高差にして、150mほど下ってゆく。途中、傾斜が強くなるが、やがて傾斜が緩み、1850M付近で、予定通り川又道の踏跡に出合う。ホッとする。時刻は14:40、何とか日没前に下山できそうだ。小休して行動食を頬張り、水分を補給する。あとはこの川又道を下るだけだ。 10分も歩くと、曲沢下降点である。立木の根元に、赤丸ペンキ印が付けられている。道は、少々アップダウンがあるので、見失わぬよう注意が必要だ。さらに30分弱進むと、昨年4月に雪で敗退した、曲沢左俣右沢源頭1830M作業場跡。ここも、見覚えのある地点である。 1830M作業場跡を過ぎて、なおもトラバースを続けると、やがて1735Mコルへと至る。この辺りから、笹藪帯となるのだが、一昨年のことだか、刈払いが行われたらしく、歩き易くなっている。道は、なだらかに、1762Pの北側を巻いている。1762Pは、まさに藪の中である。 さらに、道は北へと続く。樹林帯は、所々藪っぽくなっているが、尾根の西面をトラバースするように、踏跡は続く。笹藪の方が、刈り払われていて、道が明瞭である。やがて、久渡ノ沢右岸斜面の笹藪の中を、下って行くと、1400-1450M付近で、広場のような斜面に出る。 さらに下ると、再びトラバースが始まり、久渡ノ沢右岸枝沢である涸れたガレ沢を横切り、笹藪は消えてくる。1173Pの尾根に乗る前のトラバースの辺りから、ドコモの携帯メールが届くようになる。尾根に乗ると、歩き易い。尾根の左手には、平坦地が広がる。水さえあれば、快適なサイトになりそうだ。 道は、1173P手前の馬酔木の多い1165Mコルから、右手の斜面を下り始める。トラバース気味の下りと、ジグザグ下りを繰り返しながら、次第に高度を下げて行く。涸れ小沢を渡って、小尾根を下ると、850M付近の針葉樹植林帯に突入するが、この辺り極めて迷い易い。暗い植林帯で踏跡を外し、適当に下って、再び踏跡に復帰する。右手に和名沢を見ながら左岸を下って行くと、やがて吊橋へと至る。 やっと吊橋に辿り着き、川又バス停のあるR140を見上げる。釣り橋を渡り、最後の登り返しを頑張れば、愛車が待っている。長かった一日行程も、フィナーレを迎える。 |
![]()
概念図
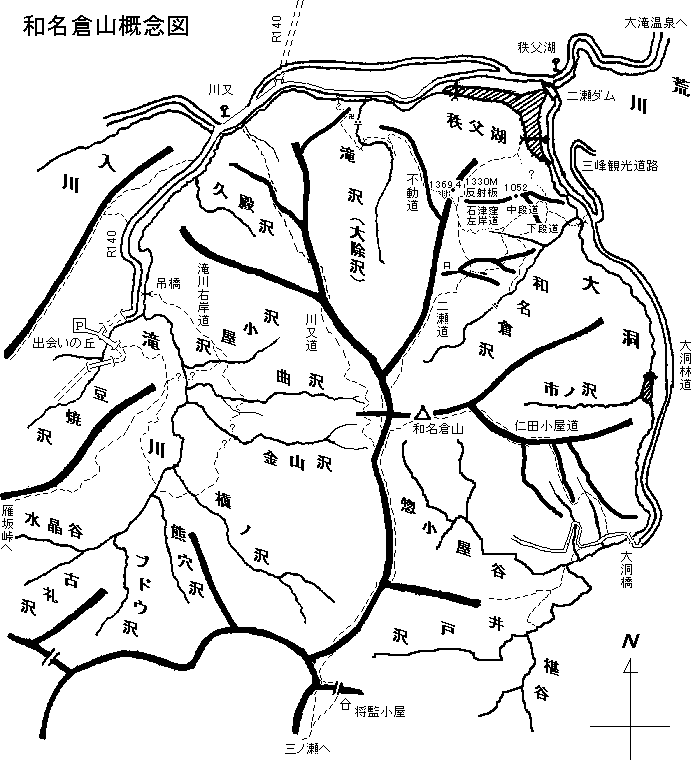
アルバム
 |
川又バス停の観光トイレ (前年4月撮影) |
 |
不動滝入口の東屋 |
| 不動滝入口吊橋 |  |
 |
不動尊 |
| 大除沢不動滝 |  |
 |
大除沢不動滝 |
| 大除沢不動滝 |  |
 |
大除沢木橋下流のナメ |
| 大除沢杣道木橋 |  |
 |
ヒトリシズカ |
| 不動沢杣道から不動道取付 |  |
 |
・871P南平坦地 |
| ・871P南平坦道形 |  |
 |
875Mコル |
| 875Mコルから先も、尾根の南西側に道形が続く 尾根から離れてゆくので、途中から強引に尾根に登って復帰する |
 |
 |
・1070P |
| ・1070P |  |
 |
1180M付近トラバース開始点を振り返る |
| 1180M付近トラバース開始点 登り気味に薄い踏跡が続く |
 |
 |
上中尾向沢源頭トラバースで振り返る |
| 上中尾向沢源頭トラバース |  |
 |
上中尾向沢源頭トラバース振り返り |
| 二瀬不動分岐で1350M水平道に出る |  |
 |
二瀬不動分岐から、1350M水平道を行く |
| 水平道と石津窪杣道の分岐の目印:東大演習林バス停 |  |
 |
水平道と石津窪杣道の分岐 |
| 水平道が新反射板の尾根を大きく回り込むと、和名倉山頂方面が見えてくる |  |
 |
水平道を振り返る |
| 水平道その先 |  |
 |
小屋跡の先の水場 |
| 水場近くのハシリドコロ |  |
 |
笹藪廊下 |
| 笹藪廊下 |  |
 |
笹藪廊下も、そろそろ終了 |
| 笹藪廊下上の1680Mコル |  |
 |
二瀬尾根唯一の展望台からの眺め |
| 笹ッ場に出る |  |
 |
笹ッ場振り返り |
| 北ノタル |  |
 |
北ノタル |
| 千代蔵ノ休場 |  |
 |
千代蔵ノ休場 |
| 和名倉山頂手前の荒地 |  |
 |
和名倉山頂 |
| 再び千代蔵ノ休場 |  |
 |
二瀬分岐北から金山沢中間尾根上部を下降して、川又道に出た |
| 金山沢中間尾根上部、川又道に合流 |  |
 |
川又道・曲沢下降点 |
| 川又道・曲沢下降点 |  |
 |
・1826肩 |
| ・1826肩 |  |
 |
1830M作業場跡 |
| ・1762P北付近 |  |
 |
・1762P北付近 |
| ・1762P北付近からは、笹藪がきれいに刈り払われている |  |
 |
・1173の尾根道 |
| ・1173の尾根道 |  |
 |
・1173の尾根道 |
| ・1173の尾根から離れ、北斜面を斜めに下って行く |  |
 |
川又吊橋を渡って川又バス停の駐車場に戻る |
 |
曲沢左俣右沢源頭1830M作業場跡 (前年4月撮影) |
![]()
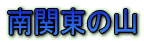 |