辺見岳「会所尾根」・「腰越尾根」下降(両神)
![]()
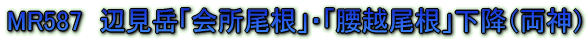
| date | 2007/5/20 晴 |
| コース | 日向大谷〜会所〜「会所尾根」〜辺見岳〜「腰越尾根」〜腰越ノ滝〜日向大谷 |
| 実働 | 登り:3h13m、下り:2h30m、計:5h43m。 |
| 概要 | 「会所尾根」は、1089独標先ギャップからルンゼ下降、絶壁岩峰の東面を下巻く。 |
| メンバー | ecosさん、すうじい |
| 使用装備 | 登山靴、アイスハンマー、ヘルメット、8mm x30mザイル、μ725SW、飲料2L |
| 不用装備 | |
| 行程 | →:山道・踏跡、→:藪漕ぎ・踏跡無し、車:=。 【5月20日】 晴 さいたま3:00=5:25小鹿野コンビニ5:35=6:00日向大谷下6:20→6:53会所7:10→7:40 880MP 7:50→8:15 1089P 8:25→尾根上9:20→9:30休9:45→10:05倉沢ノ頭10:10→10:30辺見岳北峰 11:05→倉沢ノ頭11:25→1130M岩峰西11:55→12:25 1010M肩12:35→900M肩12:50→13:15 725P 13:25→→13:40腰越ノ滝14:00→14:15日向大谷下14:20=西武秩父15:15=17:40さいたま |
| 記録 | GWに登った「腰越尾根」を下降に使い、辺見岳「会所尾根」にチャレンジしてきた。 【5月20日】 晴 心配された混雑も、GW時ほどではなく、6時に到着したら、第二駐車場に入ることが出来た。バス停横の第一駐車場には、団体客のバスが停まっていて、20人ほどの登山者が、準備体操をしていた。日向大谷の登山ポストに、計画書を投函する。この辺りから、本日の目標、辺見岳北峰・1280M倉沢ノ頭・下降予定の「腰越尾根」が望まれる。 日向大谷から、会所までの登山道では、登山者が連なっており、先程の団体さんを追い抜く。会所のベンチで、小休・準備していたら、その団体さんに囲まれる。 清滝沢・七滝沢出合へと下降し、本流を濡れずに渡る。本流清滝沢右岸の、「会所尾根」末端は、岩峰状になっているので、20mほど進んでから、斜上するバンド状泥付斜面に取り付く。さほど苦労せずに、尾根に乗ることが出来た。 「会所尾根」に乗ると、痩せ尾根ながら、快適な尾根歩きとなる。ほぼ真南に向かって尾根を辿れば、やがて尾根は広がり、どこが尾根筋だかハッキリしなくなる。下りでは、要注意である。会所から30分で、880MPに至る。 880Pからは、尾根は南西方向へと続く。概ね、快適な登りである。25分で、1089Pへと至る。密林の僅かな合間から、目指すピークが望まれる。1089Pでの小休を終え、コル状へ向け下り始める。密林のため、その先の尾根の様子は見えない。 コル状近くまで下ると、木々の合間から、突然、切れ落ちたギャップと、正面に聳え立つ、ブッシュ混じりのフェース状大岩壁が目に入る。葉の繁った木々に覆われてはいるが、我々の実力では、到底歯が立たない、見上げるような大岩壁。正面突破は、先ず無理である。地形図から判断すると、右手キワダ平ノ沢側から下巻くのは、無理そうだ。倉沢側もかなりの傾斜で、ルンゼが落ちている。 この岩壁を擁する岩峰を、果たして下巻くことが出来るか。兎に角、倉沢側のルンゼを、倉沢本流まで下降できれば、再び尾根に乗ることが出来るのは、薄川倉沢・辺見岳・三笠山'01-12の経験で判っている。尤も、このルンゼ、倉沢本流まで無事下降できる保証も無いのだが。 この大岩壁を下巻けなかったら、1089Pへと登り返して、会所へと引き返すことにしよう。意を決して、倉沢側ルンゼを下降する。1ピッチ目は、フリーで、崩れ易い急な泥付ルンゼを下降する。2ピッチ目は、立木を支点にして、ザイルを使用する。降り立ったルンゼは、少し傾斜が緩む。 更に下ると、ルンゼは急激に落ち込むようなので、右手(上流側)の岩稜に取り付く。ところが、その先は更に急峻なルンゼとなっており、トラバースが出来ない。やむなく、木の根頼りに岩稜を登り、一段登った所から、岩根に沿って、左上へと斜上を試みる。 更に、岩根に沿って落ち葉の積もったところを斜上して行くと、岩根に岩穴があったりする。次第に傾斜が緩み、疎林の斜面を登るようになる。上方に尾根が見えてくるが、落ち葉の積もった斜面は、滑り易くてシンドイ。尾根まで登ってみると、末端側は落葉樹の密林で、この藪尾根の先に、あの恐怖の大岩壁とギャップがあるとは想像出来ない。 さすがにもう、あんな難所は無いだろう。倉沢ノ頭を目指して、頑張ろう。最後に少し藪っぽい岩場となるが、正面やや左手を巻き気味に登る獣道を辿れば、たやすく1280M倉沢ノ頭の岩峰に立つ。岩峰には、檜の類が、しがみついて生えている。岩峰の檜の類の横から、聳え立つ辺見岳北峰を見上げる。2週間前には見られたアカヤシオや山桜は散り、黒木混じりの密林に覆われ、厳しい登りが待っている。 途中、二ヶ所の岩峰を、木の根頼りに右手から巻き気味に登り、倉沢ノ頭から20分の頑張りで、辺見岳北峰に立つ。両神主脈も、緑が大分濃くなったようだ。2週間ぶりの北峰では、アカヤシオの枝には、花が終わって、代わりに若葉が着いていた。ここで、30分以上の大休止をする。今回は、南峰往復を省略する。 さて、そろそろ下降開始だ。倉沢ノ頭まで、往路を戻るのだが、藪も濃く、二ヶ所の岩峰の巻き下りや、ルートファインディングが必要で、登りと同様20分を要する。 1280M倉沢ノ頭から、北東側へと痩せ尾根を下る。「腰越尾根」下降開始だ。1240M付近で、東側へ平坦な幅広尾根が派生するので、引き込まれないよう注意が必要だ。これを見送って、北東へと幅広の斜面状尾根を下降すると、見覚えある岩壁の1180M岩峰に突き当たる。前回は、この岩壁最後の2mを、飛び降りたのであった。ここをよじ登るのは、結構大変そうだ。 南東側斜面は、傾斜が緩いので、何とかこちらから下巻くことが出来そうだ。岩根を左に見ながら、南東側へと下降して行く。岩稜へは、取り付くのが難しそうだったが、岩根沿いに、1180岩峰東端へとトラバースすることが出来た。1180M岩峰は、やはり、こちらの岩根南東側を下巻くのが正解だ。前回の登りでは、岩根北側沿いに進み、北側のブッシュ混じりの岩場を強引に登ったのであった。 1180M岩峰東端から、尾根沿いを東進すれば、すぐに1130M岩峰に突き当たる。西面倉沢側は、断崖絶壁である。ここは、前回同様、南面の岩根に沿って、トラバースして行く。岩峰の挟間である、1130M岩峰東稜のギャップに乗り、さらに北東面岩根バンド状を、下り気味にトラバースする。 再び尾根に乗って、下って行くが、1050M付近で東へ派生する枝尾根に誘い込まれる。突然足元が切れ落ちて、ミスルートに気付く。幸い20m程の登り返しで、ロスは少なく済んだ。尾根に戻って少し下れば、樹林が切れて1010M肩に出る。ここには、風か雷に痛められたような大木が立っている。「腰越尾根」の数少ない展望台の一つだ。展望を楽しみながら、小休止しよう。 15分ほど下って行くと、900M肩に至る。なだらかな尾根を下り、810M付近の東へ向かう枝尾根に注意して、北東へと下ると、800M付近でフェース状岩場の上に出る。ここは、左右どちらからでも、簡単に巻き下れる。尾根が細く東西方向に延び、起伏が少なくなると、725独標となる。 さらに、尾根筋を忠実に下って行くと、最後は崩れ易い斜面となり、斜面を横切る林道跡に降り立つ。この林道跡を、右手の滝ノ沢側へと辿ると、下ノ滝横で滝ノ沢左岸杣道に出る。杣道を下って、滝ノ沢出合に降り立つ。 折角なので、薄川本流の腰越ノ滝を見に行こう。涼しげな滝の前で、荷を降ろして最後の休憩だ。充実した藪尾根周回を達成した、心地よい満足感に浸る。日向大谷まで登り返し、第二駐車場へと向かう。午後2時過ぎという、早い時間に、無事下山することが出来た。 |
![]()
ルート概念図
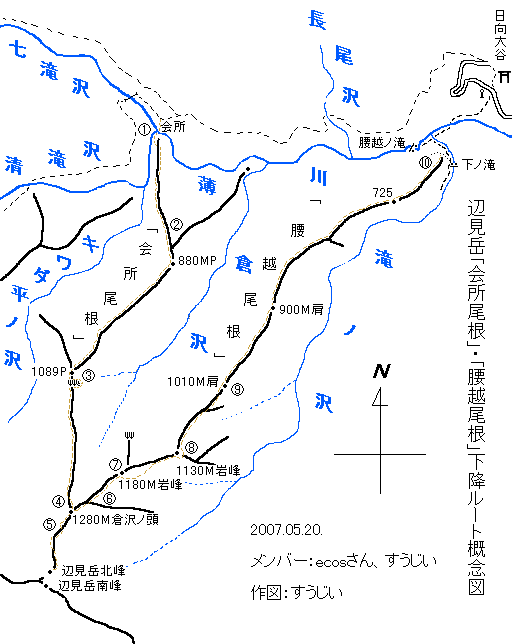
アルバム
 |
日向大谷から辺見岳と「腰越尾根」 |
| 会所の本流清滝沢・七滝沢出合 |  |
 |
「会所尾根」末端岩峰 |
| ・1089Pから、倉沢ノ頭と辺見岳北峰を見上げる |  |
 |
・1089Pの密林 |
| ギャップからキワダ平ノ沢側ルンゼ |  |
 |
ギャップから倉沢側ルンゼ |
| ギャップから大岩壁 |  |
 |
ザイルを垂らし、・1089先ギャップから倉沢側へ下降する |
| 大岩壁岩根沿いに斜上する |  |
 |
大岩壁下巻きを終えて、尾根上から北側を望む |
| 同じく南側に続く尾根 |  |
 |
1280M倉沢ノ頭から辺見岳北峰を望む |
| 辺見岳北峰から両神主脈 |  |
 |
辺見岳北峰から三芳岩方面 |
| 1280M倉沢ノ頭の藪岩峰 |  |
 |
1180M岩峰西端、右手滝ノ沢側から下巻く |
| 1180M岩峰東端、前回の登りでは右手倉沢側から岩根沿いに進んだ |  |
 |
1180M岩峰東端、今回は岩根の左手滝ノ沢側を巻いて来た |
| 1130M岩峰東稜ギャップから、北東面岩根バンド状を下る |  |
 |
1010M肩の特徴的な針葉樹 |
| 1010M肩から天理尾根を望む |  |
 |
800M付近のフェース状岩場、左右どちら側からでも簡単に巻ける |
| 尾根に忠実に下れば、下ノ滝から続く林道跡に出る |  |
 |
滝ノ沢下ノ滝からは、左岸沿いの杣道を下る |
| 薄川本流の腰越ノ滝、充実した藪尾根周回を終え、涼しげな場所で最後の一休み |  |
![]()
| 両神山の山行記録へ |
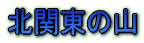 へ へ |