中津川石舟沢右俣・剣ヶ峰・梵天1383P西尾根下降(両神)
![]()
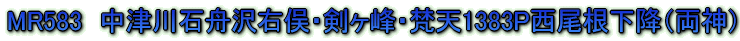
| date | 2007/3/18 晴 |
| コース | 長栄橋〜石舟〜石舟沢右俣左沢1300M付近〜右沢〜ヒゴノタオ〜剣ヶ峰〜梵天1383P西尾根〜トウタロウ沢出合〜長栄橋 |
| 実働 | 登り:4h40m、下り:6h、計:10h40m。 |
| 概要 | 右俣左沢敗退、1383P西尾根下降は手強い。 |
| メンバー | すうじい(単独) |
| 使用装備 | 登山靴、アイスハンマー、ヘルメット、8mm x30mザイル、ハーネス、8環 |
| 不用装備 | アイゼン、渓流足袋 |
| 行程 | →:山道・踏跡、**:アイゼン、→:溯行、→:藪漕ぎ・踏跡無し、車:=。 【3月18日】 晴 さいたま4:00=5:30影森コンビニ5:45=6:05道の駅大滝温泉6:15=6:40長栄橋7:05→石舟7:50→→1010M二俣8:10→1170M奥二俣8:50→左沢1300M付近引返点9:45→10:25 1170M奥二俣10:40→11:10ヒゴノタオ11:20→12:10剣ヶ峰12:20→12:50ヒゴノタオ13:00→13:12三芳岩13:13→14:00 1383P 14:10→1300M付近 14:45→16:25 1020M付近16:30→不正解小尾根引返点17:10→西尾根復帰17:35→トウタロウ沢出合18:15→18:45長栄橋18:50=19:55道の駅あしがくぼ20:25=21:50さいたま |
| 記録 | 以前から気になっていた、石舟沢右俣左沢。取り敢えずチャレンジしてみたが、やはり手強く、1300M付近で引き返し、右沢からヒゴノタオへとエスケープ。また、梵天尾根大峠の南にある1383Pから、西へ派生する尾根を、ecosさんの情報を元に、下りに使ってみた。これが、結構な曲者で、結論から言えば、一度登りを経験してから、下るべきだったと思う。 【3月18日】 晴 中津川沿いの道は、新しくなっており、快適だった。持桶トンネルを抜けて、橋を渡った所で、旧道を戻り、長栄橋に車を停める。先客1台は、仕事か釣りか。 石舟沢右岸の尾根に付けられた道を少し登ると、山ノ神の祠があり、そこからトラバースが始まる。以前は、朽ちかけた桟道など、怪しい道だったが、伐採作業のお陰か、かなり手入れされている。それでも、崩れかかった場所もあり、注意は必要だ。 トウタロウ沢出合に近付くと、伐採地となり、明るく開ける。トウタロウ沢を左に見送り、石舟沢沿いの道を進む。すぐ先に、左岸側に踏跡を見る。これが、1383P西尾根末端の作業道入口のようだ。石舟沢右岸沿いも、かなり伐採されている。 石舟沢右岸の踏跡を辿ると、川床から伐採地を登り、一段高いところをトラバースする。やがて、左岸に、石灰岩の空滝15m(別名ホトノ滝)を懸ける峠沢出合に至る。踏跡は、一旦石舟に近付くが、右岸側のガレを登って、石舟鍾乳洞入口付近を高巻いている。上方を見遣れば、獣が一匹、こちらを見下ろしている。どうやら、カモシカのようだ。 今回は、峠沢を見送って、この踏跡を辿り、石舟を右岸から高巻くことにする。巻きの途中から、石舟核心部を見れば、倒木が詰まっている。石舟上流の右岸枝沢出合手前で、石舟を俯瞰する。前回、苦労して通過した石舟も、あっけなく高巻くことが出来た。 石舟上流の右岸枝沢を渡り、少し右岸の植林帯沿いに進むと、踏跡は姿を消す。殆ど水の涸れた石舟沢を溯行すれば、20分ほどで、1010M二俣に至る。 右俣出合には、見覚えのある、2段5m滝下ナメが懸かる。この滝は、凍ってはいない。いつかは、左俣を溯行して、狩倉槍へと突き上げてみたい。今回は、見送って、右俣へと入ることにする。前回取り付いた右俣出合の2段5m滝下ナメは、中間尾根に取り付いて簡単に巻く。 1010M二俣から40分ほどで、1170M奥二俣に至る。今回は、左沢を登ってみよう。歩きにくい涸れゴーロを、更に進む。少し登ると、4m滝が現れる。左手から取り付いてはみたが、薄氷が張り、登り辛そうなので、断念する。左岸の枯葉の積もった急斜面から巻くが、悪い。木の根を頼りに、何とか越える。 沢の傾斜が増してきて、ゴーロは次第にナメ滝連続となり、枯葉のかぶった凍結ナメ滝が多くなる。このナメ滝を右岸側の泥斜面から巻いているうちに、「これでは、いくら時間があっても、ツメ上げることは無理だなぁ」という気持ちになる。 9:45、敗退決定。1300M付近であろうか、立木を支点にして、懸垂2回で沢床に戻る。先程の4m滝は、立木利用で、懸垂1回。尻尾を巻いて、1170M奥二俣に戻った。やれやれ、小休して態勢を立て直そう。右沢を登って、ヒゴノタオへと抜けることにする。 右沢は、はじめ巨岩ゴーロだが、すぐに水が涸れる。左岸側ガレ斜面をトラバース気味に辿る方が、効率が良い。1230M付近で、左手に横八丁の1683P方面への直登沢を分ける。この辺りでは、右手に、三芳岩西端岩峰が、威圧的に聳える。正面のヒゴノタオを目指し、黙々と登る。 やがて、ヒゴノタオの鞍部が見えてくる。最後は、左手の小尾根に乗ってしまった方が、幾分楽なようだ。脚を踏ん張って、幅広小尾根をゆっくりと登って行く。 ヒゴノタオは、ホッとする穏やかな鞍部である。だがこの日は、冷たい西風が吹き荒れていた。東面へと少し下って、風を避ける。パンを頬張り、水分を補給する。まだ11時過ぎなので、少し欲が出る。荷物をデポして、剣ヶ峰を往復して来よう。上着を脱いだまま、長袖シャツ1枚で出発したのは、失敗だった。 ヒゴノタオから大笹までは、高度差約280M程の登りである。登りだから汗をかくかな、との予想に反し、冷たい西風は容赦無く吹き付け、凍えそうな寒さであった。大笹から剣ヶ峰までは、さほど高低差の無い縦走となる。山頂には、単独男性が二人いた。八ヶ岳の展望が良い。浅間は、少し雲が懸かる。 休憩もそこそこに、引き返そう。ヒゴノタオまで、30分で下り着く。荷を背負うと、登りの足取りは重くなる。三芳岩は展望良好だが、露岩の風は、ちと怖い。大峠までの高度差130Mの下りも、脚に来ている場合、要注意だ。大峠一つ手前のコルから、峠沢へ下降ルートを目で確認する。 大峠から1383Pへの踏跡は、更に薄くなる。落ち葉で滑り易い道は、西側を巻き気味に取り付いている。やがて右下に平坦地を見下ろし、東側を巻いて梵天ノ頭方面へと続く踏跡から離れ、1383Pに立つ。木々の合間から、三芳岩や大笹・横八丁を振り返り、石舟・トウタロウ沢出合付近の伐採地を見下ろす。腕時計の高度を合わせ、地図とコンパスを再度スタンバイして、いざ下降開始だ。 浮き石の多い痩せ尾根を、慎重に下り、先ずは、顕著な1325M藪岩峰を目指す。はじめのうち、慎重過ぎて、やたら時間を浪費する。1325M藪岩峰から、西北西方向に30-40M下り、尾根を右へ1本見送って、西南西への急降下に移るのだが、ここが最大の難所。なるべく尾根に忠実に、立木利用の懸垂下降。古い地形図では、この辺りから、登山道を示す破線が峠沢へと下っている。更に、痩せた小尾根をもう1本右に見送り、1240MPの尾根に乗る。 1200Mで右手に枝尾根を見送り、1150Mの尾根分岐でも右手の尾根が不正解であることを確認して、左手の尾根へと移れば、岩根沿いに下って尾根に乗る。やがて傾斜の緩くなったザレ尾根を下って行く。 1000M付近まで下ると、右手に下れそうな枝尾根が何本も現れる。対岸に見える石舟沢右岸伐採地につられて、下って行ったら、最後の最後に、断崖の上に出てしまった。2本ほど左手に、針葉樹の尾根が見え、「そうか、植林帯の尾根なら、作業道か踏跡がある筈だから、安全に下れるに違いない」と思い付く。 17:10と、かなり遅い時間だが、断崖を強引に懸垂下降するのは、あまり得策ではない。結局、もう一度登り返すことにした。この不安定なガレ尾根の登り返しが、一番辛かった。幸い25分ほどで、再び西尾根上に乗ることが出来、杉林が始まるまで、西尾根を忠実に辿る。 最初に現れた、薄暗い杉林の小尾根を下降する。下るにつれ、足元は不安定なガレガレ斜面となるが、一本一本の杉の幹に掴まりながら、慎重かつ強引に下降する。落石を頻繁に引き起こしながら、何とか石舟沢本流左岸に辿り着く。 本流を徒渉し、倒木のジャングルジムを登って、トウタロウ沢出合の作業道に至る頃には、既に暗くなってしまった。ヘッドランプを出す暇も惜しく、石舟沢右岸作業道を急ぐ。踏跡を見失った地点で、止む無くヘッドランプを出す。長栄橋の車に戻ったのは、18:45であった。 |
![]()
溯行概念図
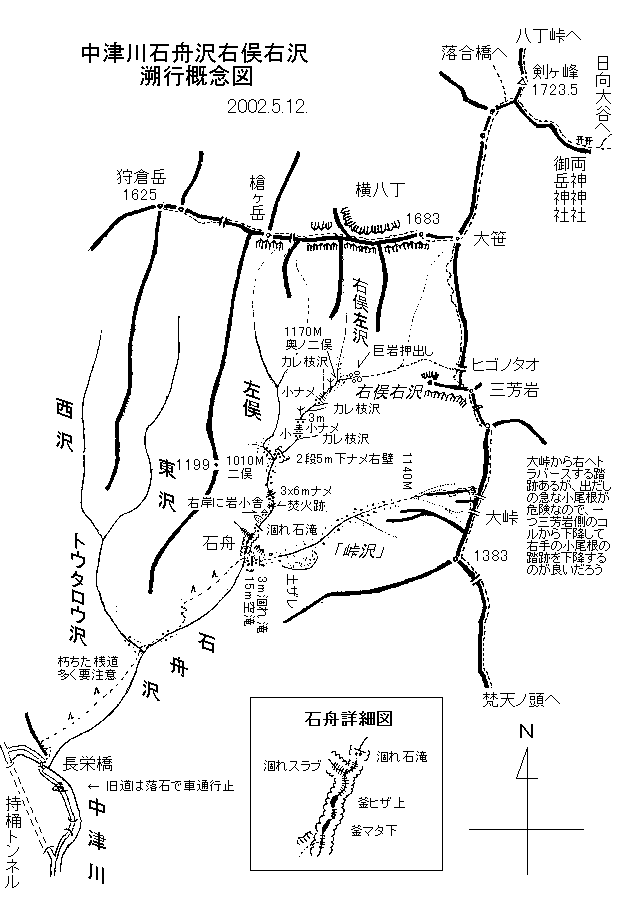
アルバム
 |
長栄橋の登山口 |
| トウタロウ沢出合の伐採地 |  |
 |
石舟入口 |
| 流倒木の詰まった石舟核心部を右岸から巻く |  |
 |
同じく俯瞰する |
| 石舟沢1010M二俣 右俣2段5m下ナメ |  |
 |
石舟沢右俣1170M奥二俣 左沢に入る |
| 薄氷の張った右俣左沢4m滝 |  |
 |
右俣左沢1300M付近のナメ滝、右岸高巻途中で敗退決定 |
| 右俣右沢1230M付近から、1683P南面直登沢方面 |  |
 |
右俣右沢1230M付近から、三芳岩西端岩峰を見上げる |
| ヒゴノタオへの最後の登り |  |
 |
ヒゴノタオ |
| 大笹から1683P方面 |  |
 |
剣ヶ峰から、赤岩尾根・御座山・八ヶ岳方面 |
| 剣ヶ峰から、狩倉岳方面 |  |
 |
三芳岩にて |
| 大峠から、西側の峠沢を俯瞰 |  |
 |
大峠のベンチ |
| ・1383Pより、三芳岩・大笹方面を望む |  |
 |
・1383Pから、これから下る西尾根 |
![]()
| 両神山の山行記録へ |
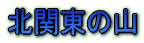 へ へ |