石津窪左岸道・二瀬尾根から和名倉山(奥秩父)
![]()
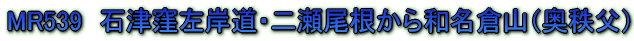
| date | 2005/6/12 晴のち曇 |
| コース | 大洞林道分岐〜下段道小屋掛〜中段道〜石津窪左岸道〜1350M軌道跡上段道〜二瀬尾根〜和名倉山〜二瀬尾根〜1350M軌道跡上段道〜和名倉沢1380M右岸枝沢出合〜1350M軌道跡上段道〜索道残骸尾根下降点〜二重山稜〜中段道〜下段道小屋掛〜大洞林道分岐 |
| 実働 | 登り:4h45m、偵察往復:1h45m、下り:3h10m、計:9h40m。 |
| 概要 | 中段道・石津窪左岸道・1350M軌道跡上段道踏査を兼ねて、和名倉山頂往復。 |
| メンバー | すうじい(単独) |
| 行程 | →:山道・踏跡、→:溯行、→:藪漕ぎ・不明瞭な踏跡、=:車 【6月12日】 晴のち曇 さいたま3:05=5:35大洞林道分岐6:00→6:35下段道小屋掛6:40→→中段道分岐6:50→中段道石津窪左岸道分岐7:14→石津窪小屋跡水場7:30→→8:25上段道・石津窪左岸道下降点8:35→9:05上段道小屋跡水場9:10→→9:55 1680Mコル10:05→1780M展望台10:23→1800M索道広場10:26→10:45笹ッ場10:50→11:20和名倉山11:25→笹ッ場11:50→12:05 1800M索道広場12:15→1680Mコル12:26→→12:50水場13:00→→14:00和名倉沢1380M右岸枝沢出合14:10→→14:55水場15:00→上段道・索道残骸尾根下降点15:13→中段道索道残骸尾根二重山稜15:30→中段道・山ノ神尾根15:40→15:57中段道・石津窪左岸道分岐16:07→下段道小屋掛16:27→16:38和名倉沢木橋16:48→17:15大洞道路分岐17:45=20:37さいたま |
| 使用装備 | 渓流シューズ「水無」、ステッキ、E-1、14-54mmF2.8-3.5、 |
| 不用装備 | ヘルメット、フェルトソール、三脚、 |
| 記録 | 昨年4月、大洞和名倉沢左岸踏跡調査・大滝見物では、和名倉沢左岸下段道から登る踏跡調査、「通らず」・大滝撮影目的で出掛けた。その後、昨年5月の大洞和名倉沢中・上流部の日帰り溯行へと繋がったわけである。今回、鳶八さんから「1350M軌道跡が和名倉沢まで続いている」との情報を得て、その調査を兼ねて、中段道・石津窪左岸道経由で和名倉山を往復した。 【6月12日】 晴のち曇 車は、大洞林道・三峰道路分岐に停める。和名倉沢下降点から、下降尾根を辿り、大洞本流に懸かる吊橋を渡る。さらに和名倉沢右岸の山道を辿ると、木橋で左岸へと渡る。 杉林の中の道を登って行くと、やがて小屋掛に至る。ここで道は二つに分かれる。左へ続くのは、800M付近をトラバースしている下段の道だ。今回は、右上方へと続く道を辿る。顕著な東へと続く尾根の手前で、広場状の場所がある。 ここから、尾根の南面を適当に登るが、次第に傾斜がきつくなり、足場が不安定となる。困ったな、と思っていたら、右手の尾根からトラバースしてくる踏跡がある。ラッキー、とばかりに、これを辿って、トラバースを開始する。これが、中段の道だ。 中段の道を、ひたすら辿って行くと、石津窪手前で、明瞭な分岐がある。そのまま水平からやや下り気味の道と、登って行く道だ。右の登って行く道を選ぶ。この道は、石津窪に近付いて、小屋跡と水場のあたりで、不明瞭になる。 基本的には石津窪左岸側に踏跡がついているので、あまり沢に寄りすぎない方が判り易いようだ。最後は、ジグザグになり、1350軌道跡の上段トラバース道に出る。 1350M軌道跡の上段トラバース道を、歩く。山ノ神尾根、索道残骸尾根の下降点には、目印がある。やがて、小屋跡まで至り、水場近くから、更に南へと軌道跡が続いているのを確認する。その先は、帰りに、偵察しよう。 水場のホースを調整して、水が出るようにしておこう。なにせ、ここからズルズルの急登が始まり、笹藪廊下へと突入することになる。オマケに、今日のこの蒸し暑さ。和名倉山を往復して来たら、喉がカラカラになっているに違いない。 気合を入れ直し、ゆっくりと登り始める。苔生したゴーロ状を登り、やがてズルズルの急登になる。次第に笹藪となって、いつの間にか笹藪の廊下が始まる。傾斜の緩急はあるが、永遠に続くのでは・・・と錯覚させられる場所である。 それでも、水場から45分で、笹藪廊下上の1680Mコルに至る。小休止しよう。ここから、顕著な尾根上の道となり、20分ほどで、1780M展望台(展望の得られない二瀬尾根コースでは、1330M反射板と並んで、貴重な展望台だ)に至り、さらに僅かな登りで、1800M索道広場に出る。 索道広場からは、道は尾根の南面をトラバースして行く。20分で、笹ッ場の草地に出る。少し休憩して、1955Mコルである、北のタルの針葉樹林帯に入る。熊鈴を鳴らしながら、単独男性が擦れ違う。ここは、苔生した幽玄の世界だ。 20分ほど歩けば、二瀬分岐に至り、間もなく、千代蔵ノ休場の草地に出る。今日は、雲が出て、残念ながら富士山は見えなかった。緩やかに登る踏跡を辿り、やがて密林の中の和名倉山頂に至る。 誰もいない山頂を辞して、1800M索道広場まで40分。そこからさらに、水場まで35分だ。先程調整して置いたホースから、水が流れている。しっかり水分を補給した後、1350M軌道跡の上段トラバース道を、南下して、和名倉沢へと調査することにする。 細い踏跡を辿ると、すぐに軌道跡の幅広道形が復活する。ただ、そこそこ笹が繁っているため、藪漕ぎしながらのトラバースを強いられ、結構歩きにくい。10分ほど歩くと、傾斜の緩い浅い谷地形に至り、一旦道形が不明瞭になる。しかし、そのまま水平に進むと、更に軌道跡が続いている。 急斜面や沢状地形では、道形が崩壊して、判りにくくなっている場所もあるが、その後もほぼ水平を保ちつつ、踏跡を辿ることが出来る。1時間ほどの藪漕ぎトラバースで、最後の顕著な小尾根に乗り、眼下に和名倉沢と滝が見えてきた。 この小尾根を越えて、トラバース気味に沢へと下降すると、1380Mの15m滝を懸ける(1:2)右岸枝沢出合に出た。つまり、1350M軌道跡上段トラバース道は、二瀬尾根の1330M反射板から、水場の小屋跡を経て、和名倉沢1380M右岸枝沢出合まで、続いていることになる。 赤ガムテープの最後の断片を、目印の木に巻き付け、往路を引き返そう。顕著な小尾根までは、踏跡が薄いため、ルートファインディングに少し緊張する。水平踏跡に出ると、あとはスピードが上がる。尤も、水場までの帰りも、45分掛かってしまった。 水場で、またのどを潤し、小屋跡の残骸を踏み越えて、上段トラバース道を辿る。13分で索道残骸尾根下降点に至り、一昨年のテープの目印から、笹藪の中の踏跡を下降する。索道残骸からは踏跡不明となるが、急な尾根沿いを適当に下降し、上段道から17分で、二重山稜に出る。 二重山稜から、中段トラバース道は、さらに南へと続いており、σ(^_^)の想像では、大滝上の顕著な小尾根上の踏跡へと繋がっているような気がする。こちらも、一度踏査しておきたい。今回も、中段トラバース道を辿って、北へと向かう。 二重山稜から10分で、いつもの山ノ神尾根に至るが、今回は、尾根沿いには下降せず、中段道を忠実に辿ることにする。山ノ神尾根の支稜沿いに、少し下ってから、再びトラバースを開始する。更に10分ほどで、水の涸れた石津窪を横断し、更に5分で、石津窪左岸道分岐に至る。 今朝方の分岐に、到達したわけだ。中段道を、更に忠実に辿ると、12分で、1052Pの尾根(石津窪左岸尾根)に乗る。道形は、更に尾根沿いを5分下り、平坦地形近くで分岐があり、平坦地形を経由して、小屋掛まで更に5分。 小屋掛で、下段道と合流し、杉林の中を、和名倉沢の木橋へと下降すること10分。冷たい和名倉沢の水で、火照った顔を洗う。大洞本流の吊橋を渡り、最後の登り返しに汗をかき、やっとのことで、大洞林道・三峰道路分岐に駐車した車に戻る。 |
![]()
概念図
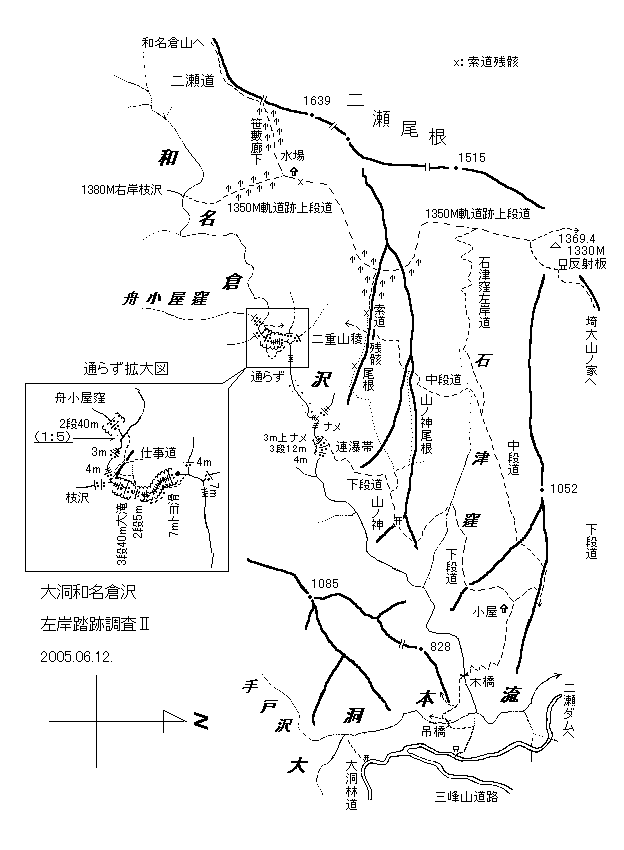
アルバム
 |
1960M笹ッ場 |
| 北ノタルの苔生す樹林帯 |  |
 |
北ノタルの苔生す樹林帯 |
| 千代蔵ノ休場 |  |
 |
千代蔵ノ休場から、カバアノ頭・飛竜山 |
| 密林の中の和名倉山頂 |  |
![]()
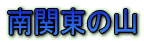 |