クワウンナイ川・化雲岳(大雪)
![]()
![]()
| date | 1995/9/8-13 |
| コース | 天人峡〜クワウンナイ川〜天沼南コル〜ヒサゴ沼〜化雲岳〜小化雲岳〜天人峡 |
| 実働 | 第1日6h25m、第2日4h30m、第3日8h40m、第4、5日停滞、第6日8h00m、計27h35m |
| メンバー | すうじい、I君 |
| 概要 | 沢89、天人峡基点、クワウンナイ川を溯行、悪天下ヒサゴ沼避難小屋で二日停滞。 |
| 行程 | 【9月8日】 曇のち雨 小樽=天人峡七福岩駐車場8:20→8:55ポンクワウンナイ川出合9:15→10:00 618M右岸枝沢10:15→12:25 670M右岸枝沢12:45→15:30 783M左岸枝沢(BP) 【9月9日】 曇 783M左岸枝沢→小滝幅広10:20→876M右岸枝沢11:45→13:30化雲の沢出合(BP) 【9月10日】 晴のち曇のち雨 化雲の沢出合7:00→8:00魚止滝下8:20→8:55 1170M左岸枝沢9:10→9:45 15x30m出口滝上9:55→11:00 1355M二俣11:15→13:35 1650Mカール状底14:10→15:25天沼南コル15:30→17:20ヒサゴ沼避難小屋(泊) 【9月11日】 風雨のち曇 ヒサゴ沼避難小屋(停滞泊) 【9月12日】 暴風雨 ヒサゴ沼避難小屋(停滞泊) 【9月13日】 快晴 ヒサゴ沼避難小屋6:10→7:35化雲岳8:15→10:00小化雲岳10:30→14:30滝見台14:55→15:45天人峡七福岩駐車場 |
| 記録 | 85、90年に続き、3度目5年ぶりのクワウンナイ川溯行は、やはり良かった。 やや水量が多いためか、ポンクワウンナイ川出合から魚止滝までずっと、徒渉が手強くて苦労した。撮影装備の重さも、難易度を増加させたと思われる。初日からの雨、増水と重荷、稜線に抜けてからの前線通過と、いろいろ悪条件が伴い、焚火があまりできず、釣りのポイントが少なく、ナキウサギの観察や撮影ができず、旭岳方面への縦走を断念した。 だが、幸運もあったと思われる。苦労しつつも、沢の中でのビバークは、予定通りの位置で安全なサイトを得ることができたし、ちゃっかりオショロコマも釣った。核心部の滝の瀬十三丁は、晴天の下、快適に溯れた。源頭では、草紅葉とナキウサギの声を十分に堪能した。本降りになる前に、なんとか避難小屋に辿り着いたし、丸2日の停滞で、快晴の空の下、紅葉の山々を眺めつつ、無事に下山できたのであった。 【9月8日】 曇のち雨 フェリーから小樽に上陸すれば、なんと大雨が降っている。話が違うじゃないか、とブツブツ言いながら、札樽道を飛ばす。道央道に入る頃には、小降りになったものの、先行き不安は隠せない。終点の旭川鷹栖ICから、天人峡へ向かう。七福岩の無料駐車場には、トイレは無いが、公衆電話はある。ここで身支度を整え、車を置いて出発する。 例によって、林道に張られた立入禁止(「クワウンナイ川は遭難救助が困難なため立ち入りを禁止します」と書いてある)のロープをまたいで進むと、すぐに崖崩れのため林道は崩壊している。これを下巻くが、結構難儀する。先が思いやられるぜ。再び復活した林道を進み、・586ポンクワウンナイ川出合へと下降する。丸太を利用して、これを渡る。ここでフェルト足袋に履き替える。泥の上に、鹿かカモシカらしい足跡が見られた。 右岸のブル道跡を進むが、すぐに終わって、1回目の徒渉となる。膝上から腿くらいの深さで、流れも速く、水温も低くて、いきなり手強い。I君は、かなりビビッているようだ。数日来の降雨のため、増水しているらしい。すうじい過去2度の溯行では、徒渉に手こずった記憶はない。なるべく徒渉の回数を減らすよう努めるが、やはり無しでは済まされず、その度に体力を消耗する。 ・618右岸枝沢水流二分の出合で、小休する。この上に小函があるが、通過は困難ではない。奥に滝の見える640M右岸枝沢を過ぎ、本流が水流二分してから、扇状地状の・650右岸枝沢を見送り、660M右岸枝沢の辺りで、水流は一つになる。 12時25分、670M右岸枝沢出合の大石河原で、大タルミする。左前方に岩峰が聳えている。前回90年の時は、ポンクワウンナイ川出合からここまで1時間20分で辿り着いて、ビバークしたのであった。ここでやっと、今日の溯行予定の半分である。 まだまだ先は長い。ゴーロ歩きと藪漕ぎと徒渉を繰り返すうち、雨が本降りになって、休憩もままならなくなってきた。泣きべそをかきながら、先を急ぐ。I君は徒渉するうちに足がつり、更に辛そうだ。終いには、雷を伴う土砂降りとなった。 15時半、やっとのことで・783左岸枝沢出合に至り、ビバークサイトを探す。出合の少し上流の左岸に、5張分くらいの快適そうなプラッツを見つける。雨の中での設営は辛い。それでも、サイトの前の巨岩の間の流れの淀みで、オショロコマを釣り上げた。焚火は諦め、岩魚汁にする。大分くたびれたゴアのツェルトでは、本格的な雨に濡れは免れない。 【9月9日】 曇 朝、雨は上がっているが、いろんなものが濡れていて、撤収は辛い。I君が重荷に潰されそうなので、食糧もすうじいが担ぐことにする。サイトの前の右岸は、ガレて赤っぽい土が露出した壁となっている。昨日の疲れから、出発は9時となる。 水量は相変わらず多く、ゴーロの行程ははかどらない。1時間強で、小滝幅広に至る。更に1時間強で、・876右岸枝沢。ここから左岸の踏跡を辿ると、10分ほどで、林の中の1張分のプラッツに至る。ちょうど右岸に枝沢が滝を懸ける。踏跡を更に辿ると、流れから離れて登って行き、小尾根を越える形で流れに戻る。少し先の910M付近の川原で小休し、行動食を頬張る。 ここから1時間半で、化雲の沢出合下の左岸巨岩押し出しに至るまで、前回の黒テンを見たビバークサイトを、探しながら進んだが、繰り返す大増水のためか、川の様子はすっかり変わってしまっていて、全然判らなかった。 この巨岩押し出しで、前方に見覚えのある化雲の沢出合を見て、釣竿を出し、キジ餌をつけてI君に渡す。流れから外れた、巨岩の合間の小池状に、無造作に糸を垂れたI君は、あっと言う間にオショロコマを釣り上げた。 すぐ先の、出合下左岸の川原に設営する。左岸の林の中の踏跡を辿ると、3〜4張分のプラッツがある。薪集めをI君に任せ、すうじいは一人化雲の沢へ偵察に行く。出合付近の化雲の沢は石滝連続である。 サイトに戻り、焚火おこしと炊事だ。薪が湿気ているので、焚火も意外と苦労する。水の冷たさに、米を研ぐ手が痛い。食前酒の梅酒を味わい、ディナーを始める。飯盒で炊いた飯は、やはりうまい。ふりかけも好評だ。 【9月10日】 晴のち曇のち雨 やっと晴れたぜ。今日は、核心部の滝の瀬十三丁を溯り、稜線に抜ける大事な日なので、7時にサイトをあとにする。 巨岩ゴーロに苦労しつつも、1時間で入口の魚止滝下に至る。増水が心配なので、空身で滝上を偵察したところ、よかった行けそうである。滝の左岸巻道取り付きに、2張分のプラッツがあるが、今日は濡れていて不快そうだ。 いよいよ魚止滝を越え、滝の瀬十三丁が始まる。I君の嫌いなゴーロから解放され、一枚岩盤の滑床の上をヒタヒタ歩く。10mスダレを右岸から小さく巻き、5分も歩けば、ナメ歩きの要領を思い出す。これまでの行程が、増水により難易度アップしていたことを思えば、この心配された核心部の快適さは夢のようである。見上げれば青空、両岸の高みには紅葉、足下には美しい流れ。心地よさと安心感が広がり、ビデオカメラを首から下げての溯行となる。 30分ほどで、中間点の1170M左岸枝沢出合両門の滝に至り、滝上で小休止。ああ、まさに秋の溯行日和だ。再び滑床歩きを続ける。流れの中に、丈の低い藻だか苔だかのクッションを踏みつつ、快適に溯れば、やがて出口の15x30m幅広に至る。これは水線右を直登する。この上は平凡なゴーロになってしまい、美味しかった滝の瀬十三丁は、実働1時間10分で、終了する。 ここで小休して行動食を頬張る。15分ほど行くと、10mOHの下に出る。右岸の巻道を急登すると、岩壁に突き当たる。固定ロープを頼りに登攀し、荷を置いてクライムダウンし、I君の荷を担ぎ上げる。空身のI君も登攀し、無事高巻きを終えて滝上に下降する。下降点近くに、1張分のプラッツがあった。 1355M二俣でタルんだ後、中間尾根の巻道を辿って、出合の10m、20mの二段の滝を高巻く。前回左岸の踏跡につられて、ずいぶんと登って引き返したことを思い出す。早めに沢に戻り、やや貧弱になった流れを行くが、流れに沈んだゴーロは歩きにくい。 1時間ほど歩いて、重荷に負け、小さな川原にへたりこむ。そろそろ稜線近くの美しい紅葉が見えてきた。さらに5分歩くと、1460M付近で6mスダレを右岸から巻く。ここから階段状の小滝連続となり、ぐいぐい高度を上げる。右岸に踏跡が始まり、これを辿る。1550M付近で1張分の源頭のサイトが現れる。これで一安心、小休する。更にもう少し頑張って、カール状底の1650M付近に至ったのは、13時35分であった。 ここはまさに別天地。1張分のプラッツ、小さな流れ、草紅葉、周りの岩々の間からは、懐かしいナキウサギの鳴き声。ここでの幕営は、さぞや楽しかろう。兎に角、フェルト足袋を脱いで裸足になる。気持ちいい。麦茶を飲み干し、行動食を摂る。念のため水を700mlほど担ぐ。軽登山靴に履き替え、山と積まれた捨て草鞋を横目に出発する。 動物たちを脅かさぬよう、熊鈴は外して行くことにする。始め平坦だった踏跡はやがて岩々を攀じ登るが、時折ナキウサギが警戒音を発し、目を凝らすも姿は見えない。すうじいは一度だけ目の前を横切る姿を見たが、無論、撮影する暇などなかった。 そのうち道は窪状から右手に登り始め、肩状に至る。重荷が肩に食い込んで、もうハテハテである。ここで今回初めて縦走路を行くヒトの声と姿を経験する。踏跡は少し下って、この季節でも残る雪田を経て、左手に沼を見下ろしながら、1830M天沼南コルへとトラバースしてゆくのである。15時25分、やっとのことで縦走路に出た。 トムラウシのピストンは、さすがに考えなかった。縦走路に出たと言っても、さほど楽になったわけではないのだ。相変わらずの重荷だし、道はI君の嫌いな岩々続きだし、もう8時間以上行動し、850m程高度を稼いだ後だし、肩の痛みと喰いバテで、「もうフラフラ勘弁して」状態であった。何か糸がプッツン切れてしまったかのようだ。本来なら、天沼を始め、日本庭園の美しいところのはずだが、それを観賞する余裕もなく、ヨタヨタとヒサゴのコルを目指す。 やがて右下に、ヒサゴ沼が見えてきた。コルの北西側の化雲の沢源頭方面には、雪田を伴う沼があり、踏跡も続いている。化雲の沢を溯行するパーティも結構あるということか。コルからの下りは、再び岩々だ。Iのペースが落ちる。ガスが次第に濃くなり、小さな雪渓を経て、ヒサゴ沼畔に至る頃には、小雨が降り出した。17時20分、やっと避難小屋に辿り着く。 小屋には既に10人ほど先客がいたが、幸い入口近くに空きがあったので、ここを占有する。水場を尋ねると、先程の小雪渓下の流れがそうだという。あちゃー、来るとき汲んでくりゃよかったなあ。すうじい雨具に身を固め、薄暗い中、飯盒とペットボトルと熊鈴を持って出撃。疲れているはずなのに、怖いよー、冷たいよー、というわけでぴゅーと行って帰ってくる。 先ずは熱いカフェカプチーノを飲んで、それから飯炊きだ。他のパーティよりかなり遅れての夕食だが、今夜のメインは牛丼だ。味噌漬の魚は、そのまま岩魚汁になる。勿論、梅酒は欠かせない。2階のオジサン連中は、結構遅くまで賑やかだった。今夜はぐっすり眠れそう。 【9月11日】 風雨のち曇 一応4時にアラームをかけたが、雨音がしているのでまた寝る。昨日の疲れがたっぷり体に残っているので、全く起きる気がしない。他のパーティがそろそろ出発し始めた頃、とりあえず、朝食のネコマンマを作って食べる。8時半頃、2階のオジサン連中が下山してしまうと、小屋にはグルメのアンチャンと我々のみになる。 天気予報では、朝のうちに気圧の谷が通過し、午後には晴れ間も見えるというのだが、明日はまた強力な低気圧と寒冷前線が通過するらしい。もう、旭岳方面への縦走は断念しているが、今日下山するか、停滞するかだ。停滞の場合、おそらくあと2泊せねばならず日程ギリギリとなる。教科書的には、即下山のところだが、I君の体力と足のむくみが心配だし、すうじいも疲れているので、兎に角今日は停滞とする。 停滞と決まれば寝貯めだ。時々ラジオを聴いたり、お茶を飲んだりする他は、ひたすら寝る。午後に一瞬日が射したが、あとは降ったり止んだりだ。本降りになる前に、水汲みに行く。 3時頃、単独のアンチャンが到着する。グルメアンチャンと「やあ」と声を交わしている。一昨日この小屋に泊まったあと、昨日はトムラウシ山を越え、三川台まで行ったが、天候が悪化しそうなので引き返してきたとのこと。夕食はお待ちかねのカレーだ。激辛で美味しい。となりのグルメは、何やらうまそうなものを調理している。早めに寝る。 【9月12日】 暴風雨 覚悟はしていたが、猛烈な吹き降りだ。鉄骨入りの頑丈な小屋にも、バラバラいう雨音とビュービューの風の音が響き、風上側の壁からは雨漏りしている。壁際にいた出戻りの彼は、グルメの隣に移動する。 我々は、1泊目で焚火ができなかったため、燃料のブタンガスの残量が少なめで、行動食を温存し、お茶もケチる。おなかが空かないよう、寝てばかりいる。他の2人は、食糧、燃料共に豊富で、羨ましい限りだ。ガス欠になったら、即、乞食をしようと密かに決意するすうじいであった。10時頃になると我慢できず、遅い朝食のネコマンマを作る。みんな寝袋から出ずに、ウダウダしている。トイレは小屋の外にあるので、我慢しがちになる。 午後になって、北大低温研の2人がこの悪天をついて到着。雪渓の調査をしているらしい。今日の水汲みは、この雨のお陰で、小屋のすぐ近くで流水が得られた。今夜は冷えそうなので、ツェルトを広げて掛ける。最後の夕食は中華丼だ。天気予報は、前線が通過したので次第に回復する、と告げている。明日に期待して、早めに寝る。 【9月13日】 快晴 夜明けにトイレに出ると、スカ天だ。紺色の空に、ニペソツの印象的なシルエットが浮かぶ。さあ、急に元気になったぞ。さくさく朝食を済ませると、急ぎパッキングして、6時10分出発。 4度目の快晴のトムラウシ山頂は諦めて、化雲岳を目指す。途中振り返れば、ヒサゴ沼の畔の、朝日に照り輝く紅葉の中に、我々を3泊させてくれた避難小屋が、可愛らしく建っている。泥んこで滑りやすい道をなおも登ってゆくと、やがてハイマツの緑と、ウラシマツツジ、チングルマの草紅葉が交互に帯状になったところを登る。 化雲のヘソの傍らに立てば、うっすら初冠雪の旭岳から白雲岳の稜線が、まず目に飛び込んでくる。その裾野の、忠別川源頭の紅葉も美しい。東へ目をやれば、五色ヶ原から沼ノ原、石狩連峰、ニペソツ山。南にはトムラウシ山、クワウンナイ川源頭、十勝連峰。昨年のニペソツでも、紅葉がベストの時期だったが、今回もベストの時期に当たったようだ。しばし見とれ、フィルムに収めるうち、出戻りの彼が登ってきた。彼はフィルムがもう無いと悔しがっていたが、ネガフィルムの持ち合わせがなくて、お役に立てない。リバーサルフィルムは沢山あるので、こちらは写真撮りまくりだ。 小化雲岳への稜線を、展望を楽しみつつ行く。クワウンナイ川本流と化雲の沢に挟まれた、神々の庭と名付けられた台地状には、青い空を映す多くの池塘が、紅葉の錦の間に散らばっている。黄金ヶ原の黄色い台地の奥には、十勝連峰の山々がひしめいている。トムラウシ山は、まるで天然の要塞のようだ。眺めの良い所ごとに止まるので、なかなか先へ進まないが、やがて小化雲岳手前のコル付近から、道はトラバースして下り始める。小化雲岳への明瞭な踏跡はなく、池塘のある辺りから、枯れた草地を踏んで適当に登ってゆく。10時、あまり苦労せずに山頂に至る。 期待したナキウサギは居そうもないが、なんて素敵な山頂だろう。大展望を堪能しつつ、おやつを頬張る。化雲の沢源頭を見下ろせば、是非とも一度足を踏み入れたいとの思いが湧き上がってくる。30分間の至福の時を過ごした我々は、この別天地に別れを告げ、北面の草地を降りて行く。 再び登山道に合流し、やがて地獄のようなズルズル泥んこ道へと下って行くのであった。覚悟していた事とはいえ、まさに天国から地獄であった。泥んこのため、腰を下ろす場所が無く、約4時間の苦闘の末、羽衣の滝を正面に望む滝見台に至る。I君は、かなり足が痛いらしい。ここから更に、涙壁の三十数回のつづらおりを下って、天人峡温泉の車道に出た。 自動販売機のジュースを買おうとしたが、硬貨の持ち合わせがなく、断念。七福岩の駐車場まで、トボトボ車道歩きだ。15時45分、やっとのことで車に戻る。 先ずは給油のため、志比内のスタンドに向かう。空腹と渇きに苛まれる我々は、隣のAコープで、おやつと飲物を買い込んで貪り食うのであった。 |
![]()
溯行概念図
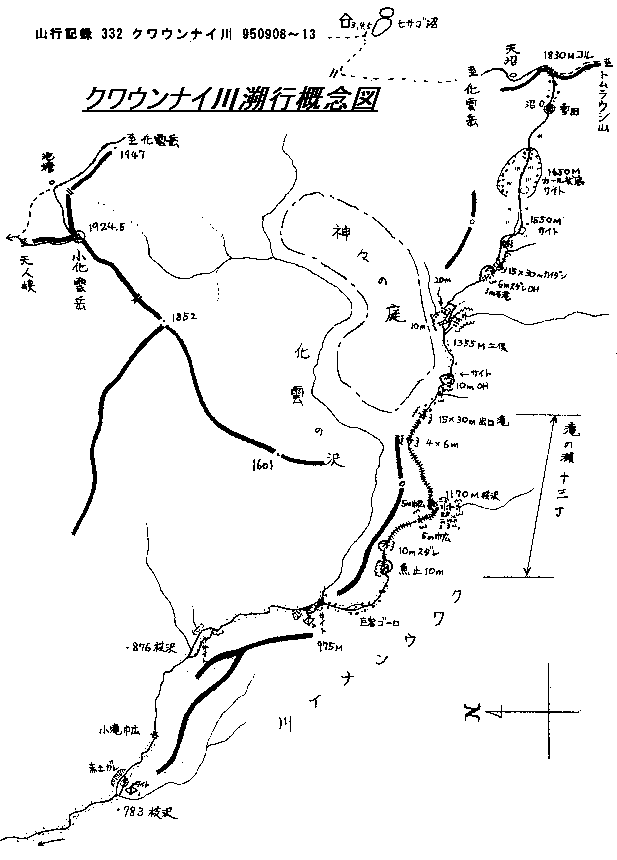
アルバム
 |
ヒサゴ沼からニペソツ山 |
| ヒサゴ沼から化雲岳へ向かう途中、トムラウシを振り返る |  |
 |
ヒサゴ沼避難小屋を振り返る |
| 化雲岳の雪田から、大雪山旭岳 |  |
 |
化雲岳の岩を目指して登る |
| 化雲岳から大雪山方面 |  |
 |
化雲沢川源頭斜面 |
| 忠別岳と忠別沼 |  |
 |
五色ヶ原と沼ノ原、石狩岳方面 |
| 化雲岳からトムラウシ山 |  |
 |
化雲岳からトムラウシ山、十勝連峰 |
| 黄金ヶ原と十勝連峰 |  |
 |
小化雲岳方面 |
| 大雪山白雲岳方面 |  |
 |
大雪山旭岳方面 |
| 五色ヶ原と石狩岳方面 |  |
 |
沼ノ原とニペソツ山 |
| トムラウシ山 |  |
 |
トムラウシ山 |
| 黄金ヶ原と十勝連峰 |  |
 |
旭岳 |
| 白雲岳 |  |
 |
紅葉 |
| 沼ノ原 |  |
 |
黄金ヶ原とオプタテシケ山 |
| カムイミンタラ |  |
 |
トムラウシ山 |
| カムイミンタラ越しに、黄金ヶ原と十勝連峰 |  |
 |
小化雲岳から、トムラウシ山方面 |
| 草紅葉の小化雲岳から黄金ヶ原越しに十勝連峰 |  |
 |
小化雲岳からトムラウシ山 |
| 小化雲岳から黄金ヶ原越しに十勝連峰 |  |
 |
小化雲岳から大雪旭岳 |
| 小化雲岳から、化雲岳とニペソツ山 |  |
 |
小化雲岳から、夕張岳・芦別岳方面か |
| 小化雲岳から、十勝連峰 |  |
 |
小化雲岳から忠別沼・武利岳・武華山方面か |
| 大雪白雲岳 |  |
 |
大雪旭岳 |
| カムイミンタラ(神々の庭) |  |
 |
化雲ノ沢・クワウンナイ川右俣と黄金ヶ原 |
| 小化雲岳から、カムイミンタラとトムラウシ山 |  |
 |
第二公園?から旭岳 |
| 滝見台から旭岳 |  |
 |
滝見台から羽衣ノ滝 |
| 滝見台から羽衣ノ滝上・中部 |  |
MR359_ トムラウシ山ナキウサギ撮影行(大雪)1997/07/21-25
![]()
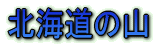 へ へ |