馬坂沢ジャーコン沢・帝釈山・田代山湿原・黒岩山・鬼怒沼・尾瀬沼(帝釈・奥鬼怒・尾瀬)
![]()
![]()
| date | 1981/9/22-25(午後発3泊) |
| コース | 川俣大橋〜馬坂橋〜栃ノ葉橋〜馬坂沢ジャーコン沢溯行〜帝釈山〜田代山〜小田代〜田代山〜帝釈山〜台倉高山〜引馬峠〜黒岩山〜鬼怒沼〜黒岩分岐〜小淵沢田代〜尾瀬沼ビジターセンター〜大江湿原〜三平峠〜大清水 |
| 実働 | 第一日:2h10m、第二日:6h50m、第三日:9h15m、第四日:6h20m、計:24h35m。 |
| メンバー | すうじい(単独) |
| 概要 | 沢登りの後、草紅葉の田代山湿原・鬼怒沼・尾瀬沼をつなぐ縦走。 |
| 行程 | =:バス・鉄道、→:山道、→:溯行、\\:藪漕ぎまたは詰め 【9月22日】 曇 北千住13:29=15:34鬼怒川温泉15:40=17:26川俣大橋17:30→19:10無砂谷橋19:20→19:25=19:45→20:10作業小屋(泊) 【9月23日】 快晴のち曇 作業小屋5:35→6:10栃ノ葉橋6:20→サル沢出合6:35→7:20オオイデ沢出合7:25→7:35小休止7:50→9:43迷いの二俣10:08→10:45\\稜線10:55→11:15コル11:25→11:55帝釈山12:05→12:45田代山太子堂12:50→小田代13:15→13:45太子堂(泊) 【9月24日】 晴のちガス 太子堂4:50→5:35帝釈山5:40→6:30小休止6:40→7:30台倉高山7:50→8:40引馬峠8;50→9:45孫兵衛前衛峰10:00\\10:50黒岩山北コル11:00\\11:50黒岩分岐12:00\\12:35黒岩山12:40\\黒岩分岐13:10\\13:25黒岩清水13:40→14:35小休止14:55→15:55鬼怒沼小屋(泊) 【9月25日】 雨 鬼怒沼小屋6:05→小松水場7:20→黒岩清水7:40\\黒岩分岐7:55→送電線下9:40→小淵沢田代10:00→10:30ビジターセンター11:50→12:05大江湿原12:15→三平峠13:00→一ノ瀬休憩所13:20→13:55大清水14:25=15:35沼田15:47=上野 |
| 記録 | 【9月22日】 曇 昼過ぎに出発して、北千住へ向かう。東武鬼怒川温泉から川俣温泉行のバスに乗り、川俣大橋で下車。ここから4夕暮れの川俣湖岸の道を歩くうち、辺りは真っ暗になる。 無砂谷橋の少し先で、後ろから来た車に便乗し、馬坂橋の2kmほど奥まで運んでもらう。さらに25分ほど馬坂林道を歩くと、作業小屋があり、そこで寝る。シュラフカバーのみだが、さほど寒くは無い。 【9月23日】 快晴のち曇 目覚めると、外は明るくなりかけている。小屋からさらに林道を歩くが、現在位置がさっぱり判明しない。しばらく行くと、栃ノ葉橋があり、林道は右岸から左岸へと渡っている。ここで、川原へと降りる。 30分ほどゴーロを行くと、3m2段の滝があり、右岸から水流の細い6m滝が落ちている。さらに4mトヨ状を越すと、2段10mCS、2段10mCSと連続し、オオイデ沢出合となる。この辺りが核心部であるが、どの滝も簡単に登れるものばかりである。 栃ノ葉橋からオオイデ沢出合まで約1時間。右俣であるジャーコン沢は、台風などのためか、ブッシュの間を流れているような感じで、左俣のオオイデ沢の方が、本流的様相を示す。 ジャーコン沢の花崗岩砂の明るい流れに足を踏み入れ、さらに1時間ほど溯ると、左手に砂のガレがあり、続いて、(5:1)、(2:1)、(2:1)と二俣がある。これらの二俣は、すべて左俣へ進むが、3つ目の二俣の左俣は、苔生した累々たる石の積み重ねを水が流れている。 ここから先は、沢筋を覆う倒木との戦いである。滝は、主として石滝となる。これを1時間ほど進むと、(2:1)の迷いの二俣に至る。正面に2本の木が立っている。足を踏み入れた右俣は、急激に水量が減るので、戻って左俣を溯る。 左手に大岩を見て、次の(1:2)の二俣を右俣に進めば、流れは細くなってチョロチョロだ。最後の(1:1)二俣で右へ行くと、すぐに水は涸れ、ツメはハリブキ混じりの藪の急登。10分ほどの藪漕ぎで、・1898Pより少し南の稜線の縦走路に出る。 ホッとして、帝釈山方面へ歩き出す。帝釈山頂を経て、田代山まで来ると、「秋分の日」であるためか、ハイカーが大勢「湿原の秋」を楽しんでいる。その中に混じって、神ノ田の草紅葉とレンゲツツジの真紅に燃える紅葉の織り成す見事な光景を、目の当たりにしたのであった。 太子堂にザックをデポして、小田代まで下ってみたが、こちらはさほどの感動を得られず、引返す。田代山まで登り返して、人々の去った山頂湿原の草紅葉を、静かに堪能する。弘法大師らの祀られた太子堂で、一人寝る。夜中に紅茶を入れて夜食を食う。 【9月24日】 晴のちガス 懐中電灯を手に太子堂を発ち、帝釈山頂に至る頃にはもう明るい。ここから先、孫兵衛山前衛峰に至るまでの笹藪は、刈払いしてあるので、大変楽である。昨日のツメ上げ地点付近で小休止し、台倉高山へと頑張る。所々に小湿原がある。 台倉高山からしばらく行くと、北西面の樹林帯を通るトラバースとなり、名も知らぬ草の実がたくさんジャージにくっつく。引馬峠から孫兵衛前衛峰までは、刈払いがしてなかったら、ハリブキ混じりのスズタケで苦労しそうである。 孫兵衛前衛峰付近から、刈払いが無くなり、深い藪を漕がされる。踏跡を懸命に追う。帝釈・奥鬼怒山域には、なんでこうハリブキが多いのだろうとウンザリしながら、背丈ほどもあるハリブキを避けながら、スズタケを漕ぐ。 黒岩山北のコルで、小休止したあと、黒岩山南東面のトラバースに入る。やや倒木とハリブキに悩まされつつ、1Pで黒岩分岐に至る。ここは、鬼怒沼林道が通っている。林道とは言っても、無論単なる山道である。 MWVの赤布に導かれ、藪を漕いで黒岩山をサブする。踏跡は、よく捜さないと判り難いが、意外なことに、ここではMWVの赤布が正確・律儀であった。分岐に戻り、15分ほど下ると、黒岩清水で、テント2張分のプラッツもある。さらに20分行くと、小松湿原の上の方に位置する辺りだが、水場とテント3-4張分のプラッツがある。 鬼怒沼山の峰々の山腹を行く頃には、完全に果て狂っていて、倒木のあるスズタケ漕ぎが鬱陶しい。鬼怒沼山のピークハントなんぞやる元気は、全く出なかった。やるとしたら、踏跡は見当たらないので、急な藪漕ぎ登りが強要されるであろう。 やっとのことで、鬼怒沼の湿原木道に立つ。既に人影は無く、ほのかに霧の懸かり始めた草紅葉の湿原。この夕暮れを独り占めし、心ゆくまで佇み、木道のベンチで夕食も済ませ、ゆっくりと沼沼の間を散策する。 夜は、ネズミがゴソゴソやっている避難小屋で寝る。夜半、雨が降り始め、小屋泊まりの有難さを噛み締める。 【9月25日】 雨 朝起きれば、雨がしっかり降っている。田代山、鬼怒沼と湿原の草紅葉を味わうと、どうしても、「尾瀬」に想いを馳せてしまう。雨の中をついて、鬼怒沼林道を踏破することにする。「尾瀬まで7時間」と書かれた道標をちらり見て、昨日の道を戻り始める。 黒岩清水までの笹藪は、刈払いしてないので、雨具を着てはいても、全身びしょ濡れとなる。雨の中、休憩も、行動食も摂れず、地下足袋の軽さでビンビン飛ばす。鬼怒沼林道は、ガイドブックに載っている一般登山道であるにも拘らず、道が悪いという定評があるようだが、まあその通りだと言えよう。 赤安山付近で、2パーティの登山者とすれ違う。赤子の手のような楓の葉が山道に落ち、雨に打たれているのを、地下足袋で踏みつつ、未だか未だかと飛ばすうち、ガスの中に送電鉄塔が現れ、間もなく大清水への下山路を分け、されに行くと、やっと小淵沢田代に至る。 立ち止まって辺りを見回すが、風雨で寒いので、すぐに尾瀬沼目指して歩き始める。鬼怒沼小屋を出発してから、ノンレストロングピッチで4時間半、ようやく沼畔のビジターセンターの屋根の下に入る。 雨具を脱ぐと、濡れた体に風が寒いので、立ったまま震えつつ行動食を食べる。紅茶をたっぷり入れて飲むと、やっと生き返るようだ。冷たい雨の中、今日の尾瀬沼は、人が少なくて、なかなか良い雰囲気だ。しばらくは雨降る中へと出て行く気はしないので、燧を眺めつつウダウダと大休止する。 その後元気回復して、大江湿原の草紅葉を見に行き、戻って三平峠へと登る。途中、振り返れば、沼と大江湿原の黄と山々の緑が、メルヘンチックな風景を見せてくれる。雨に濡れた木道も、フェルト地下足袋ならヘッチャラで、濡れた岩から岩へ跳んで下れる。三平峠から一ノ瀬まで、僅か20分で下る。 大清水の東武バス待合所は、立派になっていた。タクシーで沼田へ出る。 |
![]()
概念図
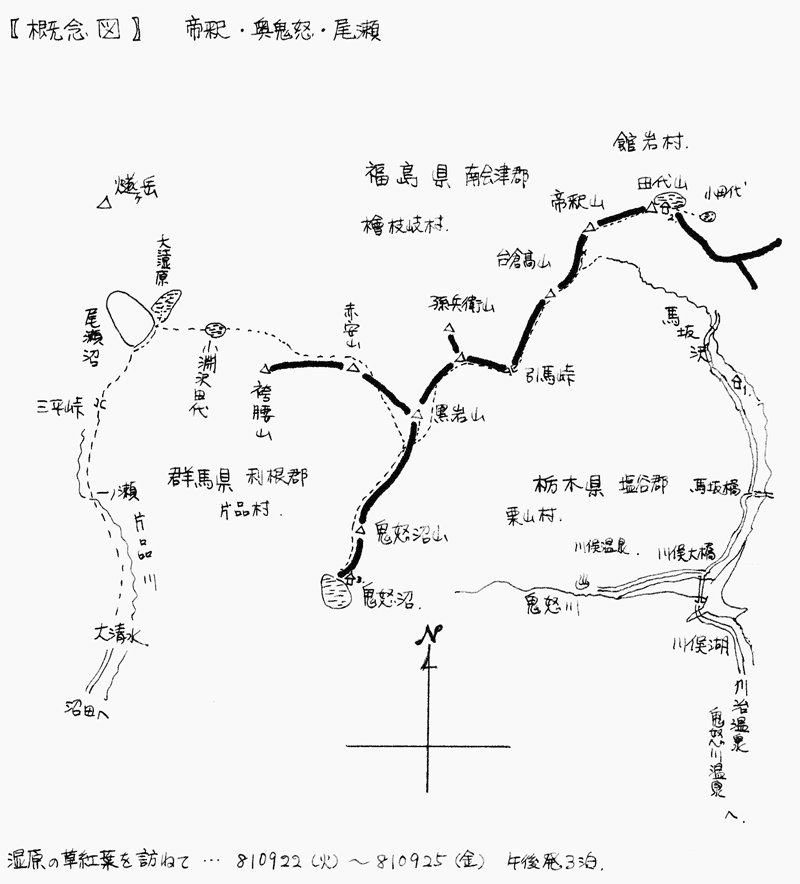
溯行図
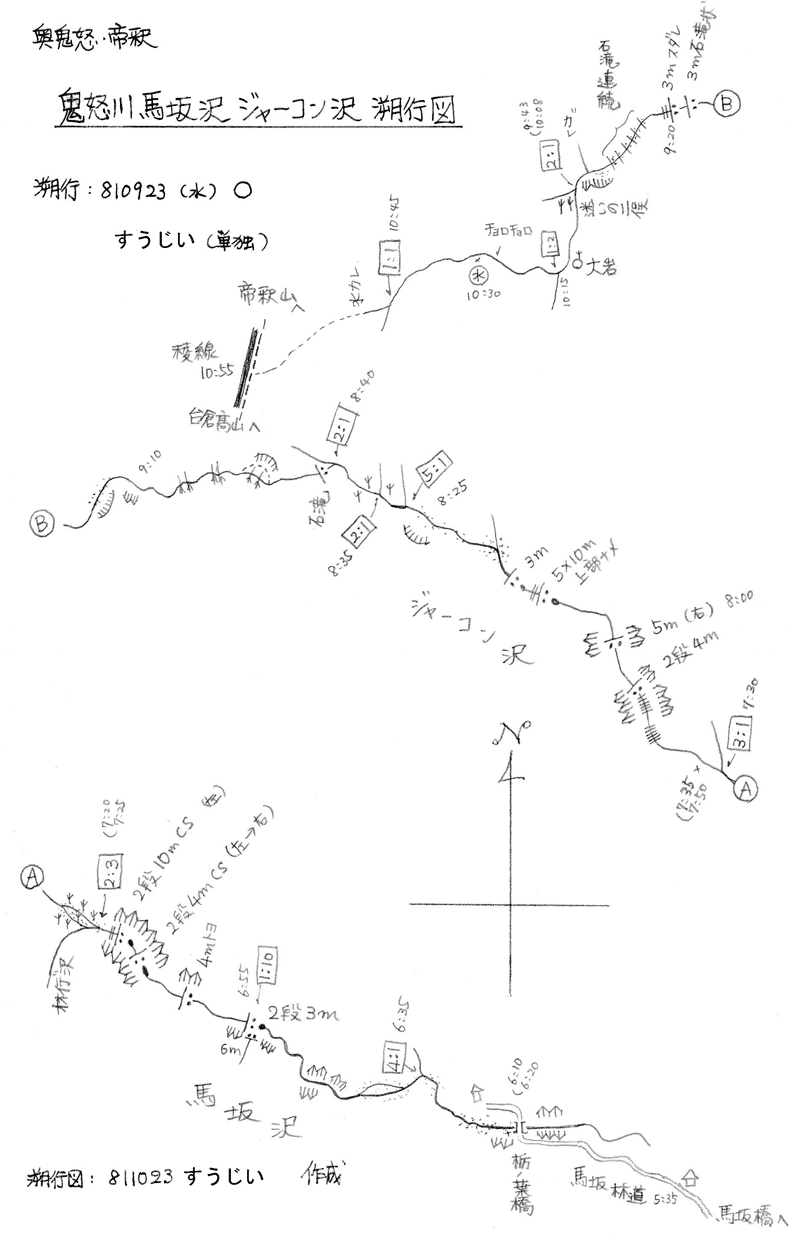
![]()
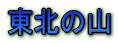 へ へ |
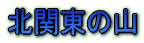 へ へ |