笛吹川ヌク沢・木賊山・鶏冠尾根下降(奥秩父)
![]()

| date | 2009/10/31 快晴 |
| コース | 西沢渓谷駐車場〜近丸新道〜ヌク沢左俣右沢〜木賊山〜鶏冠尾根下降〜鶏冠谷出合〜西沢渓谷駐車場 |
| 実働 | 登り:5h43m、下り:6h25m、計:12h08m。 |
| 概要 | ヌク沢溯行、鶏冠尾根上部の藪漕ぎ、夜の鶏冠尾根下降。 |
| メンバー | Tds君、すうじい |
| 行程 | →:山道、→:溯下行、→:藪漕ぎ・踏跡不明瞭、=:交通機関。 【10月31日】 快晴 自宅3:05=6:00駐車場6:25→7:20 H13堰堤下入渓点7:40→8:53 H9堰堤上9:15→10:10 大滝下段下10:45→11:05中段下11:25→11:55上段下12:15→2100M左岸ガレ水汲み13:00→→13:48縦走路14:08→木賊山14:25→鶏冠尾根入口14:28→15:35休15:45→・2177北東コル15:55→・2177 16:00→・2115鶏冠山16:40→・1986ヘッドライト装着17:17→→17:50 1910M付近(迷う)18:10→→1800Mトラバース開始18:45→1695M尾根復帰19:10→19:35 1630M付近19:50→20:40鶏冠谷出合20:55→遊歩道21:05→21:50駐車場21:55=1:45自宅 |
| 使用装備 | 渓流靴、μ-725SW、ヘルメット、E-1、ED12-60mmF2.8-4、三脚、軽登山靴 |
| 不用装備 | 8mmx30mザイル、8環、ハーネス、ハーケン、アイスハンマー |
| 記録 | 今回は、GPSが極めて有効であった。日の短いこの時期に、木賊山から鶏冠尾根へ向かうのは、正午までにすべきであった。 【10月31日】 快晴 西沢渓谷の無料駐車場を振り返ると、R140のループ橋後方には、朝日を浴びる鶏冠尾根が立派である。あの尾根の下降で暗くなり、ここに戻ってくるのが、15時間半後になろうとは、この時知る由も無かった。しばらく、笛吹川左岸沿いの林道を歩くが、ナレイ沢の紅葉もなかなかだ。 ヌク沢橋手前で、鶏冠山林道東線が分岐し、その付け根のヌク沢左岸尾根に、近丸新道入口がある。しばらく、急登が続く。やがて、平坦なトラバース道が始まり、軌道跡も現れる。この辺り、紅葉が美しい。最近、殆どの登山者が徳ちゃん新道を使うためか、近丸新道には崩れ掛けた所が結構ある。 再び、どんどん登るようになって、汗をかかされる。やっと下り気味になり、ヌク沢に出ると、H13堰堤が聳え立つ。小休後、左岸から巻くが、この巻きが今山行中一番イヤらしかった。 H13堰堤を左岸から巻き、溯行を開始する。少し行けば、ナメが始まる。水流沿いを進むも良し、何となく踏まれた岸を歩くも良し。時間短縮のため、なるべく後者を選択する。紅葉は盛りを過ぎたようだが、良い雰囲気である。 1465M右岸枝沢が出合うと、本流には奥にH6堰堤が見えてくる。H6堰堤直前に、左岸から1480M枝沢が出合う。H6堰堤下に出れば、いよいよ、H6-H9からなる4連続堰堤の始まりだ。H6堰堤には、最初に出くわしたH13堰堤と比べたら、遙かにましな踏跡が、左岸に付いているので、これを辿る。 H6堰堤を過ぎると、1510M付近で左岸に大崩壊ガレ斜面が現れる。ガレの上方には、あの鶏冠山林道東線があるようだ。この辺りで、右岸に台地状の地形が見られ、踏跡の「匂い」がしたので、右岸斜面に取り付いてみた。これが正解で、台地状の上に、林道跡のような道形を発見する。振り返ると、どうやらH6堰堤付近から続いているようだ。これでH7、H8、H9と、三つの堰堤を全て右岸道形で巻けそうだ 右岸の道形を辿ると、思惑通り、H7堰堤が現れる。高度を変えずに、楽々と通過する。続いて、H8堰堤も通過するが、高度を変えずに、そのまま右岸を進む。沢は、二俣(実際は三俣状)となって、水量の少ない滝を懸けて出合う右俣左岸の枝沢上方に林道の橋が見える。 左俣に設けられたH9堰堤付近は、右岸に崩壊があるので、少し高巻く必要がある。この高巻き途中で、大滝中段と思しき滝が遠望される。期待が膨らむ。H9堰堤上へと無事降り立って、やっと本格的な溯行モードとなる。 左俣を進むと、先ず4m滝が現れ、右から越える。続いて、4m2条滑滝を越え、水量比(1:2)の1630M奥二俣は、右沢が本流である。滑床状を進むと、右岸から1660M枝沢を迎え、本流には3mナメ幅広が懸かる。 やがて、倒木に埋まりがちな、前衛ゴルジュが始まる。結構な連瀑帯なのだが、下部は倒木が鬱陶しい。右岸通しに、バンド状を登って行く。前衛ゴルジュ出口の滝を、右岸から越えると、いよいよ大滝の下に出る。 大滝は、3段260mとされており、下からは、下段100mの下部〜中部しか見えない。下段100mを見上げながら、左岸で休憩を入れよう。大滝下段下部〜中間部は、左岸側の階段状草付斜面状右壁を適当に登る。 上部では、左岸側から樹林帯が迫り出して来るので、この藪を漕ぐ手もありそうだ。一般的には、水流を渡って、左壁を登ることになる。下段上部トヨ状の上には、中段下部が見えている。左壁上部を登って行くと、落口へ抜けるところが少しイヤらしいが、慎重に行けばザイルは不要だろう。 落口を抜けたテラスは、大滝中段80mの真ん前である。ここからは、中段の下部〜中間部までが見えている。軟弱ルート取付付近から、中段下部右壁を見上げる。今回は、8mmx30mザイルしか用意しておらず、ザイルは使わずに右端ガリー沿いを登ることにしよう。 右手の小尾根から回り込むように、岩壁下をトラバースし、右壁右端ガリーに取り付く。振り返れば、中段下テラスの下段落口越しに、ヌク沢左岸尾根の林道が見えている。右端ガリーを登って行くと、途中一旦水流へと近付くことが出来る。この日は、水量が少な目であったが、岩の上を迸る流れが嬉しい。 再び右端を登り、やがて落口上へと斜上して、上段下テラスに出る。中段は、かなり開けた状態になっている。おそらく、他所から遠望しても、良く見えるに違いない。 上段80mの下に立つと、「いくら何でも、これは80m無いだろ・・・」と思うのだが、登ってみると、上の方に続く結構長い滝であった。上段は、左壁を登って行く。傾斜はやや緩く、草付混じりで、慎重に登ればさほど問題は無い。 中程で、右岸大岩を越える。そこからトヨ状の水流を跨いで、左岸へと移る。水量が多いと、大変そうだ。上段最上部もトヨ状になっているが、そのまま左岸側草付混じりを登って行く。こうして、大滝3段260mが終了する。 大滝上の滑床を進むと、8x 12mトヨナメ上2条が現れる。この滝が、最後の滝らしい滝となる。その後は、源流のナメが続く。源流ナメに飽きる頃、左岸側にガレが出現し、伏流気味のゴーロになるので、水汲み休憩とする。 傾斜が再び増し、ゴーロを登って行くと、右岸に大ガレが出現する。そろそろ踏跡が出てくるのでは・・・と期待しながら左岸側に目を配りながら進むが、それらしき形跡は無い。徐々に、足取りが重くなる。 沢床の低い方を選びながら進むと、沢筋には次第に針葉樹の藪が濃くなり、たまらず左岸に逃げる。縞枯状を利用して、登って行くと、再び樹林帯に入る。獣道を拾いながら、樹林を漕いで行くと、やがて稜線の縦走路に飛び出す。 縦走路に出て小休していると、小屋のボッカの男性、そして単独の縦走者が通り掛かる。ここから10分ほどで、戸渡尾根分岐まで登る。木賊山山頂までは、もう少しだ。展望の無い三角点を踏み、すぐに引き返す。 少し戻って、鶏冠尾根目指して藪を漕ぐ。踏跡は、極めて薄い。幅広の尾根を、2410M付近まで南下し、右手の樹林帯斜面の目印と踏跡を辿る。この目印と踏跡は、迷い沢源頭へと続く小尾根に向かう。2350M付近で、これは迷い沢を詰めた沢屋の踏跡だろうと考え、南東側の正解尾根へとトラバースを開始する。 幸い大した藪も無く、獣道状を利用して、2330M付近で、正解尾根に復帰する。2280MPから鶏冠山方面を望むと、まだまだ遠いのが判る。前回Ts君がYh師匠と鶏冠谷から突き上げた2185M付近から、木賊山を振り返る。 ・2177の展望ピークに辿り着いたのは、既に午後4時であった。取り敢えず、振り返って木賊山と甲武信岳を撮影しておこう。木賊尾根の核心部は、まだまだ先である。・2177から40分掛かって、・2115鶏冠山に到着した。かなり薄暗いが、残照を利用して稜線を辿る。 第三岩峰横からは、北東側を巻き下る。その先の・1986で、ヘッドライトを装着する。もう、辺りは真っ暗だ。これから先が、苦労の連続だった。「尺取り虫作戦」と名付けた方法を採る。目印の場所にすうじいが残り、一度このコースを下っているTds君が、その先の踏跡と目印を探す。コンパスとGPSで、方角・位置・高度を確認しつつ、ライトと掛け声で合図しながら、一つ一つ目印を探して下った。 特に、1900M付近が、最も迷った地点であった。踏跡は、東南東へ向かうべき本来の尾根筋から離れ、1800M付近の崖マークを避けて南へと下り、1820M付近から岩壁下トラバースをして、1700M付近で尾根に復帰するのである。 1820M付近で岩壁下トラバースが始まると、ようやく現在位置とルートに自信が持てた。1695M付近で尾根に復帰し、あとはひたすら尾根沿いに下降して行く。鶏冠谷出合に降り立ち、登山靴を再び渓流靴に履き替え終わったのは、午後9時少し前であった。 月夜であることが幸いして、東沢本流を問題なく徒渉し、右岸沿いに下ると、間もなく東沢橋で遊歩道に出る。西沢渓谷駐車場の車に戻ったのは、午後10時少し前であった。こうして、長い一日が終わった。 |
![]()
![]()
GPS軌跡

近丸新道をかなり進んでから、GPSの電源をON
溯行図
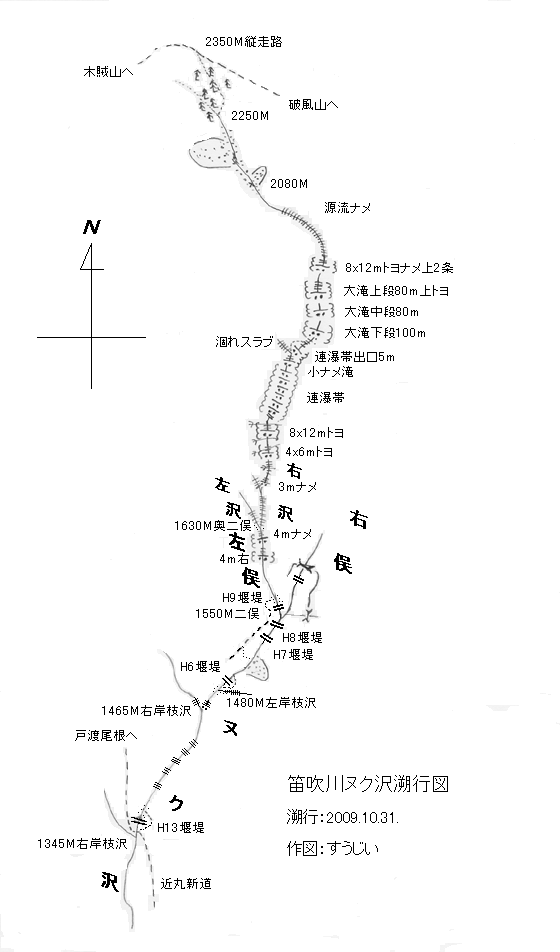
アルバム
 |
西沢渓谷駐車場、ループ橋の上に鶏冠尾根 |
| ナレイ沢ナレイ滝か |  |
 |
近丸新道入口 |
| 軌道跡 |  |
 |
H13堰堤 |
| ナメ |  |
 |
ナメと紅葉 |
| 1465M右岸枝沢 |  |
 |
H6堰堤現る |
| 1480M左岸枝沢 |  |
 |
H6堰堤 |
| H6堰堤左岸巻道 |  |
 |
左岸ガレ |
| 右岸道形に出る |  |
 |
右岸道形を振り返る H6堰堤付近から続いているようだ |
| H7堰堤 |  |
 |
H8堰堤 |
| 右俣左岸枝沢と橋 |  |
 |
左俣に築かれたH9堰堤 |
| H9堰堤の右岸高巻き途中で、大滝遠望 |  |
 |
左俣4m |
| 左俣4m |  |
 |
左俣4mナメ2条 これを越えると奥二俣 |
| 1630M奥二俣は、本流の右沢に入る |  |
 |
1660M右岸枝沢出合本流3mナメ |
| 大滝前衛連瀑帯は、少々ボサが鬱陶しい |  |
 |
大滝前衛ゴルジュ出口 |
| 大滝前衛ゴルジュ出口滝は、右岸から越える |  |
 |
大滝下段100m |
| 大滝下段100m |  |
 |
下段中間部 |
| 下段中間部右壁 |  |
 |
下段上部と中段 |
| 大滝中段80m |  |
 |
中段下部右壁は、クラック状に取付く |
| 中段下部 |  |
 |
中段下部より鶏冠山林道東線 |
| 中段中上部 |  |
 |
中段中上部 |
| 中段落口より俯瞰 |  |
 |
大滝上段80m |
| 大滝上段80m |  |
 |
大滝上段上部 |
| 上段上部横断点を俯瞰 |  |
 |
上段最上部 |
| 上段最上部より俯瞰 |  |
 |
8x12mトヨナメ上2条 |
| 源流ナメが続く |  |
 |
源流ナメが続く |
| 2130M付近の右岸大ガレ |  |
 |
木賊山山頂 |
| 2310M付近 |  |
 |
2310M付近 |
| 2280MPから |  |
 |
2185M付近から木賊山 |
| ・2177Pから.木賊山と甲武信岳 |  |
 |
・2177から鶏冠山 |
| 2020M第三岩峰横 |  |
 |
2020M第三岩峰横 |
| 岩壁下トラバース |  |
 |
東沢橋 |
![]()
 へ へ |