|

アカヤシオの両神山剣ヶ峰(1978年5月2日)
【両神山の範囲】
「両神山」(実業之日本社刊)を著した飯野頼治氏によれば、
「両神山の範囲は、東は一位ヶタワ、西は狩倉岳の手前、南はヒゴノタオ、北は八丁峠。
さらに、両神山塊という広い範囲を考えるならば、
東は天理ヶ岳、辺見ヶ岳(二子山)、西は赤岩山、南は梵天ノ頭、北は群馬との県界尾根1207M三角点まで。
この範囲は、剣ヶ峰の三角点を中心として、半径3km以内に丁度収まる山域である。」
【両神山の地質】
両神山を形成する主な岩石は、チャートと呼ばれるもので、
角岩とも言い、火打ち石に使われたものも、この仲間だそうだ。
チャートは硬くて風化に強いので、ギザギザした尾根や絶壁を形成しやすい。
まさに、両神山の特徴ある地形は、このチャートの特性を表現しているわけだ。
【両神山の山系】
両神山山頂の剣ヶ峰から西岳へと続く八丁尾根の主脈、そこから様々な尾根が派生している。
剣ヶ峰から北へ続く主脈は、東岳・西岳・八丁峠を経て、群馬県との県界尾根となり、
赤岩尾根から天丸山方面へと至る。
また、八丁峠の西、P1から志賀坂峠、二子山へ至る尾根を派生させる。
剣ヶ峰から東へ延びる尾根(辺見尾根)は、産泰尾根を派生させ、三笠山・辺見岳・両見山を経て、四阿屋山に至る。
剣ヶ峰から南へ延びる梵天尾根は、すぐに西へ狩倉尾根を派生し、梵天から秩父御岳へと続く。
前東岳からは、天理ヶ岳尾根が東へと延び、天理ヶ岳・奈良尾沢峠を経て、両詰山へと続く。
西岳からは、西岳尾根が北東へと延びる。
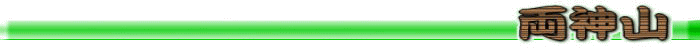
 について
について